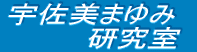| 2012年 |
| 2012b |
「理性が導くことを情熱を持って実行する」『亜細亜大学 経営学部 Interview 2012』亜細亜大学 経営学部:17. 1頁. |
| 2012a |
「高齢者とコミュニケーション」『治療』94(2)(Series「医療を適切に受けるためのポライトネス・ストラテジー(12)」)、南山堂:184-185、2頁. |
| 2011年 |
| 2011b |
「外部評価員による評価②」『多文化共生時代の協働による日本語教員養成―体験活動での教育効果を高めるWEBダイアリーの活用―』, 京都外国語大学:2011年3月. |
| 2011a |
「高齢者との円滑なコミュニケーションの基本にあるもの」『WAM』560、法研:26-27. 2頁. |
| 2010年 |
| 2010 |
「高齢者とのコミュニケーションのとり方 - 保護するような話し方から対等で普通の話し方へ -」『自動車学校』46(12)、啓正社:11-13. 3頁. |
| 2004年 |
| 2004 |
「年賀状のゆくえ」『月刊言語』33(1) (1月号特集「島のことば」)、大修館書店: 4-5. 2頁. |
| 2002年 |
| 2002 |
「マルチメディアとコミュニケーション」(パネルディスカッション録、国際交通安全シンポジウム、2000年9月29日)『車社会はどう変わるか』、文芸社: 56-112. 57頁. |
| 2001年 |
| 2001 |
「システムネットワークによる授業の変化 (4)」『東外大ニュース』108 (特集: 新キャンパスから広がるネットワーク)、東京外国語大学: 8. 1頁. |
| 2000年 |
| 2000 |
「日本語から見た日本文化」『平成11年度北区の国際化推進事業』: 58-91. 34頁. |
| 1999年 |
| 1999 |
「日本語を学ぶ若者から見た日本語」『教育と情報』497、文部省大臣官房調査統計企画課編集: 18-21. 4頁. |
| 1998年 |
| 1998e |
「自由席: 言葉と思考 -「~らしい」の危険性」『週間教育資料』590、教育公論社: 50. 1頁. |
| 1998d |
「ポジティブ・ポライトネスとネガティブ・ポライトネス」『Tradepia』7、日商岩井株式会社: 20-23. 4頁. |
| 1998c |
「女性と言葉と日本社会」『SQUARE』110、労働情報センター: 20-21. 2頁. |
| 1998b |
「高齢者を活気づける広告コミュニケーション」『月刊宣伝会議』4、宣伝会議: 48-50. 3頁. |
| 1998a |
「女言葉、男言葉」『総合教育技術』3、小学館: 10-11. 2頁. |
| 1997年 |
| 1997 |
「女の子の「男言葉」」『東京新聞』 (日刊). 8月28日付. |
| 1993年 |
| 1993 |
「外国人体験が日本人として日本語教師としての自分を育てる」『月刊日本語』6(2)、アルク: 26-29. 4頁. |
| 1992年 |
| 1992 |
「大切なのは外国語ができることではなく、うまく教えられる力 -西川寿美、森山武氏との対談録」『月刊日本語』5(9)、アルク: 7-12. 6頁. |
| 1990年 |
| 1990 |
「アメリカの大学で教える」『アルク地球人ムック』59 (海外就職: 特集 日本語を教える)、アルク: 71-73. 3頁. |
| 1989年 |
| 1989d |
「あなたの適性は? 国際派感覚で教えたい人たちへ -倉持保男、丸山敬介両氏との対談録」『月刊日本語』2(10)、アルク: 8-14. 7頁. |
| 1989c |
「じっくり話し合える研修会 -アメリカ・オハイオ州」『月刊日本語』2(7)、アルク: 90-91. 2頁. |
| 1989b |
「OPI試験官養成の講座受講レポート」『月刊日本語』2(6)、アルク: 96-97. 2頁. |
| 1989a |
「テキストの開発に向けて」『月刊日本語』2(2)、アルク: 92-93. 2頁. |
| 1988年 |
| 1988 |
「経験者よ、来たれ」『月刊日本語』1(12) (特集-アメリカで日本語を教える)、アルク: 14-17. 4頁. |