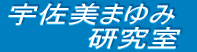 |
Home>研究業績>招待講演・シンポジウム・ワークショップ講師等>ディスコース・ポライトネス理論と日本語教育 |
|
「ディスコース・ポライトネス理論と日本語教育」 |
|
Brown & Levinsonが定義した日本語で言う「丁寧さ」とは全く性質を異にする「ポライトネス(politeness)」という概念(ポジティブ・ポライトネス)を日本語に適用して解釈すると、例えば、「冗談を言うことによって円滑なコミュニケーションができるのであれば、敬語を使っていなくても『ポライトだ』と捉える」というこれまでとは違った新しい言語行動の見方が可能になる。これからの言語教育は、人間関係を円滑に進めるための「コミュニケーション教育」として捉える必要があることが主張されて久しいが、そういう文脈の中で、「ポライトネス理論」は、大変興味深い視点を提供してくれる。 しかし、この包括的な理論も、基本的に、言語行動を発話行為レベルで捉えているために、細かい部分を検討していくと、敬語を有する言語とそうでない言語におけるポライトネスを同じ枠組みで捉えることができる真の意味での普遍理論になっているとは言い難い。そのため、ここでは、さらに一歩踏み込んで、Brown & Levinsonのポライトネス理論では扱っておらず、また、Leechなども語用論の対象として考えていなかった「相対的ポライトネス」という捉え方を核として発展させてきた「ディスコース・ポライトネス理論」を紹介し、その上で、この理論と日本語教育、異文化間コミュニケーションとの関係、これからの日本語教育における待遇表現の具体的な指導法や、注意すべき点などについて考える。 |