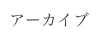〈制度性〉の思考へのプロローグ
(『中村雄二郎著作集』第Ⅱ期月報8)
〈制度性〉の思考へのプロローグ
(『中村雄二郎著作集』第Ⅱ期月報8)







〈宗教〉と呼ばれる現象はある意味では全体的である。というのも、〈宗教〉は一方であらゆる人間の生活を規定するようでありながら、また個人の内面の問題でもあるように思われるからだ。〈宗教〉のうちには政治もあれば経済もあり、思想もあれば芸術もあり、なにより生の実現がある。たとえばキリスト教中世では、〈宗教〉はひとが選び取る対象ではなく、生きる世界の枠組みを与える壮大な制度の伽藍のようなものだった。ひとはそこで空気を呼吸するように、祈りの世界に生きていた。ところが現代の世界では、一部の特殊とみなされた地域を除けば、どこの社会でも〈宗教〉はいわば継子扱いされている。それはある種の社会的寛容によって「容認」されているのであって、不可欠なものでないどころか、公共的には「黙過」される存在にすぎない。多くの人は信仰など顧みることなく生きており、生の充実は〈宗教〉とは無縁なところに見いだされる。むしろそれが通常の「幸福」であって、「宗教に頼る人はどこか不幸なのだ」と言われたりもする。
ある意味ではそれは簡単な話で、〈宗教〉のステイタスが歴史的に変わったのである。その変化は通常〈世俗化〉というタームで表現される。人間が一般的に、世界の説明原理や根拠を問うときに、神のようなものに依拠しなくなり、すべてを地上的な原理で合理的に解釈するようになったということである。かつては人間は自分が世界の主人だなどとは思っていなかったが、今では人間は自分の権能の限界というものを知らない。〈宗教〉が人間の有限性の自覚と結びついているとすれば、無力な人間が世界ともつ関係は「宗教的」だっただろう。けれども近代以降は、人間にとって世界は扱いうる対象として現れ、信仰のたぐいは個人の内面の関心事としてしか場をもたない。そして〈宗教〉が「公共空間」に侵入してくると、それは越権行為として非難され、「宗教の政治化」が取りざたされる。
いわゆる「政教分離」という近代社会の原則がある。信仰が個人の内面の関心事であるかぎり「信教の自由」は保証されるが、公共の場にはもちだせないということだ。このとき〈公共性〉というのはギリシアのポリスを元にしたポリティックな空間、つまり「市民社会」の謂いでもあるが、そこには〈学知〉の流通も含まれている。というのも、そのような原則を支える言説を生みだし支えるのは〈学知〉なのだ。それに何よりその〈学知〉、つまり神の要請に従うのではなく、地上的な原理に従って合理的にものごとを把握し、そこから依拠すべき〈真理〉を導き出す〈学知〉が、根本のところで〈世俗化〉を推進したのである。
〈宗教〉についての論議が複雑になるのは、実はそのことに関わっている。というのは、〈宗教(religion)〉という概念が、キリスト教以外の類比しうる諸現象を覆う一般概念として確立され、キリスト教からシャーマニズムや自然信仰まで、すべてが〈宗教〉として語られるようになったのは、それ自体「世俗的」な近代の〈学知〉によってだからである。つまり〈宗教〉という概念は、それによって指示されるものが大きく変容するプロセスと不可分に作られてきたということだ。言いかえれば〈宗教〉は、社会一般の意識、とりわけ知的意識が、そう呼ばれるものから離脱したと“信じられた”ときはじめて、外部から観察の対象として措定されたのである。
そのために〈宗教〉に関する論議はいつも曖昧になり、概念そのものが視点によって、万華鏡のように変化する。それは〈宗教〉を扱う言説が、〈宗教〉を離脱したという別の信憑を含んでおり、〈宗教〉とは違う、しかしそれとオルタナティヴでありうるある種の〈制度性〉に依拠しているからである。
世俗化した現代の社会で「信仰」を問うとき、「宗教は必要だ」とか「宗教を必要とする人々がいる」と言うとき、ひとは〈宗教〉を認めているのか、あるいは許容しながら根底では否定しているのか。〈宗教〉を個人的救済のための避難所としたり、政治的な馴致や動員の手段にしたりしないとすると、〈宗教〉にはどういうあり方が可能なのか、手段でない〈宗教〉とは、……そういった疑問が次々に湧いてくる。
中村雄二郎氏の『悪の哲学ノート』や『日本文化における罪と罰』を読んで、さまざまに啓発されながら、思い浮かべたのはつい最近観た、ベラルーシのルポルタージュ作家スベトラーナ・アレクシイエービッチを取材した番組『愛と哀しみの大地−−ロシア・小さき人々の記録』である。アレクシイエービッチは、独ソ戦を男たちといっしょに戦った旧ソ連の女性兵士たちの証言集『戦争は女の顔をしていない』でデビューし、その後『アフガン帰還兵の証言』や、原発事故の被爆者たちを取材した『チェルノブイリの祈り』、あるいは、ソ連崩壊によってそれまでの生活や信条のすべてを否定されて自殺した何十万という人々の物語『死に魅せられた人々』などを書いている。彼女が取り上げるのはもちろん、いわゆる歴史を導いた人々ではなく、ソビエト連邦という「ユートピア」に生まれ育ち、〈世界戦争〉の時代にそれぞれのささやかな生活を国家の恣意によって翻弄されてきた「小さき人々」である。
その中に、あるアフガン帰還兵の話がある。あるとき彼は凶悪犯として逮捕された。アフガン帰還兵には特有の手口があるという。死体の惨殺状態を見れば、通常の犯罪者でないことが明らかだというのだ。彼には犯行時の記憶がなかった。ゲリラ戦の戦場で凄惨な行為を強いられ、軍からは口外してはいけないと言われ、残虐行為に及ぶとき、兵士たちは自分たちのすることから目をそらして、狂気の獣のように行動するのだ。その狂気が、返ってきた日常のなかでときに目を覚ましてしまう。だが、そのときは意識の方が不在を装うのだ。
戦場から帰ってきた彼は、祖国のために尽くした英雄だった。ところが、凶悪犯となり、ソ連崩壊で彼の戦場での行為を正当化する「祖国」はすでになく、それまで息子を誇りに思いそれだけを生き甲斐にしてきた母親は、長い刑務所通いをつづけながら、世間の指弾を受けねばならないことで息子をなじる。やっと刑期を短縮して出所した息子は、しかし母親のもとには帰らず、キリスト教系のある宗教団体に入ってしまう。その息子に会いに教会を訪ねた母親は、息子を理解しない母親として信徒たちの前で執拗に非難され、赦しを請うて神に祈ることを強いられる。すべてを失ったこの母親は自殺こそしなかったが、彼女の身の置きどころはもはや精神病院にしかなかった。
ソ連という国家は、共産主義によって原理上〈宗教〉を否定していながら、指導者の「ミイラ」に巡礼することがその一体性を支えたような国である。この国家は「宗教的」なのかそうでないのか。けれどもこの両義性は近代のあらゆる〈国民国家〉にあてはまる。「世俗的」であるはずのどの〈国民国家〉も、死者の墓碑を建立し〈国民〉として〈国家〉に献身することを要求するのだ。ナショナリズムとはその意味で、世俗化した社会で宗教的信仰の何かを代替している。そして近代の〈国家〉とは「見えない教会」でもある。
そのような世俗社会のシステムのなかで、国家(その暴力装置としての軍隊)と新興宗教と精神病院しか行き場のない人たちが無数にいる。ソ連は何も特別な国家ではない。近代の産業システムのなかで技術的管理の貫かれる社会の組織原理を、「ユートピア的」に誇張しただけである。このエピソードに端的に示されているのは、もはや人間と社会の運命を語るのに、〈宗教〉とか〈世俗化〉といったタームはそれ自体何も明らかにはしないのではないかということだ。あるいは〈宗教〉と〈政治〉を別のものと考えることも、〈学知〉と〈宗教〉を混同することもできない。
〈宗教〉がいやが上にも問い直され、〈世俗化〉の年季がきたとも思われる現代の世界で、おそらくいま必要なのは、〈宗教〉とは違う、しかしそれとオルタナティヴでありうるある種の〈制度性〉、〈宗教〉であれ〈世俗社会〉であれ、そうしたタームに頼らず、人間を生かす一般的な〈制度性〉について語る視点を見いだすことだろう。〈学知〉に拠る者には、それによってしか二〇世紀世界の経験の先に、ありうべき人間の姿も社会も思い描くことはできないだろう。〈宗教〉と〈悪〉の問題を扱った後に中村氏が発表した『述語的世界と制度』の考察は、おそらくその方向を探る試みだとも言えるだろう。(『中村雄二郎著作集』第Ⅱ期月報8、岩波書店、2000年12月)