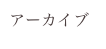『「テロとの戦争」とは何か』はしがき







「テロとの戦争」は政治的キャッチフレーズとして驚くべき成功をおさめた。九月一一日の事件をアメリカ政府は直ちに理解し、なぜあのような攻撃がアメリカに対してなされたのかをも理解した。だからこそ即座に、かつてCIAの協力者だったビンラディンを首謀者として名指してできたのだ。要するにこの事件には、歴代アメリカ政府の見えない政策が深く関与しているということだ。
にもかかわらずそのすべてに蓋をして、受けた攻撃の「無法」だけを強調するのが「テロリスト」という言葉だ。「テロはいけない」ということに誰もが納得する。だが、だからといって「テロリスト」と疑われたらその人間からあらゆる存在の権利を抹消してよいということにはならない。ところがアメリカ政府はその論理を押し通すのに成功した。そして新しくはないこの言葉を鋳直して、ひとつの新しい人間のカテゴリーを作り出したのである。つまり犯罪者としても捕虜としても扱われず、いっさいの権利も存在も容認されないモンスター、洞窟で殲滅されるか、ただ蠢く囚人として人目の届かない熱帯の刑務所に放棄される、そういうたぐいの人間だ。「人権」とか「人道的扱い」といったものは、「テロリスト」には適用されない。彼らはただ、罪を問われず殺しうる、「人間」から締め出された存在として認定されるのだ。
二〇世紀の世界は戦争による大量殺戮の経験から、つまりは国家装置の強制による破壊と暴力の経験から、「人権」や「人道に対する罪」といった概念を作り出し、個々の人間を守る智恵を尽くしてきた。だが今のアメリカ政府は、「テロリスト」というカテゴリーを再発明することによって、国家の行為を縛るこのような装置を排除することに成功したのである。「テロリスト」の適用範囲は容易に拡張される。それを「保護する者」も「われわれの側につかない者」も、「テロリストの同類」だ。そして「テロリスト」は事前に、あらかじめ除去されねばならない。先制攻撃が必要だというのだ。そのために「テロとの戦争」が組織される。この論理は「非国家組織」(NGO?)ばかりでなく、個人にも、国家(ならず者国家)にも自在に適用され、「戦争」は世界規模でだけでなく、国内的にも展開しうる。だから国内に問題を抱える多くの国の政府は、この「戦争」に参加しようとするのだ。
「テロとの戦争」の当面の結果が、アフガニスタンの徹底的な破壊であり、さらには「最悪」を更新し続けるパレスチナの惨状である。「テロリストとそれを匿う者」ならどんな手段を使って撲滅してもかわまない、いや「文明世界」の「安全」のために殲滅しなければならない、ブッシュとその仲間がそう宣言し、世界の主要国の首脳たちはそれを認めた。だからアリエル・シャロンは、我意を得たりと大手を振ってパレスチナ民衆の大虐殺に軍隊を動員しているのだ。
メディアも勇んで「テロとの戦争」のラッパを吹いた。そのなかでイギリスのBBCは早くから「テロ」という用語の不使用を決めている。よくもあしくも大英帝国の遺産であるこの放送局は、「国内の視聴者だけでなく、全世界の視聴者を意識して」、「信頼される」国際的報道機関の役割を担おうとしている。アフガン難民たちが耳を傾けていたのもこの放送局だ。そのBBCは、「テロ」のような主観的用語を使えば放送の公平・公正の評価を失うことになるとして、その語を廃して「攻撃(アタック)」という言葉を使う(たとえば「自爆攻撃」というふうに)。
一般に「テロ」は定義できない用語だと言われている。その定義できない語をまるで自明であるかのように扱って、政治学者たちまでが「テロは許せない」と平気で公言する。そこからしか思考が始まらないなら、それはあらかじめアメリカ政府の敷いた路線のうえでものを言うことである。今では「テロ」(あるいは「テロリスト」)とは、問答無用で抹消できる「非人間」のカテゴリーを作り出す言葉になってしまった。「テロとの戦争」を容認したあらゆる者が現在のパレスチナの惨状に責任があるように、ブッシュが「テロ」と呼ぶものを鸚鵡返しで「テロ」と呼ぶ者はまた、自分が定義できない言葉で多くの無辜の人びとの殺戮を許しているのだということを知るべきだろう。ひとを無反省な排除へと駆り立てる「テロ」という言葉自体にすでに罠がある。それは誰が好んで使う言葉なのか。「テロ」という言葉で事態を語ることそのものが、いっさいの道理を押し潰す国家的暴力の無法に道を開くのだということを知らなければならない。
* * *
この本は、昨年九月一一日の事件以来、事態の推移にしたがっていくつかの雑誌に書いてきたものを、ほぼ時系列に沿ってまとめたものである。ひとつひとつの文章には、発表した雑誌の性格もある程度反映されているし、書かれたそれぞれの時点でクローズアプされる局面がある。
最初に『世界』に発表した「これは戦争ではない」は、九月一一日事件の衝撃のなかでブッシュ政権の対応と、それに対する世界の主要国の協調、さらにはメディアの主要な論調に危惧を感じ、「報復戦争」に向けた「満場一致」の風潮に異論を唱えるために書いた。アフガニスタン攻撃が始まるしばらく前で、「ベトナム化」などを心配した点では予想が甘かった。事件の直後だったため、それまで低空飛行と見えたブッシュ政権の性格がまだ充分に見えていなかったからだ。だが「ベトナムの教訓」は徹底的に生かされた。それも、超大国の軍事力をもってしても「義のない戦争」には勝てないという教訓ではなく、ゲリラ戦など展開する余地も残さないほど破壊し殲滅し尽くして、その惨状はいっさい世界に報道させないという教訓だ。
だが、「三ヶ月後の追記」に書いたように、アフガニスタンで何が起こったかを見れば、「テロとの戦争」を呼号するブッシュ政権が何をめざしているのかは、もはや覆うべくもなく明らかになった。それ以後、三月末に書いた「恐怖との戦争」を含めて、主要な内容にもはや何ら訂正を要する点はない。
* * *
世界を二大陣営に分けて対立させていた冷戦が終わって「大きな戦争」の構図は崩れ、グローバル化する世界に飛散する小さな紛争(LIC)への対応だけが、「国際社会」の軍事的課題になると思われていた。だが、超大国はみずからが超大国である世界の体制を維持し、その権力を現実的に発揮するために、新たな「大きな戦争」の構図を作らずにはいられないかのようだ。その「大きな戦争」とは、世界の主要国を組み込んだ、一元的な秩序のもとでの軍事警察的な恒常的抑圧と管理の体制の別名である。並ぶもののない軍事大国となったアメリカは、もはやアメリカと事を構えようとする大国はないのに、国家でさえない集団に(あるいはそうだからこそ)かつてない「憎悪」をむきだしにして、居丈高な暴君のように身構えている。
アメリカの内にはすでに世界があるという。世界の多様性とその多様性を保証する自由な社会があるという。けれどもその社会は、星条旗の下にまとまるとき、みずからを実際の世界と錯覚し、それとは違う世界があることを誤認し、すべてがアメリカと同じようであることを当然のように求める。あるいは善意から、世界中がアメリカのようなることを、そして「幸福」になることを願う。けれども「われわれは皆アメリカ人」と言うことを望まない人びとは、エイリアンのように恐れられ憎悪される。ハリウッド映画があらゆるヴァージョンで飽きず変奏するそのメカニズムを、露骨に利用する者たちがいまアメリカの権力を手にしている。彼らはもっとも悪辣なシナリオを、世界を舞台に演じようとしている。映画の中ではなく現実に、世界は「ならず者」たちの手に落ちた、そう言っても過言ではない状況にわれわれは立ち会っている。
2002年8月31日