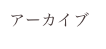内的秩序と戦争







半世紀にわたった「冷戦」の終結は、世界を二分した壁を崩してひとつの空間に流し込むと同時に、そこにアメリカを唯一の超大国として残すことになった。 それが二一世紀初頭の世界を規定するもっとも基本的な与件だったが、この一年間、われわれはその与件から生じる最悪のシナリオを見せつけられることになった。
「大きな戦争」から解放された世界は、さまざまなLIC(低強度紛争)を不安定要因として抱えながらも、 一元化した市場をエレメントとして経済活動を主軸に編成されるものと想定され、経済的なグローバル化が主要な課題として語られてきた。 どこでも問題は市場開放であり経済の拡張であり、そのためにIMF、世銀、そしてWTOが主役となった。 ところがそこへ、当のグローバル経済を象徴するWTCへの劇的な「テロ」攻撃が起こったのである。 もちろん襲撃されたのはWTCだけでなく、軍事の中枢ペンタゴンも襲われた。 つまりこの秩序の盟主たるアメリカが標的になったのだが、そのときからアメリカ国家とグローバル秩序の「安全保障」が至上命令となり、軍事的要素が一挙に世界運営の前面に押し出されることになった。 「テロとの戦争」である。 ここで、冷戦の終りは必ずしも「大きな戦争」の終りを意味せず、主要国間での戦争が想定しにくい時代においても、別の「大きな戦争」の枠組みが可能であることが示された。
この「戦争」の特徴をひとことで言えば、「外部のない戦争」ということである。 湾岸戦争以来、軍事行動はしばしば警察行動になぞらえられる。それは世界がひとつの「内的秩序」とみなされているということである。 この「戦争」もまた、国家やその集団同士の対立ではなく、内的秩序を体現する側と、その「内部化」を承認しない者との、国家横断的な対立を設定する。 つまり秩序を支える側やその受益者たちと、そこから排除された「闇の部分」から生じる反発との対立だ。世界規模の「内戦」と言うべきだろうか。 しかしそう言うにはあまりに「非対称的」である。それに後者は、この秩序全体の覇権を求めているわけではない。
アメリカ政府の宣言したこの「戦争」は、法や国家や主権についての根本的な問いを巻き添えにしている。 世界が「諸国家の社会」だとするなら、その安全保障体制として現在では国連がある。 そしてグローバル規模の安全保障には軍事だけではないさまざまなオプションがある。 けれどもブッシュ政権は、そのすべてを押しのけて軍事を優先させ、のっけからグローバル規模の「戦争」を宣言し、そのことで「諸国家の社会」をも押しのけた。 というより、アメリカ国家は事実上、みずからがそこには内属しないことを表明したのである。
ここには外部のない「内的秩序」が、いかにして内的に、言いかえれば「超越」なしに維持されるかという、いわゆる「世俗世界」における法と権力の基本問題が横たわっている。 それは「戦争の世紀」の前半に、法や国家のあり方をめぐってハンス・ケルゼンとカール・シュミットを対立させた要諦でもある。 単純化して言えば、ケルゼンは法システムの内在的自律性に社会の、ひいては「諸国家の社会」の存立の可能性を賭けたが(あくまで「賭けた」ということだろう)、シュミットは法の根拠の外在性をさらけ出す。 彼が「政治神学」を語るのは、あらゆる世俗的理論が目をつぶる制度の根拠(=理性)の原理的外在性を、言いかえればその「没理性」を強調するためだった。
周知のようにケルゼンは国際連合の理論家である。だが「九・一一」以後、アメリカ政府の行動によって世界は一挙にシュミット的様相を呈してきた。 「われわれの側につくか、テロリストにつくか」とアメリカ大統領がつきつけた二者択一は、「友と敵」とを峻別するシュミット的「政治」のエレメントを国際社会に露呈させ、差異という「間」にこそ存するというアレント的「政治」の可能性をにべもなく締め出してしまった。 またブッシュは、「これは戦争だ」として「非常事態」を宣言し、それが当然世界大に適用されるものであるかのように、もはや通常の国際法に拘束されない行動に出た。 要するにアメリカ大統領は、一元的世界という内的な秩序のなかで「例外状態」を宣言し、この秩序における「主権者」のように振舞ったのである。 そして、ほとんどの国の政府はこれに同調し追従することで、その「主権」に実効性を与えることになった。
また、このとき「敵」と名指された存在は、剥き出しの「主権」の全能の前に、もはやいかなる法的保護もない「無法」状態に裸で投げ出されることになっ た。 それがアフガニスタンでの一方的空爆やグアンタナモ収容所の意味することであり、こうしてまったき無権利の「罰されることなく殺しうる者」という新しい人 間の範疇さえ生み出された(「例外状態」で主権の前に裸でさらされるこのような存在を、G・アガンベンが「ホモ・サケル」としてテーマ化している)。 それはヨーロッパの法制度がこの二百年にわたって紡いできた「人権」という概念を根底から危ぶめるものだろう。
そして「戦争」はいまや国家間の争いではなくなった。 その目的ももはやクラウゼヴィッツの言うような、相手の国家にみずからの意志を押し付けることにあるのではない。 それは個人やその組織、あるいは一国の政権を握る人物を標的とする。 そして秩序になびかない政権を文字どおり抹消し、そのために攻撃される国の国民を頼まれもしないのに「解放」することを目標に掲げている。
この「新しい戦争」は伝統的な「正戦」の概念を援用しながら、それを臨界点にまでもってゆく。 従来の戦争は「やむをえずする」がゆえに「正しい」とされたのだが、「新しい戦争」はあらかじめ「正しい」がゆえに「是が非でもすべき」ものとされる。 その「正しさ」を保証するのは掲げられた敵の「邪悪さ」であり、「テロリスト」と呼ばれるこの「敵」は法外で無規定で捉えがたく、それゆえにまさに「秩序」の不倶戴天の「敵」なのである。 であればこそこの「戦争」は、「秩序」の実効化の名のもとにそれ自体が「法外」の暴力として、あからさまに「敵」の無制約な殲滅を目ざすことになる。
「テロとの戦争」はこの意味で「戦争の臨界」を画している。 ブッシュ大統領は当初から「この戦争は長く続く」と強調している。 日々の生活を変わらず続けることが「戦争の遂行」なのだと言われさえする。 つまり「例外状態」としての「戦争」がそのまま「規範状態」となり、「非常事態」がひとつの「恒常的体制」として敷設される。 かつて核兵器によってひとつの戦争が終ったとき、サルトルはもはや戦争と平和が区別しうる時代は終ったと語ったが(「戦争の終り」)、そのとき想定された「恒常的戦争」はまだそれでも天空に止まっていた。 いまやそれが地上に降り立ち、「戦争は平和、平和は戦争」(アルンダティ・ロイ)という意味の溶解状態が、すなわち狂気が、規範性そのものとなる時代が開かれようとしているのだ。
これが冷戦後の与件から生じた最悪のヴァージョンである。そのあおりはもちろん日本にも及んでいる。 「テロとの戦争」への協力は憲法体制を足元から崩す「超法規的」貢献の機会を与えているし、「安全」の配慮の名のもとに社会管理・統制の方途が立法化されようとしている。 「九・一一」後のアメリカ社会の反応も日本をみごとに感染させ、「犠牲」を敵意や憎悪の正当化のバネにする風潮が社会に蔓延している。 「敵」を作り、守るべきものを立て、「関係」の可能性を抹消すること、それが今「ふつう」のこととしてまかり通っており、これもまたアメリカにならって、思慮も原則も棄ててしまったメディアによって煽られている。
最悪のヴァージョンがこのまま支えきれるとは思われない。 けれども現在の事態は、遅れてきた世界戦争の「戦後」になされた、戦争の罪科、国家の責任、等々をめぐるあらゆる作業や、そこに貫かれていた「戦争の世紀」の教訓を、一挙に反故にするかのような勢いである。 戦争の反省にも表裏がある。アメリカがベトナム戦争の教訓を汲むというとき、ひとつは「義」のない戦争には勝てないということだが、もうひとつはなぜ失敗したのかという方法的反省だった。 アメリカはその「反省」から、まずIT技術による軍事革命で犠牲者を出さずにゲリラ戦に対処しうる兵器を完備し、その上メディア管理を徹底して「ユニラテラル」な戦争を作り上げるのに成功した。 その「成功」が、いま「戦争」を世界管理の通常手段と化そうとしている。
このような事態の前に、問われ、試されているのは、近代を継承するあらゆる政治思想であり、法思想であり、臨界点にある「戦争」がるつぼに投げ込んでいるあらゆる概念装置である。 われわれはどんな言葉をもって、何を、正確に、かつ有効に語りうるのか。