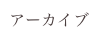これは戦争ではない − 世界新秩序とその果実
『世界』2001年11月号
これは戦争ではない − 世界新秩序とその果実
『世界』2001年11月号







打ち砕かれた「全能のアメリカ」
これほどあからさまなことはない。その日マンハッタンを襲った出来事は、現場に召喚された全米のメディアによって全世界に同時中継された。そのときカメラは、何を映すのかを知っていたわけではない。世界貿易センタービルに旅客機が突っ込むという事件の現場に駆けつけて、事態を理解する前に、二機目の旅客機が双子のタワーのもうひとつに激突し、やがて二つの巨大な建物がもののみごとに崩落するという未曾有の出来事を、ある既視感とともに茫然自失のうちに放映し続けることになったのだ。
湾岸戦争は「リアルタイムの戦争」と言われた。爆撃機の操縦席にビデオカメラがセットされ、発射されたミサイルが標的に命中して地上に噴煙があがる様子が、レーダー画像として逐一世界の「茶の間」に提供された。そのイメージは、「正義の軍隊が国際社会の無法者を懲罰」するという、この戦争の「大義」をみごとに演出し、全世界の視聴者にそれを追体験させるものだった。そのときカメラはもちろん自分が何を写すのかを知っていた。
だが今度はまるで違った。ある意味ではメディアも巧まずして乗っ取られたのだ。自分の「勲」を見せつけることが「テロ」の重要なねらいのひとつだとすれば、この「テロ」はマンハッタンを襲っただけでなく、余分に指ひとつ動かすことなくアメリカのメディアを完全に制したのである。そのとき、メディアがはからずも放映することになってしまったもの、それは湾岸戦争に動員されたカメラがけっして映し出さなかったもの、レーダー画像の向こう側でいつも噴煙に隠されていた、見えない「爆撃」現場の光景だったのだ。
起こったことは明白だ。誰もが見ただけでそれを理解した。アメリカのシンポルが撃たれたのだ。だが、そこにさらけ出された光景が、それまでアメリカが隠し続け、多くのアメリカ人が見ようとしなかったものだということには、当局はもちろん、メディアもまったく思い至ろうとはしなかった。
多くの人びとが、この日以来もはやアメリカは同じ国ではなくなったと感じているという。アメリカ社会は「禍々しい悪夢」(タイムズ誌)を目の当たりにし、深いトラウマを負った。人的・物的な被害が甚大だったというだけではなく、この事件は何より超大国アメリカの「安泰」の神話を打ち砕いたのだ。アメリカは圧倒的な経済力と技術力と軍事力をもち、市場経済を領導し、つねにテクノロジーの先端を切り開き、核ミサイル網と軍事衛星で地球を覆いながら世界を睥睨している。そのアメリカの心臓部で、日々の足である国内便を乗っ取ってそれをにわかミサイルに変えて摩天楼に突っ込むという、予想もされなかった事件が起こったのである。多くの人びとが一瞬目を疑ったと言うように、アメリカが「攻撃される」というのは映画のシーン以外にありえなかった。
人びとを襲った衝撃はその点にある。湾岸戦争の「空爆」イメージが決定づけたように、アメリカはつねに敵の射程の外にあり、安全な空から最新テクノロジーで敵を破壊する。レーザー光線で病巣を除去する外科手術のように、あるいは「悪魔」を退治する「天使の軍団」のように。それがアメリカにある種の「全能」幻想を植え付けてきた。だが、そのアメリカが攻撃されるということが、突然現実になった。ただ「安全が失われた」ということではない。そうではなく、この「全能」幻想が打ち砕かれたのである。強大な軍事力と技術力と経済力をもってしても、それだけでは「自由と繁栄」が守れなかったということ、そして他でもないアメリカが「テロ」の標的になるということ、そのことの意味を、膨大な瓦礫を片付ける作業の中で、そして長く尾を引く喪の作業の中で、アメリカの人々は考えざるをえないだろう。
「戦争」のレトリックと無法な「正義」
そこに当然浮かびあがる「なぜ?」という問いを押し潰すようにして、大統領ブッシュは「これは戦争だ」と一声をあげ、それが「自由」に対する、「民主主義」に対する「卑劣な攻撃」だとして、徹底的な「報復」を宣言した。「力」でねじ伏せること、ねじ伏せて「強さ」を示すこと、それだけがアメリカ国家の存在証明だと言うかのように。グローバル化した世界が可能にした今回の事件で、ニューヨークの人びとが「変わり」つつあるとしても、アメリカ国家のやり方はまったく変わらないのだ(違った意味で、世界に背を向けつつあったブッシュ政権は、しかしこの事件で父親の政権の敷いた「世界新秩序」の路線に立ち戻ることになった)。
それ以来「戦争」のレトリックが溢れかえっている。そして唖然とさせるのは、驚くべき「満場一致」が西欧諸国とその周辺に広がっているということだ(もちろん個々のスタンスの差はあるが、アメリカの「報復戦争」を支持し、積極的に協力するという点では一致した姿勢を示している)。そこには守るべき共通の利害があるようだが、それは各国の当局者やそれに追従するメディアが言うように「自由」や「民主主義」などではなく、アメリカを盟主とする冷戦後の「世界新秩序」と言われるものだろう。湾岸戦争によって作られたこの構造は、「文明の秩序」とそれに対する「無法者」とを恒常的に対置させる。「テロのない世界を作る」、それを望まぬ者はいないだろう。だが「文明の衝突」を演出するこの秩序そのものが、実は「テロ」を構造的に生み出しており、その強化はますます「テロ」の激化を生むだけだということを、今度の事件が示したのではないだろうか。ブッシュ・ジュニアとコリン・パウエル、役者が揃っているからそう見えるのだけではなく、今度の事件は明らかに湾岸戦争以来のアメリカの政策の帰結なのである。
にもかかわらず、世界中のテレビの解説者たちはブッシュの言葉に相槌をうち、「二一世紀型の戦争」とやらを解説し始める。だが間違えないようにしよう。たとえ甚大な被害があったとしても、起こったのはいわゆる「テロ」事件であり、「テロ」は犯罪であっても、「国民」を動員して国家が行う「戦争」ではない。そして「戦争」とは、今アメリカ政府が準備し、世界を引き込もうとしているもののことだ。
メディアの解説者たちはしたり顔で言う。「二一世紀の戦争は非対称的なものだ。国家が無形のテロ集団と戦う。その戦いは正規戦ではない。まず情報戦、そして大規模な空爆と特殊部隊による地上戦が必要だろう。」だがこれはアメリカ国防省の言うこととまったく変わりはない。そして「テロリスト」を殲滅するために、それを保護するとされる国に対して、地表のかたちが変わってしまうな爆撃を加えることを当然のように語るのだ。とはいえ、アメリカ軍が「人的被害」を最小限に抑えようとする方法については薀蓄を傾けても、彼らはその空爆下で起こる出来事の帰結については一顧だにしない。湾岸戦争のとき「連合軍」によって大量に使われた劣化ウラン弾が、その後のイラクでいまなおどれだけの子供を苦しめ、殺し続けているかについては一言も語らない。それに、湾岸戦争ではイラクのいくつかの原発が爆撃されたといわれるが、それがどういう結果になったかについてはいっさい関心を示さない。あたかも彼らの頭には、最新装備による攻撃破壊だけしか、つまりアメリカ軍の許可するイメージだけしかないかのようである。一人の個人とその組織を攻撃するという目的のために、実際には数百万の人びとがまた難民となり、その地域の生活が完全に破壊され、人びとを絶望的な無力に陥れることになる。だとしたら、それがまた不退転の「テロリスト」を生み出す温床になることは目に見えているが、そんな愚かなことが「文明の秩序」を守るための当然の「報復」として、得々と語られているのだ。
アメリカはいま、「世界新秩序」の中でほとんど唯一の「主権国家」として振舞っている。「主権者」とはカール・シュミットの有名な定義によれば、「例外状態について決定できる者」のことだ。つまり、法秩序が停止された状態で決定権をもつと同時に、何が「例外」かをも決定できる者ということだ。アメリカは実際に「これは戦争だ」と決定して「非常事態」を宣言し、世界にこの認識を共有させようとする。「戦争」は「殺人の禁止」を解除する。平時の国際関係のルールも無効になる。「敵国」を攻撃するのは当然だからだ。その「敵」を名指すのもアメリカである(「信ずるに足る証拠がある」と中身も示さず言うだけで、世界の主要国はそれを承認する)。そしてそうと名指された国は問答無用で攻撃されることになる。
これが初めてではない。すでにアメリカは何度もこうして「テロ」に「戦争」で応答してきた。だが「犯罪」に対する「報復」に「戦争」を宣言するというこの「無法」を、現在の世界のなかで公言できるのはアメリカだけである。アメリカはこの「例外的特権」を自己のものとして主張している。世界の秩序に「例外状態」を宣言し、「暴力の発動」を正当化する。「無法」と「正義」との完全な一致がこうして生まれる。あとは「正義の戦争」のキャンペーンがあるだけだ。もちろん現実的には、アメリカも諸外国の協力を要請する必要がある。だがその「要請」も、バキスタンの場合を見れば明らかなように、経済力と軍事力をバックにしたほとんど脅迫まがいのものである。アメリカが世界の「法」に関してすべてを決定するという湾岸戦争以来のこの構造、それこそが実は攻撃を誘った当のものだったのではないか。
「自爆テロ」はどこから来るか
これも湾岸戦争以来、アメリカは「敵」を人格化し、「顔」を与えてそれを「悪魔」化する。「テロリスト」という言葉も、事態を単純化するのに役に立つ。「悪」と「善」との色分けをして「恐怖と憎悪」を組織する。だがこのことは、「なぜテロが」というもっとも重要な問いを忘れさせるのだ。とりわけ「自爆テロ」には、「狂気」のせいと決めつけるだけではすまされない構造的な理由がある。「自爆テロ」は自分が死ぬことを前提にしてする行為だ。少数の「狂信者」たちがいるのではなく、彼らの「信念」を支える広範な人々の怒りや絶望が見えないかたちで広がっている。その背景にある怒りや憎悪に何らかの対処をしないかぎり、「テロ」をなくすことはできないだろう。
誰もが思い浮かべるのはイスラエルとパレスチナの抗争である。「自爆テロ」が頻発する舞台もここだ。とはいえイスラエルには、和平に踏み出す首相(ラビン)を殺害するテロリストは現れても、「自爆テロ」に走る者はいない。「自爆テロ」はパレスチナ人のいわば専売特許だ。欧米諸国はそれを「イスラームの野蛮さ」に解消しようとする。だがパレスチナ人が「自爆テロ」に走るのは、いっさいを奪われもはや失うもののないからこそであり、もともとは宗教や「文明」の違いなどには関係がない。
「パレスチナ問題」として語られるこの紛争は、実は「イスラエル問題」と呼ぶべきである。というのも、ことの発端は、ヨーロッパ諸国の後押しでシオニスト・ユダヤ人がこの地に強引にイスラエル国家を作ったことにあるからだ。それまで「パレスチナ人」という民族はいなかった。イスラエル建国によって住んでいた土地を奪われ追放された人々が、住むところのない「難民」として締め出されることになり、それが「パレスチナ人」と呼ばれるようになったのだ。
パレスチナ人には国家はない。だから彼らの権利主張を合法化する権力はなく、生存権も含めてその権利は保護されない。当然、パレスチナ人はイスラエルと敵対するが、それは国家に対する民衆の戦い、つまり始めからの「非対称的」でかつ「非合法」なゲリラ戦になる。あえてその類型を探せば「植民地独立闘争」ということだろう。この抗争に関して、国連は何度もイスラエルの一方的な行動に非難決議を出してきたが、そのたびにアメリカの拒否権によって反故にされてきた。そしてパレスチナ人の権利要求は放置され、反抗の表明は「テロ」と呼ばれ、国際社会に黙殺されたあげく、湾岸戦争後に尾羽打ち枯らして受け入れたのが「オスロ合意」だ。
ところがイスラエルはその「合意」にもとづく「和平プロセス」さえなし崩しにしようとする。それに対する反発には、圧倒的な軍事力と警察で対応する。その果てにニ度目の「インティファーダー」が起こる。イスラエル軍は発砲する。再び「テロ」が起こる。だがイスラエルに一人の死者が出れば、一〇人の殺害で応酬される。そしてついにイスラエルはパレスチナの要人暗殺(つまりテロだ)まで公然とやりだしたのである。パレスチナ人が生存権を主張するかぎりイスラエルはそれを「脅威」とみなす。だとしたら、パレスチナ人の「最終的消滅」なしにイスラエルの「安全」はないということになる。このような境遇をパレスチナ人はすでに半世紀も生きてきたのである。
日々抑圧と軍事的脅迫のもとに生き、自分たちの生存の権利まで踏みつけにされ、それに対する抗議が「テロ」と呼ばれてまた圧殺される。そんな境遇におかれ、国際社会に「正義」の保証を期待することもできず、不当さに対する憤りのなかで窒息し、人は未来に何を夢見ることができるというのだろう。多くの子供たちが「自爆テロ」を志願すると言っている。それをイスラエルは、パレスチナ人の学校では「テロリスト」を育てていると非難する。だが、自分の存在と尊厳を表明する途としてもはや「自爆テロ」しかないような生存状況に、彼らを追いやっているのはイスラエル国家なのである。
「世界新秩序」の隠れたエンブレム
ニューヨークを襲った「テロ」に対して、今アメリカがやろうとしていることは、あまりにもこれ(とりわけシャロン首相下のイスラエル)と似ている。国家が見えない「テロ」と戦うという「二一世紀型の戦争」と言われるものは、少しも新しくはない。それは結局、アメリカの「イスラエル化」ということであり、それが世界の基本的な状況になるということだ。湾岸戦争以降おぼつかない足取りでいた「世界新秩序」は、今そのような姿をあらわれにしようとしている。
「イスラエル問題」とは、長らくキリスト教ヨーロッパで「ユダヤ人問題」として語られてきたものの帰結である。もともと「ユダヤ人迫害」はキリスト教社会の宿痾だった。その事情は近代になっても変わらず、ナチズムは「アウシュヴィッツ」でその「最終的解決」を試みて失敗した。たがナチズムと戦った欧米「連合国」は、ユダヤ人を中東に送り出しそこに国家を作らせることで、この「問題」の最終的な「輸出」に成功したのである。そのとき以来、欧米から「ユダヤ人問題」は表向きとはいえ消滅し、代わりにイスラエル対パレスチナ、ユダヤ対イスラームという対立が中東に作り出された。
すでに半世紀にわたる抗争で、アメリカは一貫してイスラエルの後ろ盾になってきた。それは欧米社会の「健康(秩序)」にとってイスラエルの存在が必須だからである。冷戦時代はこの対立も米ソの対立構図のなかに埋め込まれていたが、湾岸戦争によってそれは「世界新秩序」の要石として炙り出されてきた。「世界新秩序」とは、この五世紀の西欧による世界の一元化、世界戦争によって完了した世界の一元化を、西欧世界のヘゲモニーにおいて永続化しようとする支配秩序である。イスラエルはその秩序にとって、「西欧の宿痾」を忘れさせる隠れた要になっている。
中東地域はなぜ「ポストモダン」が語られるこの時代に再びイスラーム化したのだろうか。それも文化のレベルにおいてではなく、政治的にイスラーム化したのか。それはまさしくアフガニスタンのケースに見られるように、冷戦時代は米ソの意図によって蹂躙され、生活空間のいっさいを破壊されて、人びとがもはや拠るべきものとしてイスラームしかなくなったところへ、そのイスラーム勢力の政治化・軍事化をアメリカが戦略的に支援したからである。アメリカの協力者であったサダム・フセインが、イスラーム化の戦略をとるようになったのも湾岸戦争の時期からであり、今回の事件の「首謀者」と名指されているウサマ・ベンラディンが過激化していったのも、湾岸戦争をきっかけにしてだと言われる。こうしてアメリカは、自身の戦略によって中東地域を政治的にイスラーム化しながら、「異物」となった世界を何としてでも抑えつけようとしている。
悲劇をなくすというなら、このような状況が「世界秩序」のなかに放置されていてはならないだろう。ニューヨークの悲劇は他所で起こっている悲劇の写しなのである。それに対してアメリカは、またしても「報復戦争」を唱え、「戦争」に打って出ようとしている。
ところがアメリカの「敵」として名指されたのは、この二〇年間世界の超大国によって翻弄され、蹂躙され、疲弊し尽くして、廃墟のなかでやっとわずかな安定状態にいたったばかりの、世界でもっとも悲惨な国のひとつアフガニスタンなのである。「大仏破壊」で悪名高いタリバンの制圧というその不安定な「安定」の内には、この国を翻弄した世界の秩序に対する絶望的な憎悪が、あるいは正視し難いような無力感が(アウシュヴィッツの囚人のような)沈殿しているだろう。飢餓線上の難民が四百万というこの国の惨状に、すでにアメリカは十分な責任があるのだ。そのアフガニスタンに、最強の軍備をもって「戦争」をしかけ、救いがたく荒廃したこの地に再び容赦のない爆撃を行おうという。
そしてそれを臆面もなく「無限の正義」作戦と名付けて遂行しようとする「断固たる意志」を、先進諸国の政府がこぞって支持するというこの驚くべき状況! まさしく未曾有の「野蛮」が「文明」と言い募ってまかり通るというこの世界を挙げての倒錯に、誰も異を唱えないというのが「二一世紀」の光景なのである。
ベルリンの壁崩壊を終わらぬ夜で祝っても、ヨーロッパではだれ一人としてソ連のアフガン撤兵を祝ったり、そこで犠牲になった数百万の人びとのためにロウソクを灯したりはしなかった。アフガニスタンの人びとのような存在は、ただの「非文明的」な人の群れとして、世界の「民主主義」の議論の場にはじめから席を与えられず、「テロ」から身を守るべき「民主主義世界」の眼中には入らないのだ。
そしていま「世界秩序」を自称する「文明世界」は、まさにその「秩序」が日々生み出している憎悪の噴出を「戦争」と受けとめ、その「報復」と称して「文明なき世界」へ「戦争」をしかけようとしている。そして西欧先進国(とそこに何としてでも加わりたい日本をはじめとする追従国)がアメリカへの追従を競い合っている。つまり、これが「湾岸戦争」以来試されてきた「世界新秩序」の実相であり、それはこの秩序が負のかたちで炙り出す「非文明勢力」を徹底的に抹殺することを目指して結束する、恒常的戦争体制の秩序である。その意味でも、みずからの暴力が生み出した「難民」に「戦争」を仕掛けて抹消しようとするイスラエル国家は、この「新秩序」の隠れたエンブレムなのである。そしていまこの秩序は、もうひとつの「人間のいない場所」(人間が人間として生きられず、なおかつ死ぬまで生きさせられる場所)をアジアの見えない地域に作り出そうとしている。
虚構の「正義」と「義」のない戦争
街では、ハリウッドの映画やある種の音楽が「不謹慎」だとみなされて、公的な場から消えている。配給しかけたいくつかの映画の上映も中止されたという。マンハッタンの巨大ビルが襲撃されるという光景は、あたかもそれがアメリカ人の願望ででもあったかのように、「エイリアン」や「悪の帝国」による「卑劣な侵略」のさまざまなヴァージョンとして、繰り返し映画になってきた。それが今ではあまりに生々しい「現実」となってしまい、その「現実」のトラウマが、この手の映画を観るに耐えないものにしてしまった。もうたくさん、観たくないというのだ。
だがハリウッド的ファンタズムが現実になり、もはや映画を作れないからといって、そのシナリオをアメリカ政府が現実に演じる必要はさらにないだろう。その資質が陰に陽に疑われるブッシュ・ジュニアが、まともなシナリオ・ライターも付けずに「善の帝国のリーダー」を演じようとするとき、その児戯にも劣る単純なレトリックと演技とは、映画を終わりに導く前に、アメリカもろとも世界をどうしようもない混乱に陥れてしまうことを危惧させる態のものである。『インディペンデンス・デイ』のタイトルが示すように、この手の映画ではつねにアメリカが世界の中心であり、世界はアメリカの延長でしかない。そのアメリカ中心主義がこの手のファンタズムを自己満足的に生み出してきた。だが、いま必要なのは、作れなくなった映画の続きを、世界を巻き添えにしながら現実の場で演じることではなく−−それこそ場違いというものだ−−、アメリカだけで自足する「映画」の外に出ることなのだ。
いまは未曾有の惨事の衝撃に打たれているアメリカの人々も、ブッシュ政権の演じているのが、もはや観たくない映画の、それも粗野で質の悪い続きだということに、遅かれ早かれ気づくことになるだろう。
アメリカだけでなく、ヨーロッパはじめ世界の各地で「ニューヨークの犠牲者」のための追悼の催しが行われた。はやくも死者たちは「アメリカのため」の犠牲者にされようとしている。「のため」という表現は二重の意味がある。「何かのせいで」という意味と、「に身を捧げて」という意味だ。かれらが「アメリカのために」犠牲になったとしても、それはかれらの死が「アメリカ」を目的としていたのではなく、「アメリカ」が原因だったということをすりかえてはならない。犠牲は「なぜ」という問いに正当な応答が示されるときにはじめて担いうるものになる。「なぜ」という問いに対する答え、それが「理由(リーズン)」であり、「理性(リーズン)」といわれるものであり、そこに立脚してこそ世界を納得させる対応は生まれるのだ。
ブッシュ政権は、いま準備している戦争を語るのに湾岸戦争を参照する。しかし実際に兵士としてパキスタンやアフガニスタンに送られることになる若者たちが参照すべきなのは、湾岸戦争のイメージが国家的に覆い隠したベトナム戦争の記憶である。ゲリラに襲われる恐怖が兵士を盲目的に獰猛にし、「ソンミ村」の悲劇をまたいくつも生み出すことになる。
そのベトナム戦争も、アフガンに較べればピクニックのようなものだ、そう警告を発しているのは、六十五万のアフガン帰還兵を抱えるロシアの将軍たちである。それはアフガンの地形が険しくて近代装備で戦いにくいからというだけでも、タリバンを始めとするイスラーム過激派が「悪魔」のように残虐だからでもない。ベラルーシの女性作家スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチが『アフガン帰還兵の証言』で伝えているように、泥沼の戦争がロシアの若者たちをまったくの「非人間」に変えてしまったのだ。それは結局この「戦争」に「義」がないからである。「義」のない「戦争」のなかで、あらゆる暴力が猖獗し、敵も味方も、あらゆる意味で「人間」の価値は破壊されるのだ。