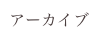記憶を分有する ー クリス・マルケルの『レベル・ファイヴ』について
(『EDGE』第12号)
記憶を分有する ー クリス・マルケルの『レベル・ファイヴ』について
(『EDGE』第12号)







戦後五〇年の節目の年に日本で「戦争の記憶」があらためて問われ始めたころ、フランスで「オキナワ戦」を題材にした一本のビデオ映画が作られていた。クリス・マルケルの『レベル・ファイヴ』である。マルケルは、世界中をまわり、ドキュメンタリーを基調にした他に似たもののない映画を撮ることで知られた特異な作家で、『シベリアからの手紙』、『ラ・ジュテ』などで知られ、ゴダールやアラン・レネの参加した『ベトナムから遠く離れて』をまとめたほか、日本にも以前から関わりが深く、黒沢明へのオマージュ『A・K』や『サン・ソレイユ』などを撮っている。
その彼がなぜ「オキナワ戦」なのか。
オキナワの名は彼がパリで迎えた終戦の頃から、その惨状のニュースとともに脳裏に刻みつけられたという。その後日本を訪れるようになったとき、ある人からぜひ行ってみるよう勧められたのも沖縄だった。「オキナワ戦」は第二次大戦中もっとも悲惨な戦闘で、一万の米兵と十万の日本兵が死んだが、何より住民の約三分の一にあたる一五万の民間人が犠牲になっている。そのなかには村ぐるみの集団自決といった類例のない惨劇の死者も含まれている。オキナワは戦後の日本のあり方だけでなく、アメリカの戦略を通して世界の状況にも大きな影響を与えたのだが、同時にまた顧みられることの少ない戦場でもある。その忘れられた戦争を「オキナワから遠く離れて」問い直そうとしたのがこの映画だ。
コンピューターを前にして、ひとりの女が見えない誰か(カメラのこちら側)に語りかける。彼女は「オキナワ戦」のコンピューター・ゲームに向かっている。このゲームの特徴は、他の歴史ゲームと違い、要素を組み替えて仮想の現実を作り出すのではなく、ジグゾー・パズルのコマを組み合わせるようにして、実際に起った事がらを再構成しようとするものだ。
さまざまな資料(作戦資料、大島渚、時津ケンジらの談話)や情報の断片が、コンピューターから呼び出され、インターネットに似たネット世界から集められる。この女性ローラは「あなた」の思い出を語る。「あなた」はコンピューターゲームの作者だが、今はもういない。残されたゲームと毎朝向き合うことで、ローラは「あなた」との不可能な対話を続ける。場面はこれしかない。
「オキナワ」の名は一九世紀初めの大作家シャトーブリアンの回想記に初めて現れた。ナポレオンに謁見したイギリスの航海家が、武器を持たず、戦争をせず、人を歓待する島の人々の優しさについて報告したのだ。ところが暴力を厭うその島が、もっとも凄惨な殺戮の修羅場となった。ローラはこの島が自分のようだという。なぜなら私の苦しみは二つとないもので、もっとも内的で、しかももっともありふれた、歌謡曲のように名づけやすいものだから、と。そして「オキナワ、わたしの恋人」と口にする。
集団自決。ローラはサイパンの絶壁から飛び降りる女性の映像を見る。この女性は飛び降りる前に一瞬あとを振り返る。まるでカメラを見るようにして。そのカメラに飛び降りる勇気を示すため、彼女は宙に身を躍らせたのだとローラは考える。逃げ場のない彼女を、カメラは獲物をねらう狙撃手のように撃ったのだと。
ローラは日毎ログインを繰り返す。それは死を介した「見えないあなた」とのランデヴゥーであり、「あなたの不在」を通してそこに「オキナワ」が再構成されてゆく。
コンピューターに向かう女性のシーンにオキナワの光景が交差し、そこにクリス・マルケルのナレーションがかぶさる。水没した子供たちへの集団供養、ひめゆりの塔の観光客。あるいは米軍の撮ったフィルムの断片がある。体を焼かれて走りながら、倒れてまた起きあがる人影。生きて捕囚の辱めを受けず、と教えられ、多くの人々が住民が日本人であることのために集団自決に追いやられたが、その生き残りの少女に白旗をもたせ、それを楯に投降する日本兵の姿。ただ、戦場は一方に犠牲者がいるだけではない。記憶を失った米兵に催眠術をかけて回復させようとする軍医。戦争の恐怖を示唆し、戦意を喪失させるというので、アメリカでも三五年間公開を禁止されていたというジョン・ヒューストンのフィルムの一場面だ。
だが、なんといってもこの映画のやま場は、わが手で母親の命を絶ったという金城牧師の語る集団自決の光景である。なにゆえに。愛する者を屈辱の死にさらすまいとする気持ちから。愛ゆえに…。始めから勝つことを想定せず、本土を守り終戦を有利に導くための「捨石」とされた戦場で、沖縄の人々はそんな極限状況に追いこまれた。
クリス・マルケルは、沖縄の記憶に近づくためにひとつの切り詰めたフィクションを設定した。この映画のなかでオキナワは、死んだ恋人の残したコンピューター・ゲームを通して現れる。それは歴史の厳粛な真実をゲームの素材として扱い、かつ国家の恣意による犠牲者たちの記憶を、「愛する人を亡くした」という私的な心情と同一視することになるのだろうか。
ここには、歴史の真実や記憶とその分有をめぐるいくつもの問いが含まれている。
まず、記憶が生きている人によって担われる出来事の痕跡だとすれば(だからこそそれは、直接の体験者たちが消えてゆこうとするこの時期に問題になる)、それを生きなかった者が、記憶の共有を僭称することなく、いかにして他者の記憶に接近しそれを分有することができるのか。アラン・レネの『夜と霧』の製作に関わったマルケルは、ここではいわゆる「歴史の真実」をドキュメントによって再構成しようとするのでもなく、あるいはクロード・ランズマンの『ショアー』のように生存者の証言の彼方に「表象不可能なもの」として出来事を絶対化するのでもなく、死による不可能の感情(もはや語り合えない、コンピューターは「あなた」の痕跡でしかない)を介して、スクリーンに「記憶の真実」の蘇生を演出しているように思われる。事実このフィクションを通して、金城牧師の証言は洗い出されたような衝迫力をもって迫ってくるのだ。
それにまた、ハイデガーが「経験の喪失」をあばき出しで久しいが、イメージが溢れ、イメージの経験が現実の経験を凌駕するような時代に、われわれにはもはや現実の記憶とヴァーチャルな記憶との区別がつきにくくなっている。コンピューターのメモリーは、人間の記憶となんと違うことか。人間は覚えていてふと思い出す。そうでなければ忘れてしまう。思い出と忘却はオルタナティヴだが(精神分析の言うことを括弧に入れておけば)、コンピューターは「記憶」を情報の信号として貯蔵し蓄積し、使いまわすのを可能にする。けれどもそのようなイメージと情報化の時代に、「オキナワ」の記憶が時間と空間を超えて伝わるのも、分かち合われるのもまたしばしば情報のネットワークを通してである。
出来事から五十年の時間を経て、その現場からも遠く離れて、世界化が深化する一方で人間の意識の経験がコンピューターによる情報化でその質を大きく変えてゆく。そんな条件のなかでなおかつその出来事の、あえて言うなら「人間的な」意味を問いその記憶を更新する。この映画はその困難な試みだと言えよう。タイトルの「レベル・ファイヴ」とは、コンピューター・ゲームの難易度を示す言葉だが、ここでは、死によってしか到達できないレベルだとされている。
この映画について論じるべきことは多いが、二十世紀後半にもっとも同時代的な(あるいは近未来的な)映画を撮りつづけたフランスの映像作家が、「オキナワ戦」の記憶に取り組んだことの意味は、この作家のためにも、またそれぞれの意味合いで沖縄と日本のためにも銘記しておきたい。
(『EDGE』第12号、APO、2000年2月10日)