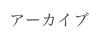沖縄と「魂の原郷」— 比嘉康雄『日本人の魂の原郷・沖縄久高島』のために







『神々の古層』シリーズ(ニライ社)で知られる写真家であり、どんな民俗学者よりも琉球の島々の祭祀に通じていた比嘉康雄が、この五月一三日に静かに世を去った。まだ六一歳だった。
フィリピンに生まれ、父を戦争で失って戦後沖縄に引き揚げ、高校卒業後警察官になった彼は、米軍基地をめぐる闘争で公私にわたる葛藤を経験し、職を辞して写真家になった。当時あふれていた報道写真とは違う沖縄を撮ろうとして彼が求めたのは、映し出される景観のこちら側に、どこにもない自分の居場所を見出すことだったのかもしれない。そんな彼の生涯のエビソードについては、沖縄のユニークな雑誌『EDGE』が奇しくもこの春の最新号(九−十号)に掲載した、編集人仲里効による会見記に詳しい。
比嘉ははじめ沖縄の写真を撮り、次に「日本」とはどんなところかを確かめるために「本土」縦断の旅をした。それから今度は「アメリカ」を見ようと渡米を考えている頃、宮古島狩股でウヤガンの祭りに出会い、神々と生きる生活の深さに震撼されて以後、島々を訪れては祭祀を担う神女たちの話に耳を傾け、祭りの写真を撮りつづけることになった。
そのなかでも比嘉がもっとも親しんだのが沖縄本島の東にある久高島だった。海と空の間に浮かぶこの島では、昔から「男は海人(ウミンチュ)、女は神人(カミンチュ)」を習いとしている。男たちは海に出て漁をし、女たちは祭祀で家族や島の守護を受けもつ。島の女たちは三十を越すと、一二年に一度あるイザイホーの祭を通してみな神女となるのだ。そして彼女たちが年間二十を越すさまざまな祭祀の担い手になる。
ここでは死者たちの魂は海のかなた東の空におもむくと考えられているが、女たちの魂は母神となってやがて島の聖所に帰り、島の人びとの生の営みを守護するのだ。その神々との不断の交流が、仏教もキリスト教も浸透せず、近代の合理主義からも隔たってきた島々の生活のかたちを作ってきた。
だが比嘉が写真を撮りはじめた頃は、女たちの祭祀をとおして神々とともに生きるという、数百年の時を越えて伝わるひとつの世界が、音もなく崩壊してゆく時代でもあった。うち寄せる近代化の波に洗われ、久高島でも一九七八年を最後にイザイホーもできなくなった。それぞれの役割を担う神女に後継者が足りなくなり、祭が成り立たなくなったのだ。祭の崩壊は、たんなる郷土芸能の消滅などではない。歴史を動かす進歩や統合の力学とは無縁なやり方で、長い時間を生きてきた一つの世界が消滅してゆくのだ。四半世紀にわたって久高島に足繁く通い、神女たちと心を通わせた比嘉は、はからずもその世界の臨終の立会人となった。
何百年も同じかたちで繰り返される生活には変化がない。進歩などない。だがそれは単なる停滞でもない。同じ生のかたちは反復される。だがそれを生きるのはそのつど違う人であり、違う人びとによってあらためて生きられる一回の生だ。進歩は歴史を尺度にして語られる。だが歴史化されない生は、同じもの反復のうちにそのつど初めてのものとして生きられる。そういう一回性のうちにこそ、歴史が消し去って顧みない生の単独性は見いだされる。
「久高島の祭祀世界を深く見てゆくなかで、私は、母性原理の神のもつ根本的な意味を考えさせられることになった(…)。この母性原理の文化は、父性原理の文化がとどまるところを知らず直進を続けて、破局の危うさを露呈している現代を考える大切な手がかりになるであろう。」
久高島の伝統の生きた守りだった西銘シズさんの死を見とり、一〇年後に自分もまたこの世を去る間際に、比嘉はそう語って遺言のようにして一冊の本を残した。そこには、神々とともに生きる島の宇宙のエッセンスが、一年を埋める日々の祭祀のディテールを通して、虚飾のない筆致で描かれている。まるで比嘉康雄その人であるかのような端正な文章だ。各章の扉を飾り、随所にさしはさまれた祭祀や風景の写真は、被写体への畏敬の念と深い共感に澄みわたり、無言のままにこの世界への扉を開け放ってくれるかのようだ。新書ながら、まさに「古典」(池澤夏樹)の風格がある。
ただ不可解なのは、このすばらしい本が『日本人の魂の原郷・沖縄久高島』という不似合いなタイトルをつけられていることだ。本文中で一度も「日本人」などに言及しなかった比嘉が、「日本人の…」などと考えていたのだろうか。
クリス・マルケルの『レベル5』という映画がある。このフランスの映画作家は、沖縄戦を第二次世界大戦中最後の最も凄惨な戦場、それも最も忘れられた戦場とみなし、ビデオ・ゲームを作る試みという設定で、沖縄戦を想起しようとした。その中にある記録フィルムの一場面−−村人たちが集団自決に追い込まれる一方で、生き延びた子供に白旗を掲げさせ、それを盾にしながら二人の日本兵が後をついてくる…。その日本兵こそが「日本人」なのだとしたら、なぜ沖縄に見出される「魂の原郷」を「日本人」のものだと言えるのだろう。
それに、今は総選挙でかすんでしまったが、この夏の「沖縄サミット」とは何なのか。まさに比嘉がその最後の証人になろうとした「神々のシマ」の宇宙を、明治以来の「皇民化政策」で踏みしだいてきた「神の国」による、押しつけがましい統合の儀式なのではないのか。
久高島の祭祀は、国民国家システムの暴力的制覇の歴史を潜ってつい最近まで生き延びてきた。それは大日本帝国にも、その末裔たる日本国にも帰属することのない世界であり、そこに生い安らうのは政治的帰属以前に生きる何人でもない人の魂だろう。あらゆる人間が国家システムから逃れられず、生まれたときから国籍を刻印され、不幸な場合には国家への統合を強いられるという、「生存の政治化」によって押し潰される現代の生だからこそ、フィリピン生まれのウチナンチュー比嘉康雄は、久高島に「魂の原郷」を見いだしたのではないのか。魂はどこにも帰属しないことによってはじめて「原郷」に立ちうる。その「魂の原郷」を「日本人」のものとしてしまうことには、「日本人」の度し難い無神経と自己欺瞞のさもしさが露呈している。
このすばらしい本がこのような題名を背負ってゆくことが何とも残念に思われるが、今は著者の東の空での冥福を祈りたい。(『新潮』124巻5号、新潮社)