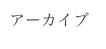『不死のワンダーランド』新版あとがき







二〇世紀の思想が出遭ったもっとも逆説的な発見は、「死の不可能性」ということだった。死を宗教とともに視界から追放して邁進してきた近代の思想が、産業化と国民化とその果ての世界戦争の時代に、非人称化した人間の動員と大量死のなかで初めて見出したのは、夥しい無名の死の周辺に浮かび上がる「死ぬことができない」という新たな生存の境位だった。アウシュヴィッツで、ヒロシマやナガサキで、そうしてテクノロジーが人間の生存環境を根底から変えてゆく「冷戦下」の日常のなかで、主体の失効とともにあらわになる「死の不可能性」は、主体の自立を前提にしたあらゆる思考の構えを根底から問い直させるものだった。
この本はベルリンの壁の崩壊前後に書かれた。つまり冷戦とともに近代の最大のプロジェクトであった共産主義が崩壊しようとし、日本では「昭和」の黄昏のなかで、「バブル経済」と「ポスト・モダン」を謳歌する風潮とが手を携えて輪舞していた時期である。大きなうねりが寄せる時の波打ち際のように、いくつもの「終り」がこの時期に重なってやってきていた。「近代の終り」「共産主義の終り」「ユートピアの終り」「企ての終り」、さらには「冷戦の終り」「戦後の終り」等々。だが問われるのは「終る」ことではない。さまざまなレベルで終り(目的)を目指してきた人間の世界は、いつか「終り」の敷居を踏み越えて、もはや「終り」に導かれることのない未知の圏域に踏み込んでいる。歴史の運動が輪を閉じてひとつになり、巨大な混沌を経てあらゆる差異や階層が組替えられようとする世界こそ、「ワンダー」という語の二重の意味(不気味な、すばらしい)において「ワンダーランド」である。
そのいくつもの「終り」の兆候を念頭におきながら、近代の思想が背を向けてきた「人間が死ぬ」ということの考察をベースに、しかし「死ぬことが不可能だ」という逆説的認識を軸にして、「終る」ことや「死ぬ」ことそのものではなく、「終り」の消滅するプロセスやそれとわれわれの思考の習性との関係を問い質しつつ、そこに洗い出される生存の未知の地平あるいはその予兆を、「死に向けて」ではなくはっきりと「生に向けて」できうるかぎり描き出そうと試みたのがこの本である。
グローバル化の動きがあらゆる境界を押し流し、ひとつの秩序のもとにすべてを溶解しようとする圧力が働いている現在、境界なき世界に新たな差異の文様を蘇らせ、すべての生存の肯定に向けてどのような差異のシステムを再編できるかということが、生命現象から個の成り立ちを経て政治のレベルにいたるまで、あらゆる領域にわたって問われている。二〇世紀思想の「夜」の部分をたどりながらここでなされた考察が、再び「戦争」によって再編されようとしている世界の現在を考えるのに、何がしかの示唆と貢献をもたらすことができればと願っている。
なお、この本の中心は第Ⅲ章「死の不可能性、または公共化する死」にあり、主として第Ⅵ章、第Ⅶ章がその展開になっている。
新版を出すにあたって、本書に関係深い「共同性」のテーマを観点を変えて論じた一章を新たに巻末に加えた。
この本の現代的な意義を評価され、改めて未知の読者に出会う機会を作ってくれた青土社の宮田仁さんに深く感謝する。
二〇〇二年八月九日 西谷 修