| (1) 如此耳<がくぎ>(急に)
「如」は韓国訓で「  <がっ>」。此れを終声を消すと「 <がっ>」。此れを終声を消すと「 <が>」。 <が>」。
「此」は日本訓で「これ」「この」。第一字目の「こ」をとり、これを韓国語の「  <ご>」にあてます。 <ご>」にあてます。
「耳」は韓国訓で「  <ぎぃ>」、これを「 <ぎぃ>」、これを「 <ぎ>」とよませます。 <ぎ>」とよませます。
三字合わせて「    <がごぎ>」。「急に」意味の古代語「 <がごぎ>」。「急に」意味の古代語「   <ががぎ>」または「 <ががぎ>」または「   <がぐぎ>」の酷似音になるのです。現代語で「 <がぐぎ>」の酷似音になるのです。現代語で「   <がぷじゃぎ>」。この「如此耳」と同じことばに「如是耳」( <がぷじゃぎ>」。この「如此耳」と同じことばに「如是耳」(   <がちぇぎ>)と「如是耳也」( <がちぇぎ>)と「如是耳也」(    <がちぇぎや>)があります。新羅の故地である慶尚道一帯、特に慶山・永川など大邱・慶州付近、または金海・馬山・昌寧など南海地方では、現在でも使われている方言です。 <がちぇぎや>)があります。新羅の故地である慶尚道一帯、特に慶山・永川など大邱・慶州付近、または金海・馬山・昌寧など南海地方では、現在でも使われている方言です。 |
 gat-da カッタ(同じだ)」の語幹である。一見もっともらしく見えるが、実はこの1つめの単語からして、すでに致命的な誤りがある。「
gat-da カッタ(同じだ)」の語幹である。一見もっともらしく見えるが、実はこの1つめの単語からして、すでに致命的な誤りがある。「 g@d」であった。ここで、母音が「
g@d」であった。ここで、母音が「 (a)」ではなく「ヽ(@)」だったことの意味は大きい。母音「ヽ」は16世紀になって「
(a)」ではなく「ヽ(@)」だったことの意味は大きい。母音「ヽ」は16世紀になって「 g@v@r (郡)」と日本語「köpöri (こほり;郡)」のように。従って、もし現代語の「
g@v@r (郡)」と日本語「köpöri (こほり;郡)」のように。従って、もし現代語の「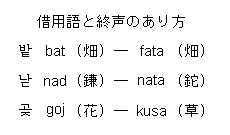 また、李寧煕氏は「
また、李寧煕氏は「
 <せんがく>」(思)、「
<せんがく>」(思)、「

 <さもはる>」(慕)など。後者の「
<さもはる>」(慕)など。後者の「 <じぇ>」。
<じぇ>」。
 <しょ>」にあてます。
<しょ>」にあてます。
 <ど>」「ど」です。
<ど>」「ど」です。



 s@」と母音が違っていたのである。これでは「恋」を「さ」と読む根拠がなくなってしまったわけで、せっかく智恵を絞って考えたアイデアも全てパーになっている。
s@」と母音が違っていたのである。これでは「恋」を「さ」と読む根拠がなくなってしまったわけで、せっかく智恵を絞って考えたアイデアも全てパーになっている。 jie」という形であった。
jie」という形であった。
 <じ>」で、所有格「…の」の意の漢字「之」の漢字音よみにあたります。
<じ>」で、所有格「…の」の意の漢字「之」の漢字音よみにあたります。
 <そむ>」。古代語は「
<そむ>」。古代語は「 <しむ>」(東南部海岸地帯では現在でも「
<しむ>」(東南部海岸地帯では現在でも「 siem」といったが、この単語はさらに古い語形が推測できる。というのも、『日本書紀』に百済の「主嶋」の読みが「にりむせま」であるという記述があるからである。ここから中期朝鮮語の「
siem」といったが、この単語はさらに古い語形が推測できる。というのも、『日本書紀』に百済の「主嶋」の読みが「にりむせま」であるという記述があるからである。ここから中期朝鮮語の「 sie-ma」あるいは「
sie-ma」あるいは「
 <だね>」。一方、三字目の「引」の場合は、日本訓の「びく」に日本音(韓国音も同じ)の「いん」を二重に接合させると、「びくいん」となるのですが、これを韓国語にあてはめると「
<だね>」。一方、三字目の「引」の場合は、日本訓の「びく」に日本音(韓国音も同じ)の「いん」を二重に接合させると、「びくいん」となるのですが、これを韓国語にあてはめると「
 <びきん>」になります。「退いた」「よけた」の意の形容詞です。漢字の「引」自体にも、「退く」の意味が含められています。
<びきん>」になります。「退いた」「よけた」の意の形容詞です。漢字の「引」自体にも、「退く」の意味が含められています。
 <こむ>」(熊)音によく似ています。熊に似ている動物貊<めく>も、古代日本では「こま」と呼ばれていました。「貊」は「貊族」の約で、古代韓国の主流部族であったので、貊は古代韓国人の代名詞とされていたのです。貊イコール熊、イコール篭毛、イコール雲の順序で、韓国貊族は古代日本において「雲」と呼ばれていたわけです。雲は空のくもであると同時に、古代韓国族の異称でもあったのです。貊族は、貊を崇尚したことから、このように称されたといわれています。
<こむ>」(熊)音によく似ています。熊に似ている動物貊<めく>も、古代日本では「こま」と呼ばれていました。「貊」は「貊族」の約で、古代韓国の主流部族であったので、貊は古代韓国人の代名詞とされていたのです。貊イコール熊、イコール篭毛、イコール雲の順序で、韓国貊族は古代日本において「雲」と呼ばれていたわけです。雲は空のくもであると同時に、古代韓国族の異称でもあったのです。貊族は、貊を崇尚したことから、このように称されたといわれています。
 <ぬん>」。これを酷似音の「
<ぬん>」。これを酷似音の「 <ぬん>」(nun)とします。助詞の「…は」と、同語です。
<ぬん>」(nun)とします。助詞の「…は」と、同語です。 'yn ウン」であるためである。つまり、「隠(
'yn ウン」であるためである。つまり、「隠( n ン」を「
n ン」を「 <じなる>」。「経過する」「住む」の意である。
<じなる>」。「経過する」「住む」の意である。
 <と>」。「土地」、陣地、領地などの意です。新羅ことばでは「
<と>」。「土地」、陣地、領地などの意です。新羅ことばでは「 <て>」と発音します(慶尚道では、現在でもこのように発音しています)。この「
<て>」と発音します(慶尚道では、現在でもこのように発音しています)。この「 <で>」に使います。「場所」の意です。
<で>」に使います。「場所」の意です。 - ji-na-」(過ぎる)に連体形の語尾「
- ji-na-」(過ぎる)に連体形の語尾「 r」がついた形である。末音の語尾「
r」がついた形である。末音の語尾「 'i」がくっついた形だからである。
'i」がくっついた形だからである。 te-h」のように、語末に「
te-h」のように、語末に「 d@i」という形であった。現代語ではお互い似ている形でも、中期語までさかのぼると、全く違った形になってしまう。ここでも「酷似音」の論理はもろくも崩れ去ってしまう。
d@i」という形であった。現代語ではお互い似ている形でも、中期語までさかのぼると、全く違った形になってしまう。ここでも「酷似音」の論理はもろくも崩れ去ってしまう。


 <おぷする>」(ep-sul)。この第一字目は初・中・終声全部そっくり使い、第二字目は終声だけ消して利用します。「
<おぷする>」(ep-sul)。この第一字目は初・中・終声全部そっくり使い、第二字目は終声だけ消して利用します。「 <おぷす>」とするのです。
<おぷす>」とするのです。
 <おぷすに>」。
<おぷすに>」。 zi」であった。おそらく「ジ」のような音であったと推測される。この時点ですでに李寧煕氏の解釈は破綻しているのだが、さらに追い討ちをかけよう。再三再四でてくる「新羅言葉」、もちろんここでも単なる慶尚道方言に過ぎないわけだが、慶尚道方言の「
zi」であった。おそらく「ジ」のような音であったと推測される。この時点ですでに李寧煕氏の解釈は破綻しているのだが、さらに追い討ちをかけよう。再三再四でてくる「新羅言葉」、もちろんここでも単なる慶尚道方言に過ぎないわけだが、慶尚道方言の「 ] である。鼻母音は慶尚道方言の特徴で、これを表記する方法は現在のハングルの正書法にはないため、しかたなく「
] である。鼻母音は慶尚道方言の特徴で、これを表記する方法は現在のハングルの正書法にはないため、しかたなく「