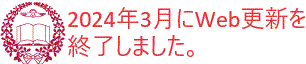2020年後期 リベラルアーツ基礎B(国際) 学生からのコメント
みなさん、授業にコメントありがとうございます。
いろいろな国の人と話してみたいという気持ちがある私にとってこの授業で本や考えたことはすごく生かされると思いました。グループディスカッションをする場面というのは考えてみるとあまりなくて、毎回楽しく学べました。ありがとうございました。
1月25日 この授業で他学科の人たちとたくさんディスカッションできいい機会になりました。
1月25日
ほかの人たちから、話し合いの進め方を学びました。また、私だったら絶対に浮かばないような考え・意見を知ることが出来て良かったです。
私の学科は他の学科の人と関わることが少ないので、この授業を対面で受けることができて良かったです。
1月25日
リベラルアーツ基礎Bは、教科書の内容に沿って勉強するようなスタイルではなく、グループワークを通じて異文化や現状について初めて詳しく学べて理解できました。人との話すのが得意でありませんでしたが、クラスの皆さんがとても優しくて意見交換をしやすかったです。毎回の授業が有意義な時間でしたので、取って良かったです。
1月25日
韓国が思っていたよりも厳しいというより、韓国以外にも日本の周りの国の基準が高いのが驚きでした。それぞれ国内で歴史的背景や文化に縛られているなど、改善する部分は多少伺えたものの、日本が見習うべきところは十分に多いのでないかと感じました。今後のグローバル発展において、どの国も同じ土俵の上でトップ(常に上)を目指して行くことになって行くので、日本も競い合って協調性を持ちながら、発展して行くこと願います。
1月21日
1つの意見として… 発表を2回に分ける日に、1回目の発表が終わったらまたグループを変え、2回目は違うグループで話し合いをし発表者するのも面白いと思った。
1月20日
私は中学生の頃から韓国ドラマが好きで韓国の文化や人に憧れを持っていましたが、韓国社会は厳しい競争社会で、思ってた以上に貧富の差が激しいことを知り、憧れだけで自分が日本人でよかったと思ったのが率直な感想。韓国人の深い友人関係は良いと思う。
1月19日
15回の授業を通し、日本と他国との違いを学ぶことが出来ました。異文化を理解する上で、各国の背景などもよく考えなければならないと思いました。
1月19日
一年間の通じて、自分でまとめたことを言葉にすることが大変でしたが、とても大学生らしい授業をしていたと感じました。
1月19日
私は大学に入学してからのこの1年間を通して、この授業が最も自分の為になったと、学ぶ価値があるものだと思いました。今までにない学習スタイルと、国際についての本質・リアルな内容に触れることで、学生のうちからこのような貴重な経験や知識を得ることができて授業を選択して本当に良かったと感じています。
1月19日
しっかりとまとめて、明確化したものを発表できるように頑張りたい。
1月18日
今回は論点が難しく、発表できませんでしたが、日本の教育を変えるとか自分をアピールすることが大切など他のグループの意見を聞いて納得しました。
12月28日
日本の学校教育では話し合いや相談は授業で行われることが多いが、議論する機会が少ないように思った。簡単な題材を扱えば小学校高学年からディベートを実践できると思う。議論の機会を積極的に作ることが大切だと感じた。自分の短所は多く上げられるが、長所・強みをはっきりと言える人は少ないのではないか。入試や就活の時期になって自分について考え始めるのではなく、日頃から自己分析をしていきたいと思う。
12月27日
今回の題は、初めに取り扱っていた内容と似ている部分があると私は思いました。また、グループの話し合いの中で、授業初期に比べて今の方が日本人と他国の人々との違いを様々な角度から見て分析できていて、着実に力はついているのだと感じました。
12月23日
この授業を受けるたび日本の悪い部分がよく見えるようになってきている。これは今まで自分がそういう現実を当たり前のように過ごしてきたからでもあり、日本だからと背いていたからでもある。受けていくうちに、日本という組織を言い訳に、自分を出さないようにしてきたと思う。自分の主張をいかに自分のものにするかがさらに今回のではっきり大事だとわかった。
12月22日
今まで様々な人間の本能を学んだ。
人間の言動には様々な本能が関係している事を学び、これらの教養があれば世界で起きている多くの問題を冷静に考え、客観的な考察ができると感じた。
12月21日
情報があふれる今日において、完璧な情報を見つけるのは非常に困難とも言えるが、情報を鵜呑みにすることなく、常に疑いの目を持ち、様々な人と意見交換をしながら自分なりの考えを持つことが大切だと感じた。また、学校で学ぶことは10年後20年後には時代遅れであるため、知識をアップグレードするために、同窓会などで勉強会を開くなどといったことも必要だと思った。
12月18日
さまざまな本を読み、みんなで話し合うことで周りから学ぶこともできるので、毎回いい経験になっているなと思いました。
12月16日
授業も終わりに近づき、私達は授業内で取り扱う大きな題材の二つの本を読み終えました。初めの頃と比べると私達は皆、考える力やディスカッション能力、話し合いに参加する意欲並びに発言する意欲が明らかに身についていると感じます。
12月16日
今回の話で古い考えが全て正しいものではないと知った。また、教える人は自ら日々学んでいかなければいけないと感じた。
12月16日
ファクトフルネスの10のルールにおいて、共通・軸となるものはなにか。グループ内では大人も学び続けることと、何事も疑うということが出た。疑うことは、単純に物事を慎重に見るということだが、大人も学び続けるというのは、進化について行くようなニュアンスだと思う。世界は常に変化し、中途半端(理解をしていない状態)のまま新しいことが次々出ている。私は学ぶことをやめてはいけない理由を本書で理解できた。
12月16日
最近、考えすぎて話がまとめられません。
12月14日
どのようにすれば世界の状況を正しく理解できるのか考えた。教える側の情報が古いことやSNSの情報の不確かさ、ニュースの都合のいい部分だけを見せているなど。私はニュースは全てが正しく伝えられていないのではと感じた。色々考えた結論として、ニュースは嘘の情報ではなく、事実がある情報源や流してる情報の理由(こちら側のメリット・デメリット)を考えて聞けば、しっかり根幹の部分を理解できると思った。
12月10日
『ファクトフルネス』の講義になってから着眼点が難しく、なかなか発表まで話が煮詰まらずに終わってしまう。グラフが直線やs字カーブなど、どんな線を描いていたとしても、4段階のレベルによって差が出ないようにフェアトレードやエシカルなものを購入するなどといった平等に近づくための努力が必要だと感じた。
12月8日
現在授業で扱っている媒体の内容が難しいとの声が生徒内で上がっていましたが、私はむしろ今の本にとても面白さを感じています。自分が考えもしなかった視点から話が展開されたり、まだまだ自分の知識が至らないことを痛感する場面が多々存在したり、社会の仕組みや世の中の現状、我々が歩んできた過去まで、とにかくなるほどと感銘を受ける内容が多くあり、これからの自分の為になる情報ばかりなのでつい読み入ってしまいます。
12月8日
国連が検索エンジンを作るという発想がなかったのでなるほどなと思いました。
12月7日
自分の言葉に責任が持てないと、メディアをさらに自身で調べようとすると「ネット」に頼ってしまうと、聞いて、自分自身もすぐネットに頼ってしまう癖があるので気を付けていきたいと思います。
12月7日
発展途上国にボランティアに行った際、現地のお年寄りに「他の国から支援金をたくさんもらっているが、政治を握る人が私用に使い国は全く良くならない」と言われたことを思い出しWorld Health Cheartでもっらた支援金とインフラの普及を組み合わせた所、10年前よりも大幅にインフラが普及していた。本人たちに自覚がないことにとても驚いた。
12月7日
自分が調べたグラフ以外の組み合わせを班の人たちや発表した人たちから知り、組み合わせによって様々なことがわかるなと思いました。
12月6日
今回正直あまり他の人との意見が聞けた感じがしなかった。しかし、自分もあっとするような発言をできなかったので、どこのフォーカスして話し合うか、相手の意見を引き出せるような聞き方をしていけるようにしたいと思う。ネガティブな本能を持つのであれば、それを補うくらいの周りの力が必要である。一人でどうするかではなく、周りが影響し合うことで変わって行くと思う。実際に日本人は周りに流れやすい傾向にあると思うので。
12月5日
ネガティブ本能を見直すためにも世界は悪くなっていると決めつける前に正しい歴史を学び、過去を振り返り、過程を知ることが大切だと思った。ネガティブなことが注目されやすい理由として悪いことは線引きしやすいが、良いことは非難する人もいるためリスクが高いという意見に納得した。
12月4日
後半に述べられていた、世界は良くなってきていると主張をする人は、決して「世界について心配する必要がない・世界の問題に目を向ける必要がない」と言っているのではなく、「世界にはまだまだ沢山の問題は存在するけれど、昔に比べたらいい世の中になったよね」と言いたいという内容を読んで、なるほどと思いました。言われてみれば納得できるし、補足の言葉を付けて言われるだけでこんなにも印象が違うのかと感じました。
12月1日
日本がネガティブな報道が多いのはそのほうが売れるという報道陣による暗黙のルールなのだと知った。
12月1日
今回の授業を通じて、検索エンジンが私たちの中で生活の一部になってきているのだと感じた。最近、googleが独占して提訴されたというニュースをみて驚きました。
12月1日
多くの情報で溢れ簡単に情報が手に入る今の時代だからこそ、自分が持つ固定概念だけを基準に物事を見るよりも、4つのレベルに分けて正確な思考法を身につけることが重要だと感じた。
11月30日
今後、世界が発展しものの価値が上がり物価が上昇して、安いものが減っていくのではないかと思った。4つのレベルは現在の内容としては、少し低すぎるのではないかと考える。それは4レベルの地域が増えてきているからだ。日本はほとんどの人がレベル3、4のどちらかにいるだろう。それがどれだけ恵まれていたことだったのかを今回の授業を通して改めて実感させられた。
11月30日
今回の資料を読んで、なぜ多くの人が現在も1965年のデータのイメージを持ち続けているのか疑問に思い、話し合いをしました。資料の著者の意見の他に、義務教育で習う「先進国•途上国」はこの授業のように深い内容でないからだという考えに至りました。また、4段階のレベルを知らず、メディアの影響を受け、(ユニセフのCMなど)受けたイメージで一括りに捉えてしまうからだと考えました。
11月30日
私は低所得が多い=貧困、発展途上国とイメージが出てしまっていたが、自分たちの国を基準に見たものは必ずしも正しくないと考えた。私たちの考えは、人々の幸福度がその国の安全や状態、手を加えるべきか否か判断できると考えた。お金がなくとも、不自由のない(それ以上を求めない)暮らしをしていると答える人が多い国は、どの国とも比べる必要性がないと思う。反対に少ない国は何が足りないのか見極める必要性がある。
11月27日
小中高の授業では先進国、発展途上国と習ったので4つのレベルに分ける方法は新鮮でした。分断本能が働く理由として、二つに分類した方が分かりやすい、簡単ということ、自分を基準にして考えてしまうからなのではないかと思った。常に自分の中の情報を更新して、脳もアップデートしていかないといけないと感じた。
11月26日
今回の資料は、前回実施されたテストの解説になるような興味深いことが多く書かれていました。筆者が伝えたい「世界を2つに分けることはやめよう」というメッセージと、それによって得られる利点、またこれを進めていくための具体的な考え方などがしっかりと挙げられていて、説得力があると感じました。文中にもあった通り、我々が想像するほど低所得国の暮らしは苦しくないし、その人口も多くはないのだと知ることが出来ました。
11月26日
シンガポールは横断歩道以外の横切りは禁止なのはぜひ日本にも取り入れてほしい法律だなと思いました。
11月25日
授業の後半に行ったアンケートがとても興味深かったです。自分の知識やグループの話し合いで導き出した答えが正解とずれていて驚きました。原因は、知識の不足と、自分の頭中の固定概念のせいだと考えました。どんどん新しいことを知れてとても面白いです。
11月24日
多民族国家の形成の共通点として、異なる民族同士が自分の文化・宗教を尊敬しつつ、多民族の宗教も受け入れることが挙げられると考える。特にシンガポールでは、憲法により少数派民族の権利保護が保証されている。同調圧力や横並び意識のある日本ではこのような文化(意識)は重要視されないが、取り入れるべきだと感じた。
11月24日
シンガポールは公衆衛生と環境に関する法律が厳しいことを知ったが、シンガポールが熱帯雨林性気候のど真ん中に位置することから、伝染病や感染症が発生しやすかったり、華人の習性、トップダウン式の政治などといったことが関係していることが分かった。シンガポール人は愛国心が強いようだが、逆に愛国心が低いと言われる日本人の理由が気になった。
11月19日
シンガポールと日本の関係やそれぞれの歴史的背景を理解することができました。
11月17日
今回の授業の後半で実施されたテストの内容と結果がとても印象に残っています。自分を含め多くの人達が誤答をしていたことに驚きました。これまでに受けてきた社会科などの授業を通して、ある程度の知識は持っているはずなのに、世の中状況をしっかり理解しているようで全然分かっていないのだと自分達の未熟さを痛感しました。
11月17日
高校生の時に、台湾や香港について同じようなディスカッションがあったがほとんど何も出来ずに終わってしまった。しかし今は政治や文化、歴史について自国との違いや客観的な視点でその国のナイーブな事情を考察できるようになり、リベラルアーツ力の修得を感じている。
11月16日
台湾人は日本への関心が高いということだったが、私は台湾と聞いて思い浮かぶモノやイメージが少なかったのでこの機会に台湾についての知識を増やすことができて良かった。外国に行くときは自分が恥をかかないためにもその国のマナーや常識をある程度知っておくことが大切だと思った。
11月16日
今回の内容の中で自分的に議論を発展することができなかった。新しい意見や発見をするために、どのように議論をして行くべきか他の人を見習うべきだと再確認した。台湾の教育視点で歴史分野を見たところ、昔は西洋史・中国史のみだったが、今は台湾史・西洋史・中国史となっており、台湾が時代の流れとともに変わっているのが教育の面でもわかった。
11月16日
今回はこれまでの題材とは異なり、「台湾」という国についてピンポイントで議論するということで、より深く内容を深めることができました。台湾の人々が外食をする機会が多い理由は食べ物屋さんが多くかつ物価が安いからと知り、なるほどと納得しました。この話を聞いて、羨ましさを感じたと共に、より台湾に行きたいという気持ちが高まりました。
11月10日
クオーター制について、とても関心しました。
内閣府の報告書 IIIの下のほうにあります。11月9日
中高の異文化理解は目的がはっきりしていなくて、実践的ではないという意見を聞いた時に、確かにその通りで、ただ授業をしているだけにすぎないのだと感じました。
11月9日
今週の台湾の範囲が楽しみです!
11月9日
同じチームの人と意見を交換し合える事はもちろん、チームの意見に対して教授から客観的な意見がもらえることがとても良い刺激になる。”ただ座って教授の話を聞いているだけ”ではない所がこの講義の良い所だと思う。
11月9日
高校までに習う世界の授業では国ごとの文化や宗教、地理などを扱うことが多く、表面的な知識は身につくが、今回習ったようなその国の人の思考や特徴といった内面的で実践的な内容にあまり触れないので、世界の教養としてもっと異文化理解に努めるべきだと思った。
11月9日
11月9日から台湾の若者たちについて学ぶにあたり、私が心からお勧めするYouTubeチャンネルがあります。「サンエン台湾」です。日台友好を目指しています。「台湾人が思う日本人の変なところ」「台湾人は日本人が好きか街頭インタビューしてみた」などとても面白く、台湾人についてよく知れるチャンネルです。真面目な感じではなくて、バラエティーなので楽しく視聴できます。
11月9日
今回のでかなり異文化との関係性やどうあるべきか考えられた。今回のまとめを踏まえて、異文化とか他国で微妙に価値観が違うことを否定的に捉えてしまった人もいると思う。しかし、最初からみんな同じであれば。ある意味人と人とを比べて自分たちを見つめ直すことはなかったと思う。どこも似てても同じではない。でも共通する大事なものが必ず1つあることを念頭に置いて接することがビジネス面でも日常の面でも大切だと学べた。
11月9日
早いもので、題材にしていた本の一冊目を今回の授業を最後に読み終えることが出来ました。それにあたり、私達のグル―プでは本全体の締めと筆者の伝えたかったことについて議論が盛り上がりました。発表でも言った通り、このような実践的で、社会に出た時に役に立つ「本当の異文化理解」というものへの学びを日本のみならず、世界全体で一般教養化していくべきだと私は思います。
11月4日
メラビアンの法則によれば、話をする際に相手に伝わる情報として、話の内容が7%・声の大きさやトーンが38%・見た目(表情)が55%を占める。異文化を持つ人に対して話し方をどうこうするよりも、良い話の時は笑顔で声のトーンをあげる等の方が効果的ではないかと考えた。
11月2日
ディスカッションにも出てきたように異文化理解は世界共通の教養としてもっと教育にも取り入れていくべきだと思った。本の中にも異文化を理解していないがために生じた様々な行き違いの例が出ていたように、「知らない」ことほど怖いものはなく、日本は島国と雖も積極的に異文化について「知ろうとする」ことが大切だと改めて感じた。
11月1日
グループで話してあったときに出た考えを、ほかのグループと比較したりすることによって、新しい考えを知ることができ、さらに学びを深めることができるのでより理解も深まりいいなと思いました。
10月29日
個人的にネガティブな発言を遠回しに言うとか、はっきり言うとか文化の違いで難しい問題ではあるが、ネガティブなことを本人に気付かせる、「この部分でダメだったところがあるんだけど、わかる?」と言ってから、はっきり言っても嫌な気分にはならないと思った。効率的ではないが、自分で発見できる点ではいいことだとおもう。
10月28日
次週でやっと、始めから皆でずっと進めてきた「異文化理解力」という本が読み終わります。これにあたり、やはり後半になるにつれて内容が難しくなっていると皆も同じように感じているようで、前半に比べて考え込む場面が多く見られるなと思いました。このことは一概に悪いという訳ではなく、自分の考えがより皆に伝わりやすくなるよう、しっかりまとめてから発言しようという努力の現れだと私は思います。
10月27日
言語の特徴のために「空気を読む」ことが必然的になっているということと、歴史の長さや民族単一性の度合いが各文化のコミュニケーションスタイルに反映されるという、知らなかった視点を持つことができて良かった。今まで疑問に思ってきた「日本人はなぜハイコンテクストなのか」の理由が少しずつ見えてきて、異文化理解の授業でありながら、日本人について知る機会に繋がってことが面白い。
10月24日
最近グループ内で意見交換した後に、個人の中で考えを深めようとして、それぞれが考え込む場面が多く見られるようになりました。決して議論が活性化していないわけではないことを、ご理解していただきたいです
10月22日
1人で読むよりもみんなで話し合った方が意見がたくさん出たら考えが深められました。
10月20日
ある程度授業数をこなしてみて、全体の空気が良い意味で軽く、明るくなったなと感じました。授業スタイルにも慣れ、生徒同士が打ち解けてきた証拠だと思います。そして、毎度話し合いをするグループのメンバーを変える事によって色々な人とディスカッションをする機会が設けられ、より多くの自分とは異なる考え方に触れることができ、私は非常に楽しさを感じています。
10月20日
私たちは日本人の礼儀文化について討論した。ハイコンテクストの風潮を持つ人々自分の発言や行動を控える・あえて言わないということを日常的にし、日本人は特にそれを建前や礼儀だと言葉で表す。自分たちがハイコンテクストな文化であると気づくあるいは教えてもらえば、本当にそれは礼儀?と疑問を持つ。その時に、説明できない礼儀は日本の中で無くすべきだと考えた。
10月20日
最初はどうしていいかわからなかったが、討論していくごとにお互いに意見を言い合うことができて、それなりの意見もグループで発表することができたので良かったです。
10月19日
ステレオタイプという言葉だったり今まで聞いたことがあったけどよく理解できていないことを今回少し理解できた気がします。次回もっと深められるように色々な情報に目を通したいと思います。
10月19日
例えば、自動車の運転歴10年の自分の前に初心者マークを付けた車がいたら「きっとまだ運転に慣れていないだろうから車間距離をいつもより長めに空けて私も気を付けて運転しよう」と考える人が多いと思います。この先入観があれば交通事故を未然に防ぐことができます。ステレオタイプ(先入観)は一概には悪いと言えないのではないかと考えました。
10月19日
日本にあるステレオタイプは皆に当てはまらないという事は海外のステレオタイプも全員が当てはまらないという事を再確認出来ました。
10月19日
ステレオタイプは必ずしもマイナスな考え方やイメージを表すわけではないということを再確認できた。国際的な環境で働く中で成果を出すために「日本人的なやり方を重視するべきか、一緒に働く人に完全に合わせるか」という問題に突き当たるが、今回のディスカッションの中でどちらも大切だという結論に至った。個を大切にしながらも柔軟な対応が求められる。「結局は信頼関係が重要」という考えに共感した。
10月19日
今回の内容では、実際に感じた印象と元々イメージしていた印象の差があり、それについてどこからそんな偏見がついてしまったのか、持っていると自覚している人は多いのか気になった。また、ニュースで韓国人が日本人に対する印象が悪いかというアンケートで2013年から始めて、過去最低の約70パーセント越えをしていたのを見て、まだまだそういう偏見は多いのかなと感じた。
10月17日
2人グループだったにも関わらず、様々な意見が出て良いディスカッションとなりました。自分たちの納得のいくまで追求できたので良かったです。
10月16日
毎回違う人と意見を交換でき、なるほどなと学ぶことがたくさんあります。
10月16日
この授業を受けてまだ4回目ではありますが、さっそく自分の力になっていると思う場面と遭遇しました。それは他の授業で、グループディスカッションをしろと指示された時のことです。この時私はいつもこちらの授業で行っているよう「とにかく自分の意見を言う、進んでその場を仕切る、皆が発言できるような機会や空気感を創る」などこれらのことを自然とこなしていました。ここで、知らぬ間に力が備わっているのだと実感しました。
10月16日
リベラルアーツ力を高めるには等の意見が沢山出て、とても面白い授業でした。日本の学校では、生徒の先生の距離が遠いと感じたりと実践力に結びつかない授業をしていたのだとあらためて思いました。
10月13日
各自、意見を持って講義に臨んだため活発な話し合いになった。第1章に関して、”日本の政治的中立と宗教的中立を守った教育方針と、アメリカの様々な著名人の考え方に触れる教育方針の違いが自然と『自分の意見を持つ』習慣になっているのではないか”という私の考えにメンバーから「その考えはなかった」と絶賛されたことが嬉しかった。教職もとっているので、それらの知識も活かしながら授業に積極的に参加したい。
10月13日
発表後に先生が発表した班の意見についてどう思うか問いかけてくださるので、本当にその考えがあっているのか考える機会ができます。
10月12日
今回の講義でも自分とは異なる視点や意見に出会えてとても充実したディスカッションができました。世界基準の子どもの教養を考えたときに、私たちの班では日本の教育制度を欧米と比較して問題点を取り上げました。別の班の発表で「環境を言い訳にしない」という言葉が心に刺さりました。
10月12日
3回目にしてお互いに慣れてきたのか、話が盛り上がったり膨らんだりすることができたので楽しかったです。
10月9日
伝えたいことが伝わっていない部分があった気がするので、しっかり伝えて行きたい。
10月7日
今回私たちのグループでは「肌色」という言葉について議論が盛り上がりました。我々は「これは肌色」と教わったので今まで何の違和感もなく使ってきた言葉ではありますが、完全日本人主体な偏った考え方・表し方だと実感しました。このように、自分では何気なく使っている言葉が「誰かを傷つける差別用語かもしれない」と一旦外側の目線から、客観的な視点から考える機会が、我々には必要なことだと思いました。
10月6日
グループ討論の面白さに気付くことができた。もっと、自分の意見をまとめて言えるように頑張りたいです。
10月5日
予習にある文章が興味のある内容だったのでディスカッションをしてさらに理解を深めることができて良かったです。文章が共感できることが多いのでそこからさらに自分の意見や案を出すことは考えを広げる良い訓練になりました。
10月5日
留学経験から”空気を読むこと”や”言葉を曖昧にする”日本の文化に疑問を感じていたので、ディスカッションを通して様々な意見が聞けてとても楽しかった。
10月3日
グループに静かな生徒が数名おり自分の意見が無いようだった為話し合いが進まない場面も見られた。色々な性格の人がいると思うので上手く接していきたい。
10月3日
『空気を読む』ことが当たり前のようになっていて無意識にいつもしている事なので、改めてこの点において外国人労働者に対してどう対応すれば良いか考えるのがとても難しかったです。
10月3日
日本人部下に指示を伝える場合は相手に不快感を与えないようにオブラートに包んだような言い回しをすることが多い。この、相手を想っての話し方は日本人同士の場合は通じるが、外国人部下には逆に解読不能な難しい言葉でしかない。そこで、外国人を相手に話をする際には、指示の理由を明確にストレートに伝えることが大切だと感じた。
10月2日
2回目ということもあり、自分自身も周りの生徒達も前回に比べてスムーズに動けていたと感じました。本格的に授業がスタートし、言われていた通り「予習」というものの存在、そしてこれを他の課題と同時にこなさなければなりません。量も多く大変ですが、その分自分の糧になると信じて、これからも全力で授業に取り組んでいきたいと思います。
10月2日
前回と比べて一人一人が積極的に話し合いに参加しており、様々な方面から多くの意見が生まれた。私たちの班は積極的に発言もできたので、より考えが深まった。
10月1日
様々なグループから指示が正しく伝わらない理由と解決策を発表していて、自分のグループでは考えなかった考えがあって、とても面白かったです。
10月1日
じゅ御油の内容に関して共感だけでなく、反対意見を見つけておくべきだと感じた。共感や似たような意見を繰り返しても結論が似通ってしまって議論が白熱しなかった。次はいろんな考えを聞けるように相手にも質問を投げて行きたいと思う
10月1日
後期もよろしくお願いします。対面でとても嬉しいです。
9月18日
違う学科の人たちと同じテーマについて意見を出し合う機会があまりなかったので、楽しみだなと思いました。
9月18日
世界のあらゆることについて、他学科のひとたちと意見を交わすことができるので、良い機会になると思いました。
9月17日
複数の学科が集まっているので、グループの発表を聞いていてさまざまな考え方があっておもしろいと感じました。
9月16日
生徒同士の交流があることで、他の人の意見を聴くことが出来ました。
9月16日
この授業は様々な意見を聞けるとてもいい機会だと思います。これからの授業が楽しみです。
9月16日
初回でしたが、グループ内で意見交換ができていたと思う。今回発表したが、他のグループにうまく説明できなかったと感じたので、次回から言葉選びにも注意して、伝える努力をしたいと思う。
9月16日
考えをまとめたり言葉にすることの難しさを改めて感じた。また、いろいろな意見があり、自分には考えられなかった見方や考え方ができるようになる授業であると思った。
9月16日
私たち日本人はアジア圏に所属しているにも関わらず、国名と位置が一致していたのが半分くらいしかなかったので、これしか合っていないのかと少し恥ずかしくなった。異文化間ソーシャルスキルのチェックをしたときになんとなく結果が違ってくるのではないかと予想できたが、なぜ違うのかを考えたことがなかったので意見を交換しながら納得し、興味深い考えに出会えたことが良かった。
9月16日
授業でのグループワークで自分の意見を出し話し合いをすることができた。
9月15日
自分の意見がグループの意見として採用されたことが嬉しかった。国際的な問題や異文化について考えることが好きなので頑張ろうと思う。
9月15日
生徒同士の交流があることで、他の人の意見を聴くことが出来ました。
9月15日
ディスカッションで自分の意見の伝え方やグループ全体の意見の全体まとめ方について学ぶことが出来ると思いました。
9月15日
やっと教室で授業を受けることになり、久しぶりに人と話し合いができる賑やかな学習をし、とても楽しさを感じました。この様な授業スタイルは学生の学ぶ意欲を存分に引き出してくれて、非常に良いと思いました。
9月15日
みんなと話し合いをしながらどんどん意見を出していくのが楽しかった。発言の機会を設けてくれることで考えることも増えてよかった。
9月15日
home