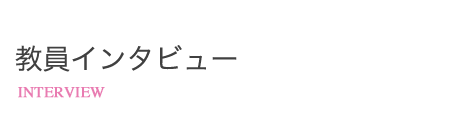イリス・ハウカンプ Iris Haukamp

- 役職/
Position - 大学院国際日本学研究院 講師
- 研究分野/
Field - 映画論
映画を通して考える日本の歴史と未来
私はイギリスのロンドン大学アジア・アフリカ研究学院(SOAS)で日本映画を研究していたのですが、アジア・アフリカ研究教育コンソーシアム(CAAS)のプログラムで、2015年から東京外国語大学にやってきました。日本映画の中でも1920年代から50年代が主な研究領域で、特に映画監督の伊丹万作に注目しています。
『お葬式』(1984)などで有名な伊丹十三監督の父親としてご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、実は伊丹万作自身、俳優や脚本も手がけるほど多才で、非常に優れた人物でした。徹底したリアリストであり、新聞や映画雑誌への寄稿を読むと、当時の社会情勢を冷静に分析し、的確な指摘をしていることがわかります。敗戦翌年に発表されたエッセイ「戦争責任者の問題」(1946年8月)では、「だまされるということ自体がすでに一つの悪である」と主張し、大きな議論を呼びました。
映画監督としては、寡作だったことに加え病弱で、肺結核を患い、1946年9月に46歳で夭折してしまったため、作品数は多くないのですが、どれも人気がありました。代表作のひとつで、江戸時代の伊達騒動を下敷きにした『赤西蠣太』(1936年)では、片岡千恵蔵が一人二役を演じており、エンディングではワーグナーの「結婚行進曲」を流すなど冒険的な試みもされています。
この映画が公開された1936年は、ちょうど満州事変を経て、軍部が中国での戦線拡大を画策していた頃。映画では、そんな軍国主義への批判ともとれるシーンも見られます。映画というのは、当時の社会世相を反映すると同時に、それに対する製作者の考えや意図を読み取ることができます。戦時中の映画を研究することで、人々がいかに戦時を生き抜いたのか、また戦時下のメディアの役割とはどのようなものだったのかを探ることが私の研究テーマでもあります。
現在、シリアの内乱を発端とした難民危機がヨーロッパを襲っています。ISの動画を使った宣伝政策や、難民受け入れを渋る国々の報道などを見ていると、第二次世界大戦直前と同じ状況が起きているのではないかと心配になります。
4月からの授業では、日本の戦争映画3本を題材に、細かな台詞やカメラのアングルなども含めて製作者の意図を探るような内容にしていきます。メディア、政治、社会の相互作用を検討・理解することをつうじて、日本の歴史・現在・未来についてあらためて考えるきっかけになれば幸いです。