|
図解 アラビア語文法
【属格(所有格)支配】
イダーファとは?
アラビア語では所有「〜の・・・」が、てにをはに相当する語句ではなく、「〜」に相当する名詞(ムダーフ イライヒ;مضاف
إليه)と「・・・」(ムダーフ;مضاف)に相当する名詞の前後関係、語末に来る母音の種類などによって示されます。
このような属格(所有格)支配表現は、アラビア語文法で「イダーファ(إضافة)」と呼ばれます。
仕組み
属格(所有格)支配は、次のようなルールに則ってなされます。作文をする際は、脱落すべきものを残さないように気をつけてください。
- 「〜の・・・」のうち、名詞「・・・」が前に、名詞「〜」が後に来ます。
【例:「その家の戸」】
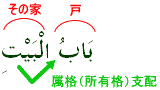
- 名詞「〜」は常に属格(所有格)。格変化は前に来る名詞「・・・」の部分で起きます。
- 名詞「・・・」にタンウィーンがついていた場合、そのタンウィーンは無くなります。
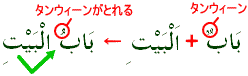
名詞「・・・」が男性規則複数もしくは双数であれば、ヌーン(ن)が脱落します。
これは、「通常の三段変化名詞からタンウィーンが脱落するのと同じ」と考えれば覚えやすいです。というのも、男性規則複数名詞の語末につくヌーンも、双数名詞の語末につくヌーンも、タンウィーンによって付加される「n」と同じであると、アラビア語文法では説明されるためです。
【例:その学校の男性教師たち(男性規則複数)】
| 【主格】 |
|
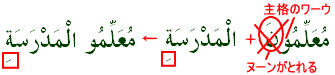 |
|
【属格(所有格)&対格(目的格)】 |
|
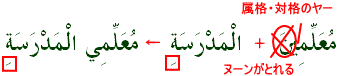 |
男性規則複数の名詞では、通常の名詞とは異なり、主格が語末の母音記号ではなく、語末ヌーンの手前に来るワーウによって示されます。これを、母音記号による格変化と区別し、文字による格変化と呼びます。
男性規則複数の名詞では、通常の名詞とは異なり、属格・対格が語末の母音記号ではなく、語末ヌーンの手前に来るヤーによって示されます。これを、母音記号による格変化と区別し、文字による格変化と呼びます。
【例:その学校の2人の男性教師たち(双数)】
| 【主格】 |
|
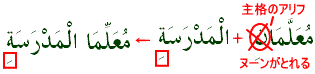 |
|
【属格(所有格)&対格(目的格)】 |
|
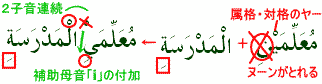 |
双数の名詞では、通常の名詞とは異なり、主格が語末の母音記号ではなく、語末ヌーンの手前に来るアリフによって示されます。これを、母音記号による格変化と区別し、文字による格変化と呼びます。
双数の名詞では、通常の名詞とは異なり、属格・対格が語末の母音記号ではなく、語末ヌーンの手前に来るヤーによって示されます。これを、母音記号による格変化と区別し、文字による格変化と呼びます。
- 名詞「・・・」に定冠詞「ال」がつくことはありません。
「〜の・・・」という、所有を表すイダーファ構文では、前に来る名詞「・・・」には定冠詞「ال」が」つきません。ただし、
2種類あるうちのイダーファ構文のひとつで、通常「複合形容詞」と呼ばれるものには別のルールが適用されることがあります。
【正:「その家の(その)戸」】

【誤:「その家の(その)戸」】
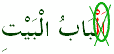 ←定冠詞をつけてはいけません
←定冠詞をつけてはいけません
複数の名詞が続くイダーファ構文
では、「(その)村の学校の先生」などのように、名詞が複数続くイダーファ構文はどうなるでしょうか?
この場合も、基本にそってイダーファ構文が作られます。「村の学校」という部分と、「学校の先生」という部分とを組み合わせ、次のような具合で格変化などが起こるようになります。
- 後ろの名詞によって属格支配を受ける名詞からはタンウィーンと定冠詞を取ります。
【例:「(その)村の学校の先生」】
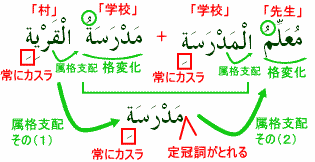
先頭の名詞、途中の名詞は後ろの名詞から属格支配を受けるので、タンウィーンも定冠詞もつきません。しかし、最後の名詞だけは後ろからの支配を受けないので、定冠詞をつけることができます。
-
先頭の名詞以外は前の名詞を属格支配するので、常に属格となります。三段変化の名詞なら常にカスラ、二段変化の名詞なら常にファトハです。
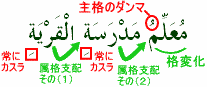
- 格変化は先頭の名詞で起きます。文中の位置によって、主格、属格、対格かが決まります。
【主格】
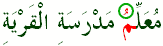
その村の学校の先生は
【属格(所有格)】
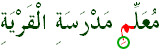
その村の学校の先生の
【対格(目的格)】
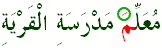
その村の学校の先生を
ここでは3つの名詞を並べましたが、それ以上の数になってもルールは同じです。作文をする際は、先頭および最後尾の名詞と、途中にはさまる名詞たちとの区別を忘れないようにすることをお勧めします。
非限定・限定の区別
「〜の・・・」を表すイダーファ構文では、最初に来る名詞「・・・」のタンウィーンが取れること、また名詞「・・・」で格変化が起きることを紹介しました。
【復習:「その家の戸」】

ここで次に、名詞「・・・」の非限定・限定について考えてみることにします。名詞「・・・」のタンウィーンが必ず取れるということは、いずれの例においても名詞「・・・」が限定された名詞として扱われるということでしょうか?
実際には、名詞「・・・」は、後ろに来る名詞「〜」が非限定なら非限定、名詞「〜」が限定なら限定、という具合に2つのケースに分けられます。つまり、タンウィーンが形の上で取れたからといって、名詞「・・・」が限定されるとは限らないのです。
【例:その家の戸(主格)】
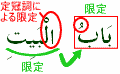 →名詞「戸」は限定されます →名詞「戸」は限定されます
この場合、「戸」という名詞は、後ろから定冠詞で限定されている名詞「家」により属格支配をされています。従って、先頭に来る名詞「戸」は限定されているとみなされます。
【例:とある家の戸(主格)】
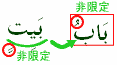 →名詞「戸」は限定されません →名詞「戸」は限定されません
この場合、「戸」という名詞は、後ろからカスラタイン(2つのカスラ、カスラのタンウィーン)のついた限定されていない名詞「家」により属格支配をされています。従って、先頭に来る名詞「戸」は限定されていない(=非限定である)とみなされます。
ただし、限定されていない別々の名詞「戸」、「家」として並べられる時とは違い、「とある家の戸」という風に、指し示される範囲がより狭くなり、あいまいさが減ります。
形容詞による修飾
【基本ルール】
以上のルールを踏まえると、イダーファによって組み合わされた2つないしはそれ以上の名詞の集まりに、どうやって形容詞をつければ良いのか、予想しやすくなるかと思います。
ここで、再度必要な文法事項を確認してみます。
- 形容詞は修飾する名詞の後につきます。
- 形容詞は修飾する名詞と格、数、性、限定・非限定の区別において一致します。
-
イダーファ構文では、先頭に来る名詞の限定・非限定は、後ろから属格支配をする名詞が限定か非限定かによって決まります。
これらのルールに従うと、次のような形で形容詞をつけることになります。「〜の・・・」のうち先頭に来る「・・・」が双数、複数になった場合は、形容詞もそれらに合わせるのを忘れないようにしてください。
【例:その家の大きな戸(限定:主格)】
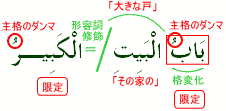
【例:とある家の大きな戸(非限定:主格)】
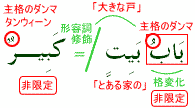
【例:その家の大きな2つの戸(限定:主格)】

【例:その家の大きな戸たち(限定)】

注:人間以外を表す名詞の複数形は、女性単数として扱います。
【形容詞を区別する】
次のようなアラビア語が母音記号無しで記されていた場合、どのような訳が可能でしょうか?

この場合、「大きな戸+その家」と分けることも、「戸+その大きな家」と分けることも可能です。文脈によって判断することは可能ですが、いずれのケースにおいても、母音記号をつける場合は形容詞がどの名詞を修飾しているのかに良く注意してください。
【その家の大きな戸】
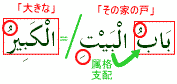
【その大きな家の戸】
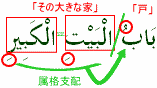
人称代名詞接続形による属格支配
【基本ルール】
人称代名詞接続形による属格支配も、上で紹介したイダーファ構文です。イダーファのルールに従い、主格・属格・対格の時の形は以下のようになります。
【主格:「彼女の本は」】
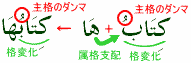
【属格:「彼女の本の」】
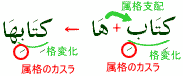
【対格:「彼女の本を」】
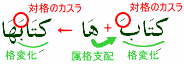
【一人称単数「私の〜」】
「〜の・・・」を表すイダーファ構文では、「〜」の部分が一人称単数の人称代名詞接続形(ي)だった場合、ヤーという音に影響されて、前に来る名詞「・・・」の語末は主格・属格・対格のいかんにかかわらず、常にカスラ(「i」音)となります。
【主格:私の本は】
 ←ダンマになるはずの語末にカスラがつきます ←ダンマになるはずの語末にカスラがつきます
【属格:私の本の】

【対格:私の本を】
 ←ファトハになるはずの語末にカスラがつきます ←ファトハになるはずの語末にカスラがつきます
|