|
図解 アラビア語文法
【「أن」(’an)の用法】
動名詞的「أن」(通称「أن
المصدريّة」)
「أن(’an
)」には、いくつかの用法があります。その中でアラビア語学習者に最も馴染みがあるのは動名詞的な用法を持つ「أن(’an)」であると言えるのではないでしょうか。
【この用法について】
アラビア語を読んでいて、知らず知らずのうちに「このأن(’an)以下は、いわゆるひとつの名詞に相当するのだな。だから、主語や述語として働いているのだろう。」と理解された方も多いと思います。
この用法は、アラビア語文法においては、動名詞に相当する語句を作る「أن(’an)」として知られています。この用法においては、「أن(’an)」は後に来る動詞と共に、動名詞と相当するものとしてみなされます。
【أن+動詞】
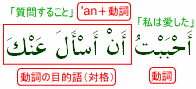
あなたについて私は質問したい(と望んだ)。
【動名詞】
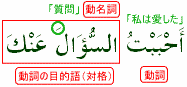
あなたについての質問を私はしたい(と望んだ)。
【後続する未完了形動詞と完了形動詞】
「أن(’an)」の後に来るのは、未完了形動詞と完了形動詞の両方ですが、未完了形動詞が続くケースの方が多く見られます。
- 未完了形動詞が続く場合
未完了形動詞が続く場合には、「أن(’an)」以下に続く動詞は、過去もしくは現在ではなく“未だ行われていない動作(=未来に起こる動作)”を示し、「〜すること」という意味を表します。
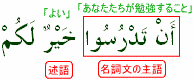
君たちが勉強すること(=勉強)は、君たちにとって良い。
- 完了形動詞が続く場合
一方、完了形動詞が続く場合には、「أن(’an)」以下に続く動詞は過去の動作を示し、「〜したこと」という意味を表します。
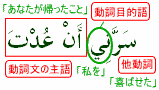
君が帰ってきたこと(=君の帰り)が私を喜ばせた。
上の例のように、文中では、動詞の目的語としてだけではなく、文の主語や述語としても用いられます。例えば、アラビア語で頻繁に使われる以下のような表現も、この用法によるものです。
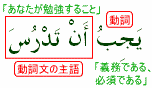
あなたは勉強しなければならない。(あなたが勉強することは必須・義務である。)
【未完了形動詞接続法が続くのはどのような場合?】
上に挙げた例により、「أن(’an)」に完了形動詞が続く場合と、未完了形動詞接続形が続く場合とがあることをご理解いただけたと思います。
では、「أن(’an)」以下に未完了形動詞が続くのは、どのようなケースにおいてでしょうか?ここでは、それについて簡単にまとめることにします。
- 疑念・希望・要望・要求
「أن(’an)」は、
疑念・希望・要望・要求の意味を持つ動詞が前に来た場合、後に続く未完了形動詞を接続法支配しなければなりません。(注:完了形動詞には接続法、要求法といった用法に応じた語形の違いはありません。)
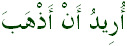
私は行きたい。(=行くことを欲する。)
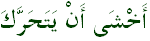
私はそれが動くのではないかと心配している。(=動くことを心配する。)
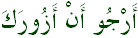
私はあなたを訪れたいと願っている。(=訪問を願っている。)
- 予測
一方、予測(〜かもしれない、〜だと思う)という意味を持つ動詞の後に続く場合は、接続法の未完了形動詞以外にも、そのまま直説法の未完了形動詞を従えることが認められています。
上とは異なり、「知った」「確信した」といった確定した事項を示す動詞が前に来た場合、「أن(’an)」の後に来る未完了形動詞は直説法になるので注意してください(注;下の別項を参照のこと)。
そのような場合、「أن(’an)」は重子音
「أنّ」の発音を軽減した「أن」(アラビア語では「أن
المخفّفة」)であると説明されます。
【この用法において認められない事項】
動名詞に相当する語句をつくる「أن(’an)」の用法では、以下の行為が禁止されます。
- 「أن(’an)」と後に続く語を、別の語によって分離すること
このような用法では、「أن(’an)」と後に続く語が、別の語によって分離されてはならないことになっています。ただし、否定の「لا」などは例外です。
- 「أن(’an)+未完了形動詞接続形」と動詞目的語の倒置
通常の動詞であれば、目的語と動詞の倒置が可能です。しかし、セットになって動名詞と同等であるとみなされる「أن(’an)+未完了形動詞接続形」では、そのような倒置が認められません。
つまり、「・・・は〜を---する」という動詞文において、「〜を」に相当する「أن(’an)+未完了形動詞接続形」の部分を先に持ってきて、「〜を・・・は---する」という倒置文を作れないということになります。
説明の「أن」(通称「أن
المفسرّة」もしくは「أن التفسيريّة」
これは2つの文章の間にはさまれて置かれる「أن(’an)」で、前に来る文章には「言う」「言った」もしくはそれに類する「書いた」「示した」「叫んだ」「命令した」等に相当する語句が来ます。
つまり、この場合の「أن(’an)」は、発言の引用を行うという役割を持っているわけです。
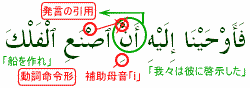
それでわれはかれに啓示した。
「われの啓示に従って、(われの目の前で=この部分は例文に無し)舟を造れ。・・・」
[クルアーン第23章「信者たち」:第27節]
余剰の「أن」(アラビア語では「أن
الزائدة」と呼ばれる)
その他にも、これといった意味が無いにも関わらず追加される「余剰のأن(’an)」も存在します。
余剰な「أن」は、文中で主語や述語、動詞の目的語、前置詞の被支配語などになる表現とは異なり、文法上での格を持つことはありません。
- 時を示す「لَمَّا」(lammā)(・・・時に)の後に来て
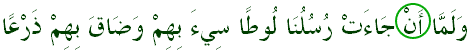
わが使徒たち(天使)がルートのところに来た時、かれは自分の無力さを感じ、人びとのため悲しんだ。
[クルアーン第29章「蜘蛛」:第33節]
- 宣誓と「لو」(law)の間に来て
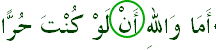
神に誓って、もしお前が自由ならば
重子音の「أنّ」の発音を軽減した「أن」(通称「أن
المخفّفة」)
これは文中で格を持たない「أن(’an)」で、本来は重子音の「أنّ(’anna)」が来る部分に置かれます。子音を重ねた「nn」の部分が単に「n」となることから、名称に「軽減された」という表現が使われています。
「知る(علم)」といった動詞の後に来る場合、この軽減された「أن(’an)」が使われるなどします。ここでは、いくつかの例を挙げておくに留めておきたいと思います。
- 動詞「知る(علم)」の後に来て
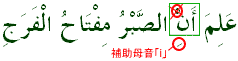
忍耐は救いの鍵であると彼は知った。
動詞「知る(علم)」の後の来る「أنّ」(’anna)の発音が変化。ちなみに、この文では、「أنّه」という形で「أنّ」('anna)についていた「ضمير
الشأن」が省略されたものと説明されます。
- 名詞文を従える「أنّ」(’anna)
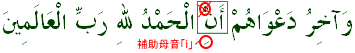
そして祈りの結びは、「万有の主アッラーを讃えます。」である。
[クルアーン第10章「ユーヌス」:第10節]
- 活用しない動詞「ليس」と組み合わせて

人間は、その努力したもの以外、何も得ることは出来ない。
[クルアーン第53章「星」:第39節]
- 未来を示す「س」が接頭した未完了動詞と組み合わせて
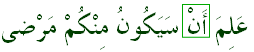
かれは、あなたがたの中病める者のあることを知っておられる。
[クルアーン第73章「衣を纏う者」:第20節]
- 否定詞「لا」と組み合わせて
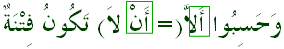
そしてかれらは(そのために)試み(の懲罰)がないものと考えていた。
[クルアーン第5章「食卓」:第71節]
|