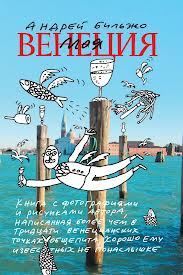フィレンツェからヴェネツィアへと言っても、ヴェネツィアへは実際に行ったわけではない。フィレンツェのアルノ川を眺めながらヴェネツィアに思いを馳せただけだ。
ヴェネツィアと言えば、もちろんロシア出身の詩人ヨシフ・ブロツキーを思い出さずにはいられない。
日本に戻り、ブロツキー 『ヴェネツィア―水の迷宮の夢』 金関寿夫訳(集英社、1996)を書庫から出してくる。英語で書かれた詩のような散文作品だ。
少し引用しよう。
もしもいつかぼくの住む帝国の支配から逃れることができたなら、もしもいつかバルト海からこのウナギがなんとか抜けだすことができたなら、なにはさておき、まずヴェネツィアへ赴き、ボートが通る度にしぶきが窓にかかるような館(パラッツォ)の一階に部屋を借りて、しめった石の床でたばこを揉み消し、書くのはエレジー二、三篇。咳をし、酒を飲む。
友だちに貸してもらったレニエの小説(ミハイル・クズミンが訳したという!)の舞台がヴェネツィアだったのが、この町への憧憬のきっかけだったという。
夕暮れになると、どんな町でも美しく見えるものだ。しかし、なかには、他所と比べてとり分け美しくなる町がある。(...)通りはすでに闇につつまれていても、河岸はまだ日中。巨大な水の鏡には、「まるでばらまかれた古靴のような」モーターボート、水上バス、ゴンドラ、遊覧用小舟、荷船などが、水に映ったバロックやゴシックのファサードを飽きずにふみつけている。
ヴェネツィア全体が「巨大な水の鏡」なのだ。
偶然にも、先日の大学院の授業で読んだのが、アンドレイ・ビリジョーの 「ヴェネツィアの12月」 という短編だった(学期の初めに割り振ったのにすっかり忘れていた)。さらなる驚きだったのは、ビリジョーのこのエッセイ風の作品にちゃんとブロツキーが登場していたこと、そして「アックア・アルタ(満潮)」で町が浸水し、文字通り、町全体が緑色の「水の鏡」と化すさまが描かれていたこと。
ビリジョーもヴェネツィアが好きでよく訪ねているらしい。ユーモアもあり、思索的でもあり、読みやすくて面白い作品だった。
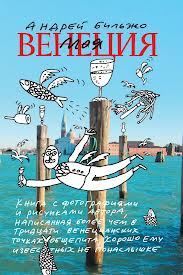
↑
ちなみに、この短編を含む作品集が出ている。
アンドレイ・ビリジョー 『私のヴェネツィア』 (モスクワ:「新文学展望」社、2013)
ビリジョーは、いわゆる風刺漫画家でもあり、同時に 「ペトローヴィチ」というコンセプチュアル・レストランのオーナーでもある。
「ペトローヴィチ」には、何年か前アクーニンに連れていったもらったことがあるが、1960-70年代のレトロな雰囲気を再現した店内は、まるでタイムマシンで「ソ連」時代に迷いこんだかのようだった。