"侵略"と結び付け 史実に反す近現代史も
来春から使われる小学校と高校(主に3年)の教科書の検定結果が二十四日、文部省から公表された。国旗・国歌の法制化が論議されるなか、小学校社会科(五社)では、日の丸・君が代を"侵略"と結び付けるなど国旗・国歌に否定的な記述が検定合格となった。近現代史などをめぐっても、史実に反した記述が検定をパスした。(2面に「主張」、26、27面に関連記事)
平成四年度から実施された現行の小学校学習指導要領は「わが国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てる」と明記している。
今回の検定では大阪書籍の4年下と6年下、教育出版の6年下に「学習指導要領の内容の取り扱いに照らして記述が不十分」との検定意見が付き、両社が記述を改めたが、検定後も不十分な記述が残った。
教育出版は現行教科書で「わたしたちは、自国はもちろんのこと、他国の国旗・国歌を十分に尊重していく態度が必要です」としていたが、今回は「世界の国々では、自国はもちろんのこと、他国の国旗・国歌も、たがいに尊重しあい、敬意をはらってあつかうようにしています」と変更した。
さらに「しかし、他の国から侵略を受けたり、支配された歴史をもつ国や地域では、それらの国の国旗・国歌に対して、素直には尊重できない感情をもつ人々もいます」と、否定的な内容を付け加えた記述が検定をパスした。
大阪書籍は現行教科書にない「戦争の被害を受けたアジアの人々の気持ちも、たいせつにしないといけないね」との一節が加わり、「戦争のときにも、日の丸がたくさん使われたね」と日の丸を先の大戦の象徴と印象づける表現がみられた。東京書籍も現行教科書と同じ「侵略されたり、被害を受けたりした国々の人々には、侵略した国の国旗や国歌を、すなおに尊重できない感情が残ります」との記述が残った。
教育出版、大阪書籍、東京書籍、日本文教出版は、日の丸の出来を説明し、国旗として「あつかわれるように」なったと記述したが、君が代の出来を書いた教科書は一冊もなかった。
近現代史では「慰安婦の強制連行」を示唆する記述などに検定意見がつき、書き直されたが、南京事件などで史実に反する記述が検定を通過した。
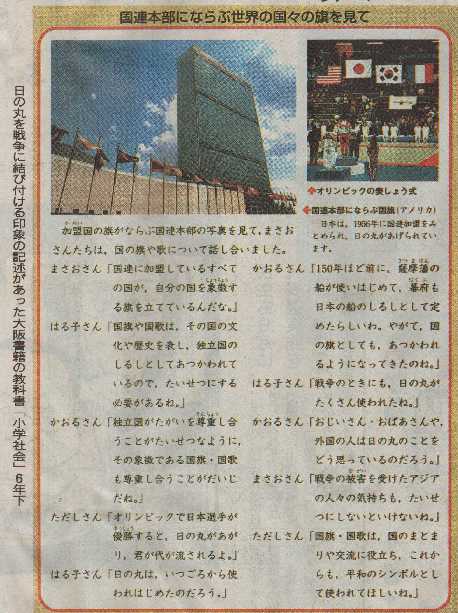
今回検定申請したのは小学校が百八十九点で、すべて合格。高校は百十点中、実教出版の「数学C」と秀文出版の「リーディング」が不合格となった。
[視点] 検定制度の限界示す 今回検定を合格した小学校社会科教科書で日本の国旗が日の丸だとストレートに記述しているのは、日本文教出版(4年下)の「日本の国旗は、日の丸です」だけだった。国歌については一冊もない。
「外国から国の代表がおとずれると歓避式が持たれ、国旗がかかげられて、国歌が演秦されます。会場では、ボルトガルの国旗と日の丸がかかげられ、ポルトガル国歌と君が代が演奏されました」 (東京書籍6年下の写真説明文)などと遠回しな表現が目立つ。「どうしても、日の丸・君が代を国旗,国歌と認めたくない」という執筆者の抵抗が伝わってくる。今回、検定意見の通知後に教科書調査官が編集者に対し、「自国の国旗・国歌を尊重する表現を入れてほしい」と検定外の「参考意見」を伝えた。
その結果、記述が変わったことを一部メディアが批判しているが、検定が一定の偏向抑止力を維持するためにはやむを得ない措置だといえる。
それでもなお、国旗・国歌を否定的にとらえる教科書が「文部省検定済み教科書」として子供たちの手に渡ることになった事実は、個々の記述を部分的に書き直させるだけで教科書を貫くイデオロギーまでは是正することができない現行校定制度の限界を象徴的に示したといえるだろう。(渡辺浩)
教科書検定
小中高校で使う教科書の合否を判定する制度。文部省は、教科書出版社が提出する「申請本」の内容が学習指導要領に即しているかを教科用図書検定調査審議会に諮って審査し、不適切とした場合、検定意見を通知する。検定意見は記述の修正を義務付け、出版社が修正部分を再提出して合否が決まる。検定サイクルは4年。小中学校では平成14年度から新学習指導要領を実施するため、今回検定の小学校教科書は来春から2年間だけの使用となる。