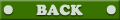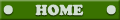山口裕之 「ベンヤミンのメディア論的思考とハイパーテクスト」
日本独文学会 秋季研究発表会 2000年10月8日(日)南山大学 シンポジウムⅣ
(ハンドアウト2)
テーゼ
- ベンヤミンのメディアをめぐる言説は〈言語的メディア〉と〈画像的メディア〉の二つの系列において展開され、この二つの系列は発展史、構造性、神学的コンテクストにおいて基本的にパラレルな対応関係にある。
- メディアの技術的展開にともなってこの二つのメディア系列は一元化に向かう。
- メディアの展開にともなって、技術性がより高められた段階のメディアのインターフェースは前のメディアのインターフェースを内容として包摂する。(McLuhan,
Grassmuck) それとともに原初的な段階でメディアが関わっていた魔術性・宗教性は、メディアの展開にともなって包摂されるメディアが層を成して介在していくことにより、展開していく技術メディアからますます疎外(世俗化)されていく。
- 〈言語的メディア〉がその優先的な機能である「知」の伝達・保存の媒体として展開していったのに対して、〈画像的メディア〉の系列において「画像」は「芸術作品」として「美」の領域にのみその展開の場が長く限定された。ベンヤミンが〈画像的メディア〉のうち関心を向ける写真や映画は、「アウラ」を失うことによって「美」の領域から解放され、「メディア」として機能することが可能となった画像メディアである。
- 写真、映画、新聞における「技術的複製可能性」によってアウラが消滅し、それによって可能となる断片の引用=モンタージュによるモザイク像において、画像メディアの系列と言語メディアの系列が接合する。その接合に際しては、とりわけ言語メディアの画像化が認められる。(文字の持つ画像的特質の自立化、文字の引用によるモザイク像の形成)
- 二つのメディア系列の一元化を、ベンヤミンは「あらゆる生活諸関係の文書化」(『写真小史』、『生産者としての作家』)と言い表している。しかし、これは画像をも「文字/書物」へと一元化することを目指す(「彼のメディア美学における分析上の限界」(Bolz))ものというよりも、文字的・画像的情報の断片によるモザイク的な像を目指すもの。
- ある新しい技術メディアは、当初からその新たな技術段階がもつ本来的な特性にしたがって用いられるわけではなく、むしろ旧来のメディアをそのうちに包摂するがゆえに、はじめは旧来のメディアの特性にかなり支配されながら用いられ、次第にメディアのもつ本来的な特性に従った用いられ方に移行していく。
- 〈言語的メディア〉と〈画像的メディア〉のモザイク的一元化というベンヤミンのメディアをめぐる思考は、単にベンヤミンの思想全体の枠組みにとって重要であるばかりでなく、メディア理論一般にとって基本的な理論モデルを提供する(マクルーハンやオングの図式の修正的モデルとして)。
- いままでのハイパーテクストに対する理解の修正――旧来の「テクスト」を技術的に整理し活用するためのメディア(Bush,
Nelson)→断片としての「テクスト」が作り出すモザイク像、テクスト的なものではなく画像的特質を持つものとしての「ハイパーテクスト」