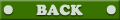1998年度 インターネット講座
メディア・情報・身体 ―― メディア論の射程
第2回・第3回講義
マクルーハンのテーゼの論点
資料08
メディア・文化・認識の形態と社会のあらゆる側面との相関関係
- 「メディアはメッセージである」(『メディア論』「メディアはメッセージである」pp.7)
- 「「メディアはメッセージ」の定理は四つの観点から見られる。そのうち三番目のが重要な意味を持つ。
第一の意味は「メディアはメッセージ」と口で言うほうが意味がよく伝えられる。メディアこそ調査すべきであり、メディアこそ人々が忘れているものだ、ということである。
人々はみな内容にひっかかっている。しかし、形式、構造、フレーム、すなわちメディアに注意を払え、ということ。(...)
第二の意味は、メディアと内容の関係を強調したものである。
コミュニケーションの形式は内容を変えるだけでなく、それぞれの形式はまた特定の種類のメッセージに適している。内容はいつも何らかの形式の中に存在し、したがってある程度までその形式の力学によって支配される。(...)
人々に伝えられるものはいつも"形式の中の内容"である。この意味で、メディアは共同メッセージである。
第三の意味は、メディアと人々の心との関係を強調したものである。メディアはそれを使う人間の知覚習慣を変える。内容と関わりなく、メディア自体が中に入ってゆく。(...)
マクルーハンは「メッセージ」をもじって「マッサージ」とも言った。(...)
事実、メディアは人々をつかみ、揺すぶり、転がしまわし、マッサージする。(...)
第四の意味はメディアと社会の関係を取り上げる。(...)
メディアは人間だけでなく社会もマッサージする。」(ジョン・M・カルキン「マクルーハン理論とは何か」、『マクルーハン理論』p.5-7)
- 「ラジオのこうした影響を理解するためには、文字文化は単に印刷技術であるにとどまらず、生産や市場の全過程を合理化するのに適用され、さらには法律、教育、都市計画にすらおよんでいることを認識する必要がある。印刷技術に由来する連続性、画一性、反復性の諸原理は、イギリスやアメリカでは長い間共同生活のあらゆる側面に浸透してきた。こうした社会では子どもは文字文化を交通や街路から、あらゆる自動車、玩具、衣服から学びとる。読み書きの学習は、連続性と画一性をもった英語圏の環境では文字文化の些細な一面にすぎない。識字能力のみを重要視するのは、やがては仕事と空間の視覚的組織化にいきつく企画化の過程をこれから始めようとしている社会のきわだった特徴である。人間の内的性格が文字文化によって変容を受けて、分節化した視覚によってすべてを捉えるような心理的変化が生じない限り、ものやサービスの連続的な変化の流れを確実に生み出す経済的な「離陸」すなわち飛躍は起こりえない。」(『メディア論』「ラジオ」p.311-312)