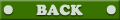1998年度 インターネット講座
メディア・情報・身体 ―― メディア論の射程
第2回・第3回講義
マクルーハンのテーゼの論点
資料07
新しい環境における旧来のシステムに対する批判
- 文学や哲学の研究者鳩もするとほんの「内容」だけを問題にしてその形式についてはとかく無視しがちである。そしてこの傾向は表音文字文化に特徴的なものである。というのは表音文字の視覚的部分そのものは意味を持たず、「内容」すなわち読書する人の頭のなかで再構成される話の中にのみ意味があるからだ。」『グーテンベルクの銀河系』p.122
- 「つまり科学においては諸感覚の分離として始まったものが、芸術が科学に対抗する根拠の全てとなったのだ。芸術家は、諸感覚どうしを切り離し、やみくもに単純化の道を進むことで狂気を求めていた世界の中で、綜合的なるもの、感覚の相互作用を保ち続けるのみならず、再び取り戻そうと懸命であった。」『グーテンベルクの銀河系』p.277
- 「機械の時代はいま後退しつつあるが、その時代には関心をもちすぎるということもなく行動をとることができた。動きが鈍かったから、反応はかなりの時間にわたって遅らされることが保証されていた。現在では行為と反応がほとんど同時に起こる。いわば、われわれは現実に神経的で統合的な生き方をしている。にもかかわらず、われわれは前電気時代の古い細分化された空間と時間のパターンであい変わらず考えているのである。」(『メディア論』p.4)
- 「電気時代の内爆発状態に立ち入ると、思考と感情の分裂は学校や大学における知識の専門部門別と同じように異様なものとうつるようになってきた。けれども、思考と勘定を分離する力、反応することなしに行動する力、これこそが、個人および社会生活において緊密な家族の絆をもった部族の世界から文字文化人を分離させたものであった。」(『メディア論』「印刷されたことば」p.176)
- 「新しいメディアは古いメディアに何かを付け加えるというものではない。また、古いメディアを平穏に放っておきもしない。それが古いメディアに変わって新しい形態と地位を見いだすまで、古いメディアを圧迫することを止めない。写本文化は教育において口誦の方式を維持していた。それが高水準の「スコラ哲学」と呼ばれるものであった。けれども、印刷が同一のテクストを任意の数の学生や読者の前に置くことによって、口頭の討論によるスコラ体制はあっという間に終わってしまった。」(『メディア論』「印刷されたことば」p.177)
- 「教育の分野では、カリキュラムを寡黙に分割する従来のやり方は、中世の三学[文法・修辞・論理]や四科[算術・幾何・音楽・天文]がルネッサンス語にたどった運命と同様に、すでに時代遅れのものとなっている。どんな科目でも、深いところでとらえれば、ただちに他の科目と関連してくる。」(『メディア論』「オートメーション」p.364)
- 「今日、アメリカは世界最大の旧テクノロジーの退蔵物の山をかかえている。印刷物と印刷物からとった方法によって築かれた教育機構、産業機構は巨大であり、いたるところにはびこっている。未開発国のほうがアメリカに比べうんと都合がよい。現在、未開発国はかつてアメリカが印刷テクノロジーを迎えたと同じように、電子テクノロジーを迎えている。私たちはこの旧時代の遺産を頭からぬぐい去るための計画、そのためにできることをまだ手がけていない。」(マクルーハン「メディアの文法」、『マクルーハン理論』p.22-23)