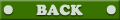1998年度 インターネット講座
メディア・情報・身体 ―― メディア論の射程
第2回・第3回講義
マクルーハンのテーゼの論点
資料05
電子メディア文化における感性・認識の新たな段階
- 「われわれの感覚および神経を地球規模に拡張する現代の電気技術は、言語の未来に大きな意味を持っている。電気技術が言葉を必要としないことは、デジタル・コンピューターが数字を必要としないのと同じである。電気は、意識そのもののプロセスを世界規模で、しかも、言語化に頼ることなしに、拡張する方法を示している。このような集合的意識の状態は人間の言語以前の状況であったかもしれない。言語は人間拡張の技術であり、言語がものを分割分離する力をもつことはよく知られている。その言語は人間がそれを用いて最高の展開にまで達しようとした「バベルの塔」であったかもしれない。」(『メディア論』「話される言葉」p.82)
- 「アルファベット(およびその拡張である活字)が知識という力を拡張させることを可能にし、部族人の絆を壊滅させた。かくして、部族人の社会を外爆発させて、ばらばらの個人の集合としてしまった。電気による書字と速度は、瞬間的かつ持続的に、個人の上に他のすべての人の関心を注ぐ。こうして、個人は再び部族人となる。人間種族全体がもう一度、一つの部族となる。」(『メディア論』「印刷されたことば」p.174-75)
- 「すでに何世紀にもわたって、活版印刷が線状的画一性と断片化された反復可能性というパターンを条件づけてきているが、このパターンは、エレクトロニクスの時代になって、芸術の世界からだんだん批判の目を向けられはじめている。線状的過程は、経営や生産の部門だけでなく、娯楽の部門においても、産業界から排除されはじめている。グーテンベルクがもたらしたこの構造的前提に取って代わったのは、テレビ映像の新しいモザイク的形態だ。」(『メディア論』「広告」p.235)
- 「広告の無意識的な深層のメッセージには、文字文化型人間の攻撃はかすり傷一つ負わすことができない。文字文化型人間には、非言語的形態の仕組みや意味を認識する、あるいは議論する能力が欠けているからである。絵を考察の対象とする能力はないのだ。」(『メディア論』「広告」p.236)
- 「蓄音機の流行という直接的な現象の背後には、電気メディア全般にわたる内爆発があって、そのせいで音楽や詩のみならず舞踏においても、実際の話し言葉のリズムが強調され重要視されていたことを忘れるわけにいかない。」(『メディア論』「蓄音機」p.284)
- 「蓄音機と歌や踊りとの絆の深さは、以前に蓄音機が電信や電話と結んでいた関係の深さに優るとも劣らない。一六世紀に初めて楽譜が印刷されて以来、ことばと音楽は分離することになった。声と楽器がそれぞれに名技性を発揮するのが、一八世紀、一九世紀の音楽の大発展の基盤となったのである。これと同じ断片化と専門分化が芸術と科学の両分野において行われてはじめて、産業、軍事組織、さらには新聞や交響楽団のような巨大な共同組織において、マンモスのような途方もないせいかが生み出されたのであった。」(『メディア論』「蓄音機」p.289)
- 「(形態としての映画は、活字印刷による断片化がもつ偉大な潜在力の最終的な成就であった。)しかしいまや、電気が引き起こす内爆発が、断片化による拡大の過程全体を逆転するにいたった。電気は、内爆発、均衡、静止を特色とする冷たいモザイクの世界を復帰させたのである。」(『メディア論』「映画」p.304)
- 「テレビ映像の様式には、映画や写真とはまったく共通点がない。ただ一つの例外は、テレビ映像も、非言語的な「形態Gestalt」すなわち形あるものの姿勢を示すという点だけである。(...)
(映画においては)観客は映像全体を一括取引として引き受ける傾向がある。これとは対照的に、テレビ・モザイクの視聴者は、映像に技法情の制約があるため、無意識のうちに点をスーラやルオーのパターンに基づく一種の抽象芸術作品に再構成する。(...)
テレビの映像は、いまは、明るい点とくらい点のモザイク状の網の目であって、映画のショットは、たとえ映像の質がきわめて低い場合でも、決してモザイク状の網の目にはならない。」(『メディア論』「テレビ」p.325-326)
- 「共感覚、すなわち統合的感覚と統合的想像力は、西欧の詩人、画家、ひいては芸術家一般にとって、長い間到達しがたい夢のように思われていた。彼らは、一八世紀以降の西欧の文字文化的人間の想像力が断片化し、不毛化してしまったことを、悲しみと困惑の面もちで見守ってきた。(...)
しかしいまや、テレビやラジオがわれわれの知覚に働きかけることによって、その夢が実現されることになった。われわれの中枢神経組織の大規模な拡張であるこれらのメディアは、西欧の人間を共感覚の活動の中に毎日包み込んでいる。西欧の生活様式は、すでに数世紀前から、感覚を截然と分離し専門分化して、視覚をその中の最上位に据えることによって達成されたものであるが、そのような生活様式は、抽象的に「個人」と呼ばれるこの巨大な視覚的構造物のまわりに押し寄せるラジオやテレビの波に持ちこたえるすべを知らない。」(『メディア論』「テレビ」p.328)
- 「西欧人にとって、すべての分野を包含するような拡張がすでに表音文字によって起こっていた。そしてこの表音文字なるものは、もっぱら視覚の拡張を引き起こす技術である。これとは対照的に、表音文字以外のあらゆる表記形態は、多様な感覚の公共をまだとどめている芸術様式である。表音文字のみが、諸感覚を分離、断片化し、意味の複合体から脱却する力を備えている。テレビ映像は、この文字文化が特色とする、感覚生活の分析的断片化の過程に逆転を起こすものだ。」(『メディア論』「テレビ」p.349)