![]()
神社
現代日本では、神道(Shinto)や仏教(Buddhism)に由来する宗教的な事柄は、信仰に基づくものというより、生活の中に根付いた習慣的な側面が強くなってきました。
神社は神道の神をまつった建物です。日本人は、特に信仰心がなくとも、神社へお願いに行くことがあります。
例えば、赤ちゃんが生まれたときには健やかな成長を願いに、お正月には新しい年が良い年になるよう祈願しに行きます。
また、人生の節目の年齢で厄払いをしてもらいにいくこともあります。
神社は日本人にとって縁の深い場所になっています。
神社の入口には、人間の世界と神の世界の境界を示す鳥居があり、神をまつった本殿(神殿)といくつかの付属の施設から成っています。
 |
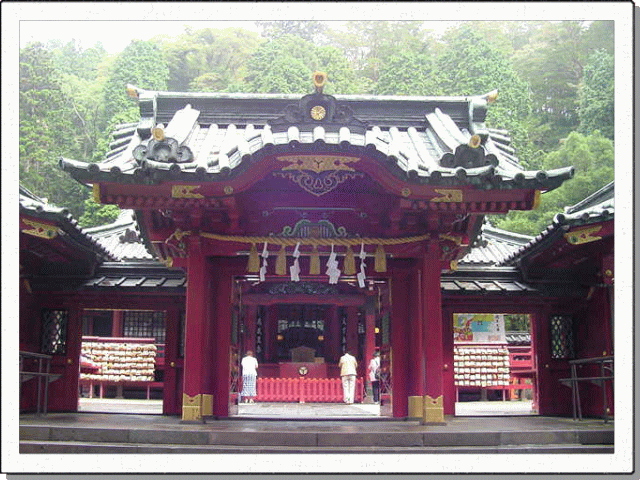 |
|
| 大鳥居と芦ノ湖 | 神門(神社への入り口) |
おみくじ
神社やお寺では、おみくじという、運勢を占う「くじ」を売っています。
紙に、運勢が書いてあります。
神社では「神」に関係があるものなので「御神籤(おみくじ)」と言います。
神社の宗派によって細かい点が異なるため、おみくじに関する知識は、日本人でも正確に知らない場合があります。
 |
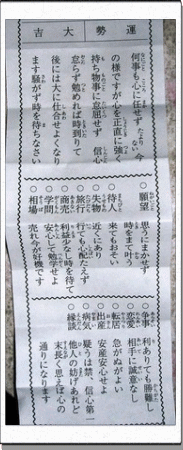 |
| 開ける前のおみくじ | 開けた後のおみくじ |
おみくじは「引く」といいます。おみくじを引く方法はいくつかありますが、次のようなものが代表的です。
① 細い棒の入った箱を両手で抱えて振り、逆さまにして、小さな穴から棒を一本だし、そこに書かれている番号の紙を受け取る。
② 紙が入った箱の中から、参詣者が紙を選ぶ。
③
自動販売機から出てくる。
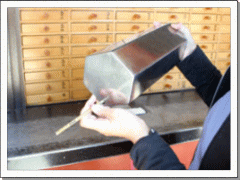 |
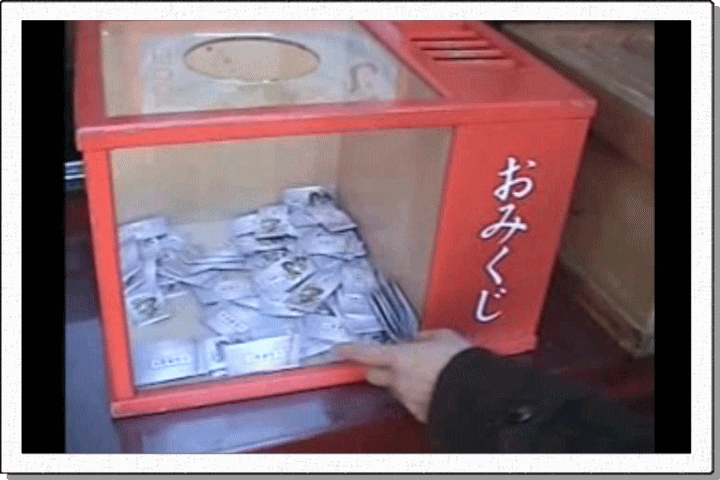 |
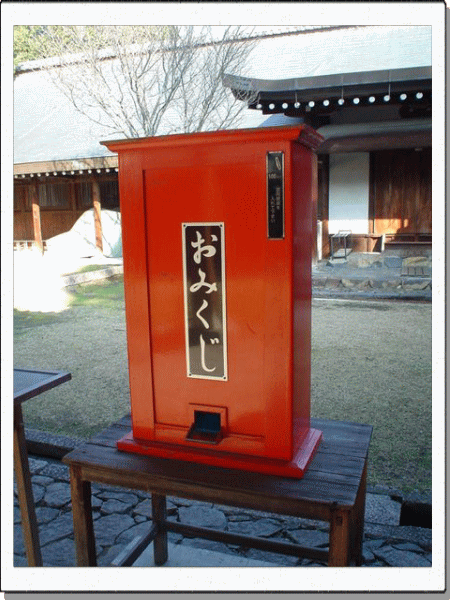 |
||
| ①細い棒が入っている六角形の箱 | ②直接手でとる箱 | ③自動販売機 |
紙には、一番上に、全体の運勢を現すものとして「大吉・吉・中吉・小吉・凶・大凶」といった言葉が記されています。運勢の区分は神社の宗派によって異なる場合があり、多いところでは12区分にも分けています。そのほか、探し物・待ち人・健康・金運・生活についてなど、個別の運勢が短い文章で書かれています。
引いた後のおみくじをどうするかについては、考え方が2つあります。
・ おみくじには神や仏からのメッセージなので、吉凶にかかわらず、身につけて持ち歩く。後にお礼を込めて神社に納める。
・ 自分にとって都合の悪いおみくじは神社の中に結びつけ、置いていく。良いおみくじは持ち帰り、後日神社の中に結ぶ。
神社の中の木などに結ぶ習慣が一般的です。最近は、木に結ぶと木の生育が悪くなるため、おみくじを結ぶための場所を用意している寺社が多いようです。
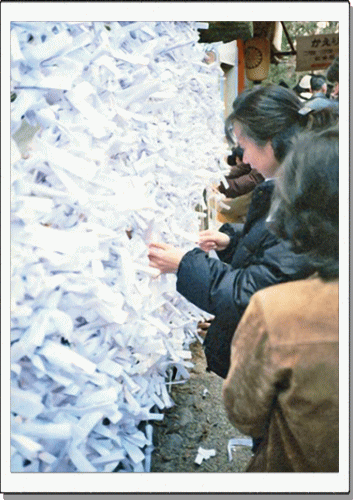 |
 |
|
| おみくじを結ぶ人たち | 梅の木に結ばれたおみくじ |