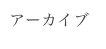慟哭のエレニー − − アンゲロプロスのギリシア
UP 8月号(東大出版会)pp.57〜61
慟哭のエレニー − − アンゲロプロスのギリシア
UP 8月号(東大出版会)pp.57〜61



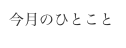

黄泉の国の難民
「エレニ」という名は、英語ではヘレン、フランス語ならエレーヌに対応するごくふつうの女性名だ。だが、ことがギリシアとなるとこの名前は過重な負荷を帯びてくる。そもそもギリシアの正式な国名がエレ[リ]ニキ・デモクラティアという。日本ではラテン語由来の呼称にしたがって「ギリシア」と呼び習わしているが、かつてヘラスと称していたこの地は今でも「エレニの国」なのだ。
ヘラスは古代の栄光の時代を開いた後、およそ二〇〇〇年にわたって歴史から消えていた。アレキサンダー大王によって東方ヘレニズム世界に拡散され、ついでローマ帝国に呑みこまれ、その分裂後はビザンツ帝国の正教的風土のふところに溶け込むが、一六世紀半ばからは異教徒オスマン・トルコの支配するところとなった。その消滅したヘラスが再びヨーロッパ周辺の地政図に浮上するのは一九世紀になってからのことだ。
もともとヨーロッパの近代は「ギリシアの再発見」とともに始まった。近代の世界がキリスト教的世界観からの脱却と軌を一にして開かれたとするなら、それはこの「再発見」をバネにしたヨーロッパの「再ギリシア化」という側面をもっていた。哲学や科学の思考はギリシアをその起源とみなし、近代の政治(デモクラシー)や文化(ヒューマニズム)もつねに古代ギリシアを参照項としてきた。とりわけドイツで際立った哲学は、ヘーゲルやニーチェからハイデガーにいたるまで「ギリシア回帰」の度を強めてきたし、つい最近のフランスのフーコーでさえ、「われわれは日々ギリシア人に戻りつつある」と書いていた。ジョージ・スタイナーの『アンチゴネーの変貌』の記述を待つまでもなく、世俗の合理主義を志向する近代の思想は、「フィルヘレニズム(親ギリシア主義)」の磁場に導かれてきたといってもよい。
ギリシア(ラテン経由のヘラス)とは、近代ヨーロッパにとって「理想自我」ともいえるものだった。ところが一九世紀には、ギリシアは現実のどこにも存在せず、理想はあくまで理想でしかなく、またそれゆえにヨーロッパに漂う古代への憧憬は、ギリシア移民たちの間に一種独特のナショナリズム(フィルヘレニズム)を生み出すことになった。それがやがて、各地に散る移民たちを動かして、二千年の時の彼方の「黄泉の国」をヨーロッパの地図上に復興することになったのである。
こうして、他者たちの普遍的モデルの夢と、過去の栄光のあまりに疎遠な記憶、そして近代国家への熱情が、バルカン半島におけるトルコ支配への抵抗のうえに多重露光されて、近代ギリシア国家は生れた。あまりに長いオデュッセウスの旅と言えなくもないが、国王をドイツ(バイエルン)から迎えるという事態が象徴するように、「帰還する移民」は不安定で輪郭の定まらないこの国のその後と切り離せず、二〇世紀になるといっそう多くの移民たちが、新たに敷かれた国境線を越えて、多難な移動を強いられることになった。
古代の夢幻の地に近代のネーション観念を投影して作られた国、難民たちが辿りつき投錨するギリシア。そこには遺跡以外の古代ギリシアはなく、一歩踏み込めば、カコヤニスの映画『その男ゾルバ』に描かれるような因習の根づく風土がある。流浪のユダヤ人は二千年間聖書を住処とし出自を守ってきたが、ギリシア人は時を越えてどこに蘇るのか。テオ・アンゲロプロスの映画を観ると、悲劇のうちに、と言いたい思いにかられる。だだ、かつて神々の力を背景に生きられた悲劇は、ギリシア現代史の混迷する政治的状況のなかで、神々なき世界の受苦のドラマとして反復される。
獣の慟哭
アンゲロプロスの最新作『エレニの旅』(邦題)は、スクリーンを舞台にしてイメージで演じ上げられるみごとな現代の悲劇である。舞台はまさにコロスの一団のような、オデッサから帰還した難民たちの登場から始まる。中央に立ち、彼らの来歴、スクリーンの外で起こったロシア革命の動乱や脱出の旅を、観客に向かって告げるのは家長のスピロスだ。そのかたわらに拾われた孤児エレニがおり、その幼い手が家長の息子アレクシスの手を求めている。この四角いスクリーンが悲劇の舞台だ。主人公たちを翻弄する禍々しい諸力はスクリーンの外で荒れ狂い、スクリーン上の私的な生の舞台に生きる主人公たちの身の上に、過酷な運命の糸を引く。
エレニはアレクシスと幼い恋をし、密かに双子の子を産む。成長したエレニを後妻にしようとするスピロスの前から若い二人は出奔し、バイオリン弾きのニコスに助けられてテサロニキに隠れ住む。スピロスの影を逃れながら、やがて二人は里子に出した子どもたちを引き取るが、その頃から周囲の気配は不穏になる。頓死したスピロスを故郷の村ニューオデッサに葬る二人を、故人への恨みから住人たちは手荒にもてなす。そしてその夜、洪水で村は水没し、帰るところのなくなった二人はテサロニキの仮住まいに戻る。出口のない暮らしから、アレクシスはわずかなチャンスにかけて「幻の楽土」アメリカへと旅立つが、その直後エレニは民主派のニコスを匿った罪で投獄されてしまう。子どもたちとの有無を言わさぬ別離。そして戦争。獄舎さえ流浪し、数年後、釈放されたエレニを待っていたのは、アレクシスが米兵としてオキナワで戦死したという知らせだった。畳みかけるように、政府軍兵士ヤニスの戦死の報。そしてかつての村人の導きでエレニが見出すのは、内戦でヤニスと敵味方に分かれて戦ったもうひとりの息子ヨルゴスの遺骸だった。
安住の地をもたない難民、そのなかでも寄る辺ない孤児、それも女性、「エレニ」という名をもつのはそういう人物だ。難民であるということは、すでにして締め出されていることであり、権力と暴力の鬩ぎあいのなかに、いかなる保護もなく裸でさらされている。そのうえ女性はバーネラブルだ。
そんな少女を、育てた男は妻にしようとするが、息子がそれをはばむ。アレクシスの愛だけがエレニにとってただひとつの寄る辺だ。けれども二人に安住の地はなく、引き取った子供を育てる暇もなく、夫とは生き別れ、自分は獄舎に繋がれて、親なくして成長した子どもたちは、内戦のなかで敵味方に分かれ二人とも死んでしまう。エレニに何が残されるのか。もはやどこに身を置けばいいのか。村を沈めた洪水のようにせり上がる悲嘆に、「子どもはふたりだったね」といたわりながら問う老婆にも、彼女は理解を拒んで答えるしかない、「何のことですか」と。難民として漂い、漂いながら得たもののすべて、愛する者、思いをつなぐ者のすべてをまた失う。安らぎのない境涯で、これでもか、これでもかと奪われる、無慈悲な剥奪の悲劇だ。
悲劇は死で終るといわれる。たしかにこの映画にもいくつかの死がある。けれども、アンゲロプロスが描き出すのは、むしろ極限まで剥き出しにされた命の孤独だ。人間でなければ味わうこともないだろうが、もはや人間ですらありえない、失うことさえ失うまでにすべてを剥奪された者の底なしの悲嘆。響くのは獣の慟哭だ。
母系の悲劇
人間が人間でなくなるほど剥き出しになること、その「剥き出しの生」をギリシア人の生に関する二つの用語を対比させて、「ビオス」に対する「ゾーエ」に引きつけたのはアガンベンだが、その対比によれば、「ビオス」とは「様式をもつ生」言いかえれば「ポリスにおける生」であり、「ゾーエ」はただ単に生きているという状態を意味するという。「ポリス」の周辺に生きる帰還難民とは、その境界に漂うべく運命づけられた存在だと言うこともできるだろう。
世界が全面的に政治化した二〇世紀の世界では、いたるところで人びとは「剥き出しの生」にさらされた。ナショナリズムの政治があり、革命があり、難民が生み出され、戦争が世界大に広がり、アウシュヴィッツやオキナワやヒロシマの惨劇が現出した。スクリーンのなかには、そのような出来事はまったく登場しない。けれども、このスクリーンは、難民たちの村のほとりに翻る白いシーツのように、この世界に吊られ、その光と影を映しながら吹く風にいつも激しく揺られている。そして「ポリス」の破綻は、スクリーンの世界にもはや生のかたちをとどめない、死の彼方の「ゾーエ」の叫びを迸らせる。
ギリシア悲劇は「運命」の勝利を演出する。一人ひとりの人間がその意志の及ばない力によって打ち砕かれる姿を描き出す。けれども二〇世紀に、人間の抗いがたい力を体現するのは神々ではなく、宗教をも呑みこんで地上で演じられる国家の政治だった。国家は人びとを従属させ、囲い込んで「国民」としたり、あるいは「難民」として追放する。そして過酷な戦争や内戦は、間違いなく「運命」の剥き出しの顔だった。
政治とは「ポリス」に関わることがらである。それは古くから男たちに結びついていた。思い出されるのは、一九世紀にポリス的世界の古層を探ったバッハオーフェンの「母権制」をめぐる議論である。バッハオーフェンは古典ギリシア悲劇の第一の作家アイスキュロスの『オレステイア三部作』の背後に、ポリス的秩序の成立によって封じ込められた「母系支配」の時代を読み取った。『アガメムノン』(これがアンゲロプロスの名を世界に知らしめた『旅芸人の記録』の下敷きだ)から始まるこの物語は、娘を犠牲にしてトロイ戦争に勝利した夫アガメムノンを恨み、愛人とともにこれを殺害したクリュタイムネストラを、息子オレストスが姉エレクトラの助けをえて、父の敵として討ったことを正義とする。これは、それ以前にあった母系制を制した父系の優位の確立を語る物語だというのだ。
父アガメムノンは戦のために娘を犠牲にする。母クリタイムネストラはそれが許せない。しかしそのために父を殺した母を、今度は息子のオレステスが討つ。そのオレステスを追う復讐の女神たちを、女神アテナはなだめ、アポロンに庇護されたオレストスを義とする。近代の世界が手本にしたギリシアとは、男たちが秩序の理念を掲げる「ポリス」の世界、哲学と政治が結託する「ポリス」の世界であり、世俗国家の原理として「市民皆兵」の民主政治を作り出したのも「ポリス」にならってである。そしてその近代ヨーロッパの政治的国民国家をなぞってギリシアは復活する。
父の国(バトリア)は死ねと命じるが、母の国(マトリア)は生んだ者、愛する者に生きよと求める。そして「パトリア」たちの抗争に打ち崩れる「ポリス」の瓦礫のなかに、「ポリス」の秩序によって葬られた「マトリア」が、もはやかたちすらない剥き出しの孤独な命として叫びを上げる。アンゲロプロスはその女性に「エレニ」という名前を与え、「妣の国」のイメージに重ねている。そうして造形された映像は、過度なまでに様式化され、好き勝手に、やりたい放題に作られているかのようだが、その造形と様式過剰は、エレニの慟哭の過剰にほとんど自然なまでにつり合っている。
絶句し、しばし椅子に釘づけになり、一息ついて映画館を出ると、夜の深さがふだんとまったく違う。今どき、誰がこんな映画を見るのか、あるいは作るというのだろうか、そんな的のはずれた疑問が浮かぶ。けれども、映画がひたすら観るという無言の経験のうちに完遂されるとするなら、その映画が観た者を促して語らせる事がらが、映画そのものからずれているのは当然のことだろう。だから、夜のなかを歩み出すとき、人工の光が誘う昼の夢幻が脳裏に広がる。二一世紀が「戦争のトラウマ」という過ぎた世紀の魔を祓い、「文明」を自認する主要国がこぞって戦争を統治の技術に再導入しようとしているとき、誰がこんな重い苦しい映画を見ようとするだろうかと。戦争はいま、世界の経済的な繁栄(市場の再開発)と手を携えて受け入れられ、市場の「安全」と市民の「自由」を守るものとして、公然と推奨されている。そのとき、国家の政治から排除された難民は、獣の慟哭さえ聞き届けられることなくどこかの野辺に果ててゆくか、あるいは「自由」を得るために「帝国」の戦争に志願し、かつてはオキナワ、今はイラクで、見知らぬ地の人びとと殺しあうしかないのである。