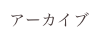《祀られる死と抹消される死》
「腐りゆく戦争」の背景



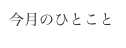
『現代宗教2004』
西洋の暦による時の流れが新しい世紀の敷居をまたぐ頃、近い将来を展望してあちこちで「生命科学の世紀」といった標語が飛び交った。遺伝子研究や医療テクノロジーの長足の発展が、科学による生命現象の全面的な解明や、生命の自在な操作という見果てぬ夢を見させていた。だが、新しい世紀の朝のまどろみは、日常生活の足となった民間航空機が、カッターナイフひとつで乗っ取られて、繁栄を象徴するニューヨークの巨大ビルに突入すると言う、前代未聞の事件によって一挙に破られた。それ以降「文明世界」の人間は「見えない死」に脅やかされ、その死の危険をあらかじめ排除するためとして、膨大な破壊力で死の元凶を追放しようとしている。だが、「文明世界」から死を遠ざけようとするその意志は、それ自体が「文明の外」に引き起こすはるかに多くの死を、同時にその視界から抹消しようとしている。
九・一一という事件はいろいろな意味で世界に重大な変化をもたらした。日本で「同時多発テロ」と呼ばれるこの事件は、何よりまずアメリカにこれまで経験したことのない恐怖(テロル)をもたらした。世界戦争の時代にも一度も爆撃を受けたことがなく、つねに海を超えた他国を戦場として戦い、その圧倒的な軍事力が他を圧してきたアメリカが、初めて衝撃的な攻撃を受けたのである。「安全」神話が崩れ落ちたと言われた。大西洋と太平洋という二つの大洋によって世界の「戦場」から隔てられ、迎撃ミサイル網によって保護されたはずのアメリカで、ニューヨークに聳える巨大な双子のビルが、一瞬のうちに壮大な廃墟と化したのである。そして三〇〇〇人近い犠牲者が出た。
だが「九・一一」という事件は、それ自体がいったいどういう出来事だったのか、まったく明らかにされないまま、さまざまな局面で世界に重大な変化をもたらすことになった。事件の背景は明らかにならない。アメリカ政府は明らかにしようともしない。ただ、「犯人」を名指し、公表できない証拠とやらを同盟国の一部に伝えただけで、ただちに「報復」の軍事行動に出た。
これによって何が変わったのか。
明らかに変わったのは戦争に関する考え方、あるいは戦争のあり方である。戦争は悪であって避けるべきだという二〇世紀の常識は一挙に過去のものとされ、敵が「テロリスト」なら、どんな強引な爆撃も、問答無用の先制攻撃も「正義の戦争」だということになり、「正義」である以上これにはみんなが参加すべきだ、という主張までなされることになった。実際、九・一一以後アメリカ政府が主張した「テロとの戦い」は、曲がりなりにも世界の主要国に認知されて、二一世紀初頭の世界統治を語る枠組みにまでなったのである。二〇〇三年三月の米英軍によるイラク攻撃に最後まで反対したフランスでさえ、「テロとの戦い」には反対していない。これは、アメリカの政権が変わればその方針が変わるだろうといって済ませる話ではない。すでにアフガニスタンでも、イラクでも「戦争」は遂行されたのだ。
冷戦が終結したと言われ、人類は「戦争の二〇世紀」を抜け出て、人間の死への考察は、もっとも先端的には「生命の開発」との関連でテーマ化されることになると予測されていた。けれどもここで一転して、死のテーマは再び衣を変えた戦争の不吉な影に引き寄せられる。というのも、現代の「新しい戦争」は、大量殺戮兵器の疑惑を口実に引き起こされる一方で、冷戦下でできなかった戦争が「できる」ものになったのも、軍事技術の高度なIT化によって、自軍の損傷を極小化して最大の破壊効果を生み出すことが可能になったからである。いずれにしても、そこにある要因は「効果的」な大量殺傷能力ということである。
九・一一がアメリカの「安全」を脅かしたというとき、それはもちろん軍事面だけの安全ではなく、現在のグローバル・システムを成立たせている社会的環境一般の「安全」である。よく指摘されるように、社会がシステム化されればされるほど、システムに起こる事故が多大な支障をきたすようになり、それだけシステムは「安全」上のリスクを抱えることになる。だからシテスムが高度化すればするほど、「事故」の危険は潜在的に大きくなり、政治的「テロ」はそこを攻撃することになる。だが、あらゆる事故を完璧になくすことは不可能だろう。小さな事故がシステム全体に甚大な支障をもたらすとすれば、それはシステムが肥大したからであって、事故を防ぐにはシステムの基本構造を変えなければならないだろう。あるいは、システムが「テロ」を避けがたく誘発するとしたら、やはりそのシステムはおかしいといわざるをえない。ところがアメリカは、九・一一に際してそうは対応せず、圧倒的な軍事力を発動することで、暴力を誘発するシステムを守るという方針を採った。
そのとき、方向を決める転轍機の役割を果たしたのが、死の、あるいは死者の扱い方である。三〇〇〇人の犠牲者が出た。その犠牲者をアメリカ国家は、ただちに国家のための犠牲者として扱った。いや、そこに多くの国籍の人々が含まれていたことを理由に、アメリカ一国を超えたグローバル秩序のための犠牲者、と言ってもよいかもしれないが、アメリカ国家はそのクローバル秩序の盟主を任じているのだから、結局は同じことである。
国家の「ための」犠牲者というとき、実は二つの意味がある。それは国家「ゆえに」犠牲になったということと、国家「のために」命を捧げた、ということである。この場合、ワールド・トレード・センター・ビルが標的になったことに表れているように、グローバル秩序そのものがこのような事件を引き起こす要因になったのだとしたら、三〇〇〇人の死はこの秩序「ゆえの」、あるいは国家「ゆえの」死である。少なくとも、この事件の犠牲者は国家「のため」と思って死んだわけではない。そこには、国家に還元しえない個人の来歴や、さまざまな私的な生があったはずである。ところが犠牲者はただちに国家の祭壇に祭られ、国家による「報復」が居丈高に唱えられた。そしていったん犠牲が国家に回収されるやいなや、それは国家の発動する暴力を正当化する手段になる。
ところがアメリカ国家の発動する暴力は、ビル二つを崩壊されるのとは比較にならない大規模なもので、そこで生み出される犠牲もまた桁が違うほどのものになる。アフガニスタンの人びとは−−いわゆるタリバンの兵士さえ含めて−−、ニューヨークの事件の責任者ではない。にもかかわらず、この機会にアフガニスタンは猛烈な爆撃を受け、アメリカの国防長官の言葉にしたがえば「石器時代に返す」ほどの破壊を受け、それが結局、アメリカの望む政府を作るためのいわば地均しになった。そのうえ、そこで犠牲になった人びとは追悼もされないばかりか、その数を数えられてもいない。そのすべてが、三〇〇〇人の犠牲によって正当化されてきた。
それだけでなく、このときからアメリカの意向に従わないアジアのいくつかの小国は、「危険」をあらかじめ封じるという口実でいつでも潰されることになった。これは誇張でも何でもない。現実にイラクはそのようにして戦争をしかけられ、国家崩壊状態に投げ込まれたのだ。そしてその場合、アメリカの圧倒的な軍事力の行使の前で、あらゆるものが破壊の対象となる。人間も、兵士として動員されていたら問答無用だし、市中で標的といっしょに吹飛ばされても、掃討戦とやらのとばっちりで犠牲になっても、建物や器物の破壊と何ら扱いは変わらない。当然、死者の数など数えられない。アメリカ軍の作り出す戦場では、殲滅すべき「敵」はいても、「人間」など死んではいないのだ。
アメリカ軍は、自軍に犠牲を出さないことを第一の原則にする。というのは、この「民主主義」の匡では、死者が出ると世論が動き、政府の責任が問われて選挙に響くからだ。ベトナム戦争はそのために、つまり世論に負けて敗北したとされている。その「教訓」を汲んで、米軍は自軍に犠牲を出さない攻撃システムや戦術を、最新技術を駆り出して開発してきた。そして今では戦争を、心配なく「できる」ものにした。
けれどももちろん、死者が出ないのはアメリカ軍の側だけである。自軍が攻撃を受けるのを未然に防ぐため、敵のいそうな場所、見つけた敵は徹底的に「無力化」する。そのための爆撃や砲火は強力だから、死骸が残るはずもない。当然ながら「敵」の兵士で生き残るのは難しい。イラク攻撃で、捕縛された捕虜がほとんどいなかったのはそのためだろう。だからラムズフェルド国防長官は言う、「ジュネーヴ条約はもう古い」と。たしかに、この戦争方法なら捕虜への配慮などまったく時代遅れなのだ。
たとえばバグダッド進攻の数日前、イラク兵は千人規模で殺されたが米軍の死者はその日一人と報じられた。そして四月四日までの米軍の死者六七人のうち五四人までが「フレンドリー・ファイヤー」(同士討ち)によるものだったという(一〇日のバグダッド制圧翌日までの死者は一〇一人)。それほど、アメリカ軍は戦闘の死者を出さなかった(必要なのは、味方を撃たない「安全管理」をすることだけだ)。三〇万の兵力によるこれだけの軍事行動で、わずか百人の死者しか出さない国にとっては、三〇〇〇人の死者が膨大な数だということはたしかだろう。
けれども、米軍の砲火や爆撃の向こう側では、兵士と民間人を含めてどれだけの死者が出ているのだろう。アメリカばかりか、世界はそれを数えたことがないし、わずかなNGO(イラク・ボディ・カウント)を除いては、けっして数えようともしない。
要するに、最近の戦争では、綿密に数え上げられて「文明」国家の祭壇に祀られる死者と、回収もされない廃品のように砂漠の埃とともに蹴散らされる無数の死骸があるということだ。その死が違う死だとは思えない。とりわけ、テレビで伝えられたニューヨークのビル倒壊現場から脱出する人びとの姿を見ると、まさにそれはアメリカの作り出すアフガニスタンやイラクの爆撃下の状況を思わせる。
結局、守るべき「安全」の側にいる人間は守られ、そういう人間の一人の死が、「安全」の向こう側の見えない無数の死を正当化する。あるいは、それを正当化するために祀られる。そんなふうに世界は新たに二分され、「文明」の周辺に、その光によって掃討されるべき闇の領域が作り出される。そこは「テロリスト」の跳梁する危険地帯であり、その「危険」はあらゆる手段を講じて封じ込め、できたら完全に抹消しなければならないものとされる。こうして、悼まれる死を期待して生きうる人びとの側と、抹消される死の中にうち棄てられる人びとの側とに、世界は「非対称的戦争」という大量殺戮によって裁断される。
どこまでも死を免れるべき人びとと、咎めを受けることなく殺すことのできる人びと。前者には、高度に発達した医療技術や、自由な市場を介して買うことのできる身体部品すらある。後者には、負傷者に手当てするための薬品もなく、劣化ウラン弾の後遺症に苦しむ子どもを助ける手立てもない。彼らはもともと救うに値しない存在だというかのように。けれども「文明」の世界では、あまりに粗暴なその現実は、そのままには公言できない。だからその不均衡が目立たないように、圧倒的な「非対称性」が当然のこととして受容されるように、許すべからざる「悪」のイメージが作り上げられる。いわく、オサマ・ビンラディン、サダム・フセイン、あるいは金正日と。サダムは世界から除去しなければならない。彼はイラクの暴君であり、世界にとっても危険きわまりない。だからイラクを攻撃する。戦争の目的はイラクをこの暴君から解放することだ。そう言ってアメリカはイラクに戦争をしかけた。
けれども、アメリカ軍の爆撃や「誤爆」で命を落としたイラクの人びとは、どんな罪をアメリカに対してし犯したというのだろうか。そして殲滅して顧みられることのないイラク兵士たちは、フセインの悪行の責めを負わされたというのだろうか。それだけではない。自軍を守ることしかしない占領軍に対して、水や電気にも不自由するイラクの住民が不満の抗議集会をする。するとそこに発砲して死者が出る。だが、その死にアメリカが責任を取ったとは聞かない。死んだのは扇動分子、あるいは「テロリスト」だったと言えばいいのだから。最近、アフガニスタンでも、戦闘ヘリが村の子どもたちを撃ち殺すという事件が報じられた。一度だけではない。タリバン潜伏の情報があったと言えば、それでも米兵は咎められないのだ。そんなことが、戦争が終ったと言われる現在でも続いている。アフガニスタンでもイラクでも、アメリカ軍は咎められずに人を殺すことができる。彼らは「戦場」にいるからだ。そしてそのような常時の戦闘によって、「文明世界」の「安全」が守られ、その「死」が遠ざけられている。
今までアメリカはこういうことを、主として中南米で行なってきたが、それは主としてCIAを通して隠然となされてきた。だが今では、軍隊を使って、ということは召集したアメリカの市民を動員して、公然とやっている。彼らはそれを「文明国家」の市民の任務として遂行しているのだ(ただ、イラクでは米軍兵士の間に異様に自殺者が多いことが問題になり始めている。この圧倒的に強力で「安全」なはずの軍隊の中でなぜ自殺者が出るのか、それは考えてみるに値する)。
もちろん、この事態は日本にもそのまま跳ね返る。というより、日本ではことさらにこの状況を利用して、果たせなかった「夢」を実現しようとする動きがある。日本はひときわ「戦争アレルギー」が強いと言われる。それはこの国が、第二次世界大戦で無条件降伏し、五年間のアメリカ占領統治を受け、「戦争放棄」の憲法のもとで曲がりなりにも半世紀、軍事抗争を免れて経済的な発展を遂げ、その恩恵を十分に受けてきたからだ。それはけっして悪いことではない。だが、以前から軍事力をもつことを主張する勢力もいた。
日本は国際社会で応分の責任を果たせと言う。だが、「国際貢献」と言うなら、軍事力より他にすることは多くある。それに、多くの国が日本に望むことは軍事的貢献などではないだろう。現代において軍事力とは、いずれにしても大量の死と不可分である。
とりわけ冷戦後に、なぜあえて軍事力を前面に出すことが必要なのか。「テロ」や「テロ国家」の脅威があるからか。しかし、たとえば九・一一後、沖縄では最高級の警戒態勢が敷かれ、観光客が一気に引いていったことからも分かるように、「テロの脅威」を呼び込んでいるのは米軍基地である。日本でも「テロ」の危険性があるというが、その危険は日本政府がアメリカに追従し、アメリカの政策に盲目的に追従するからだ。そしてグローバル秩序のなかで、東アジアの国際関係の非軍事的な再構築が必要なときに、冷戦の落し子としての「北朝鮮問題」は、ブッシュ政権が「悪の枢軸」と名指してから一気に危機の様相を呈しはじめた。
結局、アメリカの軍事力と、それを振りかざす政策が、世界に「危機」を引き起こす原因になっている。その「危機」を利用して、日本では「戦争のできる体制」作りが加速している。グローバル化のこの時代に、なぜシステム化する世界を根本から不安定にする危険を冒して、あらためて戦争をしなければならないのか。(背後を見れば、その答えのひとつは簡単である。戦争となれば巨大な軍費がいる。半世紀、武器を作ってこなかった日本は、最新鋭の軍備をそろえるのに、すべてをアメリカの軍需産業に頼らなければならない。巨額の「奉納金」がアメリカに流れることになる。アメリカにとって「日米同盟」とはそのようなものだ。)
現代に想定される「戦争」は、グローバル化の中でさまざまな事情から経済的・社会的発達の「遅れた」弱小国を相手とする戦争である。そういう地域や国が「テロリスト」の温床になり、あるいは独裁者の支配を許しているという口実からだ。そして「民主化」という名のもとに、一方的な破壊と占領が行なわれ、それによって何百万、何千万の人びとが「国家崩壊」状況に投げ出されることになる。それを「解放」と「文明諸国」は言おうとする。
一方で、グローバル秩序の内部では、システムの「安全」のためと称してその構成員のすべてを登録監視するような体制が整えられている。そして異論を立てることは「利敵行為」として封殺される。犠牲者が出たら「国家のため」に死んだ者として、直ちに国家の祭壇(日本では靖国)に祀られる。そして「この犠牲を無にしないために」と、さらに犠牲の予備軍を投入して、戦争への介入を不可逆的に進めてゆく。犠牲は一方で、戦争を後戻りのしにくいプロセスに進ませるための口実に利用されると同時に、見えない「敵」の破壊と殲滅を正当化するために使われる。そして「死」と、それを踏み台にした破壊が国家的に顕揚され、人びとはまたそのために駆り出される。国家は人民のためにあるのではなく、人民は国家のためにこそ一命を捧げるべきであり、そうでない者は(産まない女も含めて!)国家にとっての不良人口でしかない。それは半世紀前の話でもなければ、誇張された悪夢でもなく、すでに現在の日本の政治家によって公言されている言葉なのだ。
「宗教」と呼ばれるものが、「死」に関わり、生きる人びとの「死」への関わりを手当てすることを核心に抱えるものだとすれば、国家はいま、再び「宗教」の務めを横領しようとしている。日本では首相が靖国神社の参拝を繰り返す。それは宗教を重んじるがためではなく、「死」を国家の論理のうちに回収し、宗教そのものを空無化するためである。
二一世紀というのにこのありさまである。よくよく人間とは過去に学ばないものだと言わざるをえない。いま「死」について考えようとするとき、世界規模で広がる「死の二分化」とも言うべきこの歴然たる事実を見つめることを抜きにしては、あらゆる議論は空しいように思われる。