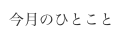琉球烈像 − − 写真で見るオキナワ
(沖縄復帰30周年)
琉球烈像 − − 写真で見るオキナワ
(沖縄復帰30周年)



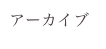

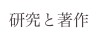


このことに関連して、すでに『新潮』4月号「ウンタマギルーの眉間の槍」を書きました。
東京外語大の大学院専任講座では、昨年二度にわたって「ビデオ上映+パネルディスカッション/沖縄、記憶と映像」を開催し、その成果は上村忠男編『沖縄、記憶と映像』(未来社)の一部として公表されています。今年も、この延長上に秋に再び新たを企画の準備していますが、この企画に沖縄から積極的に協力していただいている仲里効(APO Art Produce Okinawa 代表、『EDGE』編集人)が関わって、このたび那覇市で二つの大きな写真展が開催されました。
ひとつは『東松照明写真展/沖縄まんだら』(浦添美術館)、もうひとつは『フォトネシア/光の記憶・時の果実』展(那覇市民ギャラリー)です。前者は、69年以来沖縄の写真を撮り続けてきた東松照明の30年にわたる写真から300点を選んで、時系列を崩して展示したもの、後者は森山大道、中平卓馬、荒木経惟、石内都ら本土出身の写真家と、比嘉豊光、石川真生、大城弘明、平良孝七ら、沖縄の写真家たちをとりまぜて、沖縄とその島々を撮った作品450点ばかりを一挙に展示したもの。それと並んで、前島アートセンターでは、さらに若い世代の写真家たちの作品が展示され、沖縄はさながら「写真の夏」でした。
この写真展に合わせて、7月6日(土)には浦添美術館わきで二つのシンポジウムも開かれました。まず東松照明の講演があり、それを枕に、まず仲里効の司会で、島尾伸三、石川真生、石内都、比嘉豊光が東松の仕事やそれぞれの写真について語り、ついで港千尋の司会で森山大道、中平卓馬、荒木経惟が沖縄を撮ることについて語りました。短い時間で十分な議論はできませんでしたが、それでもそれぞれの仕事を背景にした濃密な発言が交わされ、梅雨明けで台風の襲来を待つ一夜、暑い夏が演出されました。
(http://www.gosenkobo.net/mac/ivent/ryukyuretsuzo/)
今年は、山形ドキュメンタリー映画祭でも「沖縄特集」が組まれるという。沖縄をめぐる「記憶と映像」のテーマがさらに発展する気配です。
『琉球新報』の求めに応じて、この写真展に書いた記事を以下に掲載します(7月13日土曜日、朝刊)。
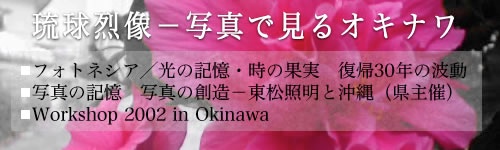
《沖縄二〇〇二年、ひしめく写真の夏》
三つの会場(浦添美術館、那覇市民ギャラリー、前島アートセンター)に八百点を越す写真が集められている。集められたというより、無数の中から選び出された作品群だ。それがところ狭しとひしめきあっている。
「東松照明展」と並行して那覇の二つの会場で開かれた、ヤマトと沖縄の写真家たちの合同展に、仲里効は「フォトネシア」という命名を試みた。島尾敏雄の「ヤポネシア」に借りたこの命名は、二重の意味で沖縄と写真との関係を豊かに喚起する。
「フォト」は「光」、「ネシア」が「島々」だとすれば、陽光にあふれる沖縄はまさに「フォトネシア」なのだが、それだけではない。沖縄は、戦争の爪痕や米軍基地と隣り合わせの生活、それに碧い海や島々の習俗によってヤマトの写真家を惹きつけてきた。それに対抗するようにこの地にも多くの写真家が登場し、島は彼らを促して多種多様なイメージを生み出させてきた。そのために沖縄には「フォト」が繁茂している。
けれども写真が、見る/見られるという関係の上に立ち、そのうえイメージとして消費されるため、写真家たちの営みは「沖縄とヤマト」との抜き差しならぬ関係に絡めとられずにはいない。それに「ショット」といった表現が喚起するように、カメラにはもともと武器のようになところがある。イメージを「盗る」武器だ。
どうしたらそうではない写真が可能か。東松照明を先達とするヤマトの写真家たちにとって、沖縄は魅惑をたたえた「現場」であると同時に、そういう試練の場でもあった。東松は「沖縄を撮る」ことから「沖縄に撮らされる」という境地に転生する。そこで東松は、どんな能動的な意図をも凌駕して迫ってくる、沖縄という時空に身を預けたのだ。東松の沖縄写真集の『太陽の鉛筆』というタイトルは、文字通り「フォトグラフ(光が書く)」の言い換えであり、「写真」のいわば「絶対他力」の境地を言い表している。
ところが、沖縄の作家たちにとっては、撮るのは自分たちの生きている現実である。ただ単に対象を捉えるのではなく、「自分たち」を撮っているのだという意識が、写真をひとつの表出にする。そしてそこに出現するのは、「外」からの眼差しによって消費される沖縄ではなく、ここで生きる日々の持続の中から切り出されるイメージである。それは沖縄が、見られる対象として扱われてきたことへのプロテストにもなる。
そこには超えがたい視線の非対称性がある。沖縄で写真を撮ることを問い直し、沖縄に身を預けて撮り続けた東松は、その非対称性を乗り越えたのではない。そうではなく、とことん引き受けたのである。だから東松は書いた。「しょせん沖縄に対する私の恋は片思い、そして写真はイメージで綴るラブレターである」と(『光る風、沖縄』)。ただしこの「しょせん」は諦めの表現などではない。それでも東松は沖縄を撮り続ける、あるいは撮らされ続けるからだ。そこでは非対称性に身をさらすことが、ひとつの揺るがぬ「関係」となっている。
二つの写真展をめぐって開かれた七月六日のシンポジウムでも、この非対称性が際立っていた。しかしそれを際立たせる場こそ、沖縄とヤマトがもっとも密に接触し交歓する場であるということもまた、会場の熱気は際立たせていた。
そしてこの非対称的な視線のベクトルを帯びたイメージのひしめきの中から、「復帰三〇年」の沖縄が立ち昇ってくる。それはたんに日本に復帰した「沖縄県」ではない。「復帰」にもかかわらず、ヤマトとの差し向いから身を解き放とうとし、小さなシマに凝縮する時空の襞を広げ、さらに「外」へと広がる縺れの中にも身を広げて、その濃密な相をあをらわにする沖縄である。
この三〇年はヤマトと沖縄が非対称性を生きた時代だった。だがその状況も今変わりつつあるようだ。「フォトネシア」展に出品している写真家はほとんどが五〇年台までの生まれだが、前島アートセンターの写真家たちはもっと若い。そして彼らの中には何気なく本土出身者が含まれている。たぶん、ヤマトと沖縄の敷居は徐々にその質を変えようとしているのだろうが、その予兆もまた繁茂する写真のなかに写し出されている。 (西谷 修)