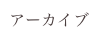空虚に因果の鎖を留める
(「ピエール・ルジャンドルとドグマ人類学」、『現代思想』2003年9月号より)

空虚に因果の鎖を留める
(「ピエール・ルジャンドルとドグマ人類学」、『現代思想』2003年9月号より)



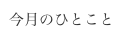
〈構造〉の側からいえばそういうことになるが、一人ひとりの人間の側からすれば、このことは〈生〉を、自分と世界とを納得するということだともいえよう。この「納得」の構造は意識的なものではない。「納得」は無意識のうちに、あるいはまさに裏打ちのない意識として、社会を支える言説との関係で作り出されるのだ。ここで詳述する余裕はないが、このメカニズムをルジャンドルは「ドグマ的組成」と呼ぶ。そこには、言葉と物との結びつき、コミュニケーションの可能性(なぜことばが通じるのか)、根拠と正統性の設定、原因の言説の支え、主体の同一性の設定といった事柄が含まれる。
「なぜ」の問いは因果関係の連鎖を引き起こす。だがその連鎖は無限に繰り延べることはできない。溺れる者がつかむ鎖は、どこかに繋ぎ留められていなければ役に立たないからだ。けれどもどこに? 虚空にである。その先には何もない空虚に因果の鎖を留める術、それが〈ドグマ〉なのである。ルジャンドルはしばしばルネ・マグリットの作品『望遠鏡』を引用する。両開きの窓扉の一方が半ば空いていて、窓越しに見えるはずの空が半開きの窓に貼りついており、隙間からは虚空の闇がのぞいている。窓が閉じていれば、ひとは透明なガラスの向こうに空が広がっていることを疑わないはずだ。だが、この絵のなかで窓ガラスは透明ではない。透明に見えるもの、そしてその向こうに確かな世界を望見させるもの、そしてそれを信じさせるもの、それが〈ドグマ的なもの〉の組立てなのである。
窓はこのようにして、青空を、世界を演出している。〈ドグマ的なもの〉はそのような「見せ」を、演出を必要とする。窓ガラスというスクリーンがなければ、空は映し出せないから。そうして、くつろいだ椅子から窓を眺めるという儀礼によって、世界の確かさという〈ドグマ〉は寿がれるのだ。「くつろいだ椅子から」、そう、この窓に触れてはいけない。窓を開ければ、世界の見かけは乱され、その隙間から虚空をさらけ出してしまうから。
言いかえれば〈ドグマ〉は、裏打ちのなさそのものを、超越的なものとの関係として演出する。それは「なぜ」の問いが汲み尽くされるとき、因果の歯止めとして置かれている。そしてそこには空虚がイメージや言葉の表象をまとい、これ以上は問う必要のない「絶対的準拠」として呈示されているのだ。ひとはその「名において」生き、話す。
けれども〈ドグマ〉は、宗教的なものにだけ関係するのでもないし、実は近代の世俗的な合理性によって放逐されてしまったわけでもない。〈ドグマ〉を追放したとみなす「合理性」そのものがそれ自体ドグマ的に支えられていないわけではないのだ。それに〈ドグマ〉が「なぜ」の問いに答える「理性=理由」の構造に結びついているとするなら、〈ドグマ〉を排除したと思いなす「合理性」とはそれ自体盲目である。すでに述べたように「理性」にはさまざまなヴァージョンがあり、これだけが普遍的で他は迷妄(あるいは仮象)だと主張する「理性」は、いかにもプラトン主義的な、つまりは観念的な、独断だということになる。その意味で西洋的合理主義とは、〈ドグマ〉なしに「合理性」が成立するとするひとつの〈ドグマ〉なのである。それがどのようにして形成されたのかは、キリスト教とローマ法との結びつきや、世俗権力(王権)と教皇権(神権、それ自体が皇帝権をモデルに構想されている)との分離というラテン・カトリックの伝統、そしてそこに発する政治と宗教との分離、とりわけ国家や法治主義の観念を生み出しすもとになった、「西洋における最初の革命」つまり「世界を造り変える」という最初の試みと規定される一一〜一三世紀の「解釈者革命」(注8)の分析を通じて、ルジャンドルが詳細に解明していることでもある。
一般的な例をとれば、個人の「自由」とか「人権」といった観念がある。これは今では「文明化した」ほとんどの社会で、譲ることのできない価値とされ、尊重されるべき理念だとみなされている。だがなぜ「自由」が確保されねばならないのか、なぜある場合には死を賭けてまでそれが求められるのか、と問うと、結局のところは「それがいいから」という以外に根拠はなく、その個人的な欲求が現在では広く社会的に共有されているから「自由」が尊ばれている、というにすぎない。それに、万人に生まれながらに備わっているとされる「人権」についても、だれが人間にそれを保障したのかとなると、「神」でももちださないかぎり、それを根拠づけるものはなにもない。法理論家たちはそれを「自然権」に帰するが、「自然権」自体がそれ以上を問わずにすますために作り出された根拠としての概念なのである。それでもそれが通用してきたのは、それに基づく「人権」という理念が広く社会的に承認され、それを価値づける論理や規範システムができてきたからであり、そうした社会のなかに生きるからこそそれは万人にとって「あるべき権利」とされるのだ。
もちろん、そのような価値を根拠づけるためにさまざまな努力がなされる。「自由」や「人権」は信仰の対象でないどころか、宗教的束縛や不合理から脱却するために、つまりまさしく「自由」になるために構想されたものであり、それを信仰の対象にするわけにはいかない(それでも、カトリック教会の権威を激しく否定したフランス革命が、その絶頂で「理性の祭壇」を作り出したのは意味深い現象だが)。だからこの「自由」を合理的に納得するためにさまざまな理論化が行われるし、その「自由」を基本的な原理として法や制度が組み立てられるようになり、人々の意識もそれに準拠して形成されるようになる。そして「自由」は、個人とか主体とか権利の観念、さらには宗教的な「罪」に代わる社会的な「責任」の観念と組み合わされながら、個々の人間を造形する規範の要になってゆく。要するに、何に保証されているわけでもない「自由」が、そのまわりにそれを〈準拠〉として組み上げるような制度的システムを言説によって組織し、その結果として「自由」は人間の譲れない原則とみなされるようになるのだ。つまり「自由」が原理であることを保証するのは、「自由」それ自体ではなく(「自由」が先験的な価値だからではなく)、「自由」を原理とする制度的システムの総体だということになる。そう言ってよければ、構造が真理を作るということだ。
もう一度言いえば、〈ドグマ〉とは、それ自体が真理として問われることなく、それを〈準拠〉として組織される言説や制度的システムによって、あるいはそのシステムの機能を通して積極的に維持され、そのことによって〈真理〉として機能するものである。たしかにトートロジーにも似ているが、このトートロジーはひとつの命題の上に自分を折り畳んで閉塞してしまうものではなく、そのなかに一社会の制度的システムのすべてを包括している。それを「ドグマ的空間」と呼ぶとしたら、そこには人間の生活=実存の広がりすべてが包括されていることになる。
□〈全能幻想〉と〈限界〉の知
きわめて概括的な例をあげてみたが、「話す種の再生産」のメカニズムは、社会的な広がりをもつ一方で、その核心にきわめて微視的なプロセスを含んでいる。そしてそれはつねに一人ひとりの主体の形成において働いている。なかでも重要なのは、ナルシスとエディプスの二つの神話的形象によって示される主体化の契機である。主体(わたし)が、見知らぬイメージとして自己に出会い、それを自分だと認知することで、世界と自己との分離と内包の関係が構造化されるさまを、オヴィディウスの『変身物語』の語りにしたがってルジャンドルは精緻に分析している(注10)。そこで主体(わたし)をナルシスの狂気から救う、言い換えれば主体に分離をもち込んで理性を刻印するのは、「これがおまえだ」と言う他者のことばであり、それこそがイメージと自己とを分離しながら結びつ〈鏡〉のあり方に他ならず、同時にことばがそこから訪れる〈第三項〉であって、人間にとってはその〈鏡〉が社会なのだということが示される。マグリットの「窓」の絵を思い浮かべてみればわかるように、この〈鏡〉が、つまり透明なスクリーンとして背後の闇を隠して浮かぶイメージはドグマであり、自己と同じであることを認知するという主体アイデンティティそのものが、分離して結びつけるドグマ的構造によって支えられているのである。
また、エディプスの神話は、「話す種の再生産」がのっけから「系譜的秩序」と不可分であることを示している。こどもがことばを発し始めるとき、ことばによる分離はすでに系譜的関係を作る。それが〈父〉による〈母〉からの分離であるにせよないにせよ、乳ならぬことばを与えるもの、名を与えるものは、それだけで〈親〉であるし、いずれにせよあらゆる人間は例外なくまず両性の〈親〉の子供である。そしてフロイトによれば、こどもがことばの秩序に生まれるこのプロセスには、すでに殺人と近親姦との二重の禁止が含まれている。ことばの秩序に参入し、〈肉〉とファンタズムの次元から離脱することは、すでにそのようにして基本的な規範構造を内在化させることなのである。(注11)
その二つの契機が、ひとをことばとイメージに投錨させ、また系譜的秩序に結びつけて、主体のアイデンティティを作り出す。そしてそこにはつねに、「生者を生きさせる」ための「理性原理」が働いている。
* * *
ルジャンドルの仕事は、西洋法制史の研究と精神分析をベースにしている。けれども西洋の規範システムに対して「他者の眼差し」を注ぐという姿勢は、彼のアフリカでの経験に根ざしていると言ってよいだろう。ほとんど哲学者や思想家の仕事を援用することのない彼自身、つねづね「自分の師はアフリカの人たちだ」と語っている。六〇年代の独立直後のアフリカ諸国に国際機関の派遣で何度か出かけたルジャンドルは、そこで新興国の「近代化」のために西洋スタンダードのシステムが次々と処方され、それがただでさえ疲弊したアフリカ諸国の自生的な生のシステムを次々と破壊し、荒廃が生み出されるさまをつぶさに見てきた。とりわけいわゆる「宗教的慣習」の排除が、どんな破壊的な効果をもたらすかを見てきた。その経験が彼に、西洋の合理主義的な産業システムがニュートラルで普遍的なものではなく、西洋キリスト教文化に固有のある種の「宗教的システム」だと考えさせるようになったのだろう。
ルジャンドルは西洋の規範システムをトーテムに対比するが、それは国家と法治主義の結合として構成されるその規範システムが、いわゆる「宗教」と同じ物を扱っているという考えを示している。そして宗教からの離脱をいう「世俗化」さえ、西洋に固有の「宗教的」現象だとみなされる。けれどもそうなるともはやそれは「宗教」のタームでは語れない。"religion"という用語もキリスト教の深い刻印を帯びているが、その用語を継承してあいまいに「宗教」と呼ばれているものも、西洋のいわゆる合理的な規範システムも、実は同じ務めに奉仕している。つまり「生者を制定する」「生を生きうるものにする」という、あらゆる人間社会の万古不易の務めだ。だとしたら、もはや「宗教」のタームで事態を正確に話すことはできない。西洋で「法権利("droit", "Recht")」と呼ばれるものと、「宗教」と呼ばれるものとを、理性原理との関係で、つまりは理性を哲学や科学の普遍から取り戻して、共通に話す知の領野を開かなければならない。〈法〉や〈信〉や〈知〉を貫く構造としての〈ドグマ〉が、キリスト教的近代の重油の沼の中から召喚されるのはそのためである。
ドグマ人類学のこの試みが、世界化の進行する現代の諸社会の知的要請にいかに適ったものであるかについて、もはや多言を要しないだろう。西洋的規範システムは信仰を分離し生の様式を分離してひたすら「価値自由」で機能的になることによって、あらゆる境界を超えて浸透しようとする。諸言語や諸文化の垣根ばかりでなく、正義と計算の境界も、性の境界も、個の境界も、果ては生と死の境界も、誕生と製造の境界をも無化してゆこうとする。あらゆるものがニュートラルな単位に還元され、機械操作可能な情報に一元化され、そのシステムの管理運営だけが社会の課題のようになろうとしている。そしてこの一元化される広大な海のなかでは、「解放」された一人ひとりの「話す動物」が、「規範のセルフサービス」システムにしたがっ、それぞれに「私的」な規範の調理にいそしんでいる。
ひとはこの状況に、「社会的第三項の消滅」とか「規律型権力から管理型権力への移行」といった診断を下す。だが、そこでは「自由」自体が規範として設定されていないわけではないのだ。そしてこのシステムにとっては、円滑な運営が脅かされることが絶対的脅威であり、それゆえ「安全」は徹底的に保障されなければならない。つまりこのニュートラルなシステムの潤滑な運営は、その背後に絶対的暴力を隠しているのである。それは「全能」の暴力であり、無差異の「全能」とは、そこに限界を課すことで人間が人間となる「狂気」の領域である。いま、政治から宗教あるいは科学の領域にいたるまで、「全能」の幻想がはびこっているように見える。限界を知り、区別し、この「狂気」から抜け出る方途を示すこと、それが〈無〉の上に生を構築する人間が、おのれを知る努力としてのドグマ人類学の務めでもある。