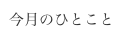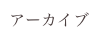黄泉がえる ~ 『島クトゥバで語るいくさ世』に寄せて


今年(二〇〇三年)がテレビ放送開始の五〇年目に当たるということもあって、最近、ときおり戦争期のドキュメンタリー・フィルムを見る機会がある。そのなかには沖縄戦の記録もある。激しい戦闘の繰り広げられる戦場、破壊され尽くした町、火炎放射器で焼かれる森、そして壕の中から襤褸をまとって出てくる住民たち、米兵の差し出す水を無表情にただ全身を震わせながら受けとる子供、そして収容所での生活。たいていは米軍が撮った記録フィルムだが、それによって沖縄戦当時の様子の一端をうかがうことができる。
沖縄戦に関するドキュメンタリーは多くあるが、「琉球弧を記録する会」が製作した『島クトゥバで語る戦世』は、そんななかでもまったく異質の作品である。もちろんそれは出来事そのものの記録ではなく、それを体験した人びとの五〇年後の証言を集めたものである。けれどもまた、単に証言というひとことでは片付かない、別の生々しさをこのドキュメンタリーはもっている。
百人を越える話者たちがいる。たしかに、それぞれの人が体験した沖縄戦の細部が語られる。けれどもそれだけでない。語られることより前にまず映し出されるのは、この人たちが「その後」の半世紀を生きてきた、そしていま生きて語っているというそのことである。沖縄の戦後の半世紀が並大抵の歳月ではなく、それぞれの人にとって日々が生き延びるための格闘のだっただろうことは、想像するに余りある。うれしいとき、うまいものを食べるとき、怪我や病気に倒れて食べ物もないまま死んでいった身近な人たちを思い出す、そういう五〇年がある。家族を失い、友だちを失い、多くの死と島の崩壊を見て、その廃墟を生きてきた、命を抱きあってきた、そういう年月がある。ここで人びとが語りだす〈イクサ世〉は、その五〇年のいのちに洗われている。とはいえまた、淡々と語られてさえ、半世紀前の記憶は生々しい。それはまるで、体を変形するまでに深く刻まれた生傷が、癒えてもなお痛ましい痕をとどめているように、くっきりとした輪郭を浮かべて語りだされるのである。癒えてなお消えることのない深い傷からことばが溢れるようにして、それぞれの人の体験がいま語り出される。このフィルムはそういう〈現在〉のことばと語りのドキュメンタリーである。そしてそれが〈島クトゥバ〉で語られる以外にないというのも当然のことだろう。そのクトゥバは、文字どおりいのちの住処であり、島の人たちがそこに生まれ、それを話すことで人となり、家族やシマの人びとと心を通わせ、それを通して生を編み営んできた、日々のいのちの通い路なのだから。
その人たちが語り出すのは、沖縄戦という出来事の記憶ではなく、かれらが潜り生き延びた〈イクサ世〉の時だ。ここで語りを引き受けている人たちは、アメリカ軍が撮った記録フィルムのなかに、自分や自分の身内を見つけることもあるだろう。あるいは、写っているのが見知らぬ他人であっても、そこにほとんど自分の姿を認めることもあるだろう。あれは自分だ、自分もそうだった、と。けれどもそうした記録に写っているのは、猛烈な戦火で破壊し尽くされた島に生き残った、亡霊かけもののような悲惨な群集でしかない。それは米軍やジャーナリストが撮った無名の人びとであり、取材や記録の対象である。恐怖や警戒心というより、それ以上に、あまりに凄惨な日々を生き延びることで精神を磨耗させ、疲労と飢えでほとんど無表情になって、ただわずかに生理的に震えるだけの、そんな人びとの姿である。
その人びとが、この記録に撮られた日々をどんなふうに生き延びていたのか、あるいは死んでいったのか、公式の記録では表情を閉ざした「もの言わぬ」群集が、その無表情の背後で何を思って生きてきたのか、それをついこの間のことのように語りだす。砲弾で人がバタバタと死に、死に切れない兵隊の首を落として死なせてやったり、膨れ上がった死体も見慣れ、瀕死で飢えと乾きにうめく人びとの傍らも通り過ぎてゆく。それは明日の自分かもしれないと思いながら。「死と隣り合わせ」という表現があるが、むしろ死はあたり一帯を覆っており、いつ自分もそれに呑みこまれるかわからない。そしてもはや生と死とはほとんど区別がなく、境界の敷居はかぎりなく低く、死の恐怖は生の極限的な災厄のなかで摩滅している。ナチス・ドイツのダハウ収容所から生還したダビッド・ルーセは、ほとんど最初のものとなった強制収容所の報告を「われらの死の日々」と題したが、〈イクサ世〉とは、沖縄に生れた人びとが逃れるすべもなく投げ込まれた「われらの死の日々」だともいえる。
細いあぜ道を必死で逃げまどう。踏み外したら死体になる。それに、道はあちこちで寸断されている。そんな「死の日々」がどんなふうだったか、砲弾の雨や機銃掃射のなかをどんなふうに逃げたのか、ガマの中で何が起きていたのか、どんな家族の惨劇や、無残な死の数々を見てきたのか、語る人びとは日付や時刻まで克明に覚えている。けれども、それがいま語りうるものであるためには、ことばもないまま体に深く刻まれた記憶が、五〇年のいのちに洗われる必要があったことだろう。ここにあるのは文字どおり「黄泉がえり」の語りだからである。
後年の証言だけで構成された作品というとC・ランズマンの『ショアー』が思い起こされるが、『島クトゥバ…』はこれともまったく性質の異なるものだ。ここにはいかなる告発の意図も、出来事や犠牲を神聖化する意図もない。たしかに、ひとりのオバアが「そこにいた者でないとわからない」とつぶやくが、そこにはどんな拒絶のそぶりもなく、ただ、話して伝えようとすることばが、あのときに生きた(あるいは死とともにいた)事柄にとうてい届かないという、諦念の慎ましさがあるだけである。その諦念の前に、聞く者もまた、「黄泉がえり」の語りはあくまで生きていての語りであって、生死の境が消える「黄泉」の体験そのものではないということを、あらためて思う。
とはいえもちろん、オバアやオジイの語りが「イクサ世」について教えてくれることは少なくない。「集団自決」を生き延びた人びともいる。チビチリガマを最初に出て米軍に保護されたというオバアは、そのときの様子を語っている。中国戦線で日本軍の看護婦だった娘が、日本軍のやることを見てきていて、若い娘は生きていたらみんな強姦されて殺される、と皆に言ったため、娘のいる何家族かが「自決」し、それが壕内に伝染したとか、アメリカ軍のビラを「読んではいけない」という規制が強かった、といった話だ。オバアたちの話はそれだけだが、聞く者はそれで多くのことを理解する。日本軍の例から、軍隊や戦争がどういうものと考えられていたかがわかるし、人びとが戦争についてまったく教えられていなかったということもわかる。もちろん当時アメリカ軍の司令官は、対日戦に関してもはや戦闘員と非戦闘員の区別はないと公然と言っていたが(無差別空襲をやっていたから)、捕虜や非戦闘員の扱いに関する国際条約はそれでも有効だったのだ。結局、「集団自決」に極まったように、住民が軍隊以上に戦争状況に極限まで拘束されるという沖縄の「死の日々」、つまり「イクサ世」は、日本国家によって枠付けられた状況だったということだ。
だがこの「証言」をどう聞くかは、聞く者の側の問題である。まさ、この語りは何か世の中の「役に立つ」ような証言でさえない。背中に深い傷を負いながら命を拾い、傷とともにその後半世紀を生きてきたオバアが、この記録のために自分の「イクサ世」を全身に喚び起こし、あたかも体内にくい込んでいた砲弾の破片を押し出すように、それを島クトゥバに語り出して、そうすることでようやく、生きていてよかったと思えるようになった、と言いい、かの女の人生そのものの印であるような、背中を大きくえぐる傷を衒いなくカメラの前にさらす、そのような「黄泉がえり」のためにこそ、このフィルムは撮られている。
戦争直後、多くの人びとが肉親を失い、無一物の悲嘆というより茫然自失のなかをさまよっているとき、小那覇舞天という芸人が家々を回って陽気な芸を披露していたという。その振舞いに、弟子筋の照屋林助は、四人に一人が死んだというなら、三人生き残ったことを喜べ、生き残ったものには生あることを喜んで明るく生きる務めがある、そういう鼓舞の思いを読み取っていた。この思いこそ、多くのドキュメンタリーを見て沖縄戦の一端を知っていても、「イクサ世」を知らないわれわれにはけっして手の届かないものだろう。恐怖と悲惨と極限の飢えと疲労のなかで「われらの死の日々」を生き、そうして無数の骸を胸に抱いて生き延びた人びとだけが、そう考え、そう思って生きる務めを(というより権利を)もっている。その人びとの長い生き延びの生のなかに、悲惨な死を死んでいった多くの人びとの記憶が生きており、死はその記憶のうちで生と区別されないままとどまっている。まるでいつも「黄泉」がいのちのうちに抱えられているかのように。そしてその生が、「黄泉」に取り残され佇んでいた生が、いまカメラを前に救いとられてこの「語りの記録」のなかに甦る。
写真集のための補遺
ふたたびダヴィッド・ルーセの言葉を借りるなら、「われらの死の日々」であった沖縄の「戦世」を語る多くのオジイ、オバアたち、ここにはその二百人ばかりの表情が集められている。
さまざまな顔がある。うつむき加減に曇った顔、見たくないものを思い起こすかのように眼を硬く閉じた顔、逆に、眼を見開いてこちらに真剣に訴えかける顔、あるいは、淡々と歌うように話す顔、遠くを、けれども外ではなく内に浮かぶ光景を見ている顔…。
これらの表情の背後に、見えないまま浮かんでいるイクサ世の光景は、声をまとい、言葉になってほとばしるとき、ただ顔の表情を動員するだけではない。日常の時間の奥から呼び覚まされる遠いはずの過去は、いまここに蘇るとき、それを生きた人の体のすべてをざわめき立たせる。銃を撃つ身振りをする人、胸元をひろげて傷をさらしながら語る人、怒りの表情で手をかざす人、ほらあそこに、と見えない断崖や敵兵を指さす人、いまも間近な爆音に耳をふさぐ人、鬼を見据えるように口を一文字に結んだ人、脳裏に浮かぶものを手まねで激しく振り払う人…。
写真はビデオのようには動かないし語りもしないが、それでもここにいる人びとの表情は一瞬に時間を凝縮し、そこからは音声以上に雄弁なことばが、声にならないまま響きわたっている。そんな表情がいくつもいくつも、ページを繰るごとに曼荼羅のように並んでめぐる。たぶん、それが写真の功徳だろう。ビデオではわれわれは、語りの時間に付き合い、たとえば六時間をかけて五百人の話を、一人ひとり順ぐりに聴く。写真は一瞬を切り取るにすぎないが、シャッターは時間を廃絶し、そのとき語る人の脳裏にあるもののすべてを無時間の平面に焼き付ける。
沈黙の声が絞り出される深くえぐれた喉。ときにことばを失って、戦場での茫然自失に戻るかの人もいる。穏やかに笑って語るひとの眼に、見るともなく映っているのは、死んだ人たちへの思いだ。レンズのこちらを指差して、責めるように、訴えかける人もいる。あるいは、ゴム手袋のような手、もう六十年もこの手でタバコをすってきたのだろう…。
この写真集は、イクサ世の地獄をまったく僥倖のようにして生き延び、半世紀を行き続けてきたオジイ・オバアの「いま」の賛歌のようでもある。安楽ではなかった日々の生活をせわしく、あるいは騙しだまし生きぬき、そのなかで深く刻まれた皺や、その溝に沈む口、不ぞろいな歯並び、目元のしみに具現した半世紀の歳月。その老いをつややかにする時間の磨きだした風格。商売を切盛りしてきたらしい恰幅のいい人もいれば、日々の力仕事をこなしてきた人、失うことに慣れ、虚空にじっと目を向ける人、寡黙そうな人、泰然とした人、厳しそうな人。服装もまたさまざまで、アロハシャツの人もいれば、革ジャンをはおった人、ジャケットを着た人、ブラウスの人、ワンピースの人、着物の人、作業着の人、それぞれの人が、それぞれの風情で、それぞれの思いを、それぞれの仕方で語っている。共通しているのは、いま口にするのがいちばん“生き生きした”思い出であるかのように、少なくとも、それをいま語ることが無くしていた生の“黄泉がえり”であるかのように、誰もがいまの「生」のありったけをこめて語っている。音のないその声が、この顔の曼荼羅のなかからざわめき立つように響いている。 (二〇〇七・五・一〇)