あなたのための世論作ります—新しい情報製造業
(『新潮』8月号「クロスロード」より)

あなたのための世論作ります—新しい情報製造業
(『新潮』8月号「クロスロード」より)



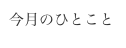

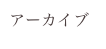

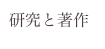

戦争が嫌悪されるのは、それが破壊行為であり多くの犠牲を生むからだけではない。戦時下には、戦争遂行という目的のために、国家が個人の活動をあらゆる面にわたって拘束し、その生命まで活用するという体制が敷かれ、その強制的な体制のなかで、権力の側に身を置くもののあらゆる類の不正がはびこって、人びとを理不尽な地獄に引き入れるからだ。権力は人を腐敗させると言われるが、権力が最大限に露呈する戦争では、それもとりわけ社会が高度に組織化された現代の世界では、その腐敗も極限に達する。そのあげくに人びとは、あらゆる抵抗の手立てをあらかじめ奪われ、暴力と恐怖と殺戮が原理である戦場に駆り出されて死んでゆかねばならない。その体制に異を唱える者ほど、前線に送り込まれて合法的に抹殺される。
戦争は国家の強制力の下に、あらゆる不正を極大化させる。だから戦争は嫌われるのだ。そのことは、戦争をしたがり、愛国心などを教育したがる連中が、けっして自分たちが兵卒になって戦場に行くことなどを想定していない、ということからも歴然としている。彼らは国家の名の下にみずからの地位の向上や世界観の押し付けを求めて、机を囲んで軍隊という名の使える道具を采配するだけだ。日本の戦争はそのことを、われわれの親たちにいやという程教えたのだ。
ところが、いつの間にか、戦争はして当然のことになった。そしてそれに対する備えがないのは間が抜けている、という話になっている。だからいわゆる「有事関連法案」、自民党の歴代首相が出そうとしても出せなかった法案が、簡単に国会で成立してしまった。ただそれでも、「有事」(何が有るのか?)というきわめて婉曲的な表現を使っているところに、「戦争」を隠したいという意図は透けて見えている。危険があるから「備える」という。だが「戦争に備える」とは、戦争を準備するということである。戦争は一方的な行為ではないからだ。たとえそれが憲法と齟齬をきたすものであっても、戦争をするための法律ができた。となると、もう戦争はできるのだが(「敵」が攻撃して来ること、あるいはその危険があると米軍!が判断しさえすれば)、その場合、とりわけ日本では、かつてこの国がどういう戦争をしたのかということをもう一度とくと考えてみる必要がある。
この変化はもちろん唐突に起こったわけではない。けれどもそれがやはり「九・一一効果」によって急激に加速されたことは否めないだろう。「九・一一効果」というのは、例の事件によってアメリカ社会が陥った「テロ恐慌」をバネに、アメリカ政権が一気にスーパー・パワーの「力の正義」を押し立てて、あからさまに世界の軍事的「改造」と経営に乗り出したことを指して言う。それまで公然とはもち出せなかったこの路線を「九・一一」によって正当化し、危険はあらかじめ潰す必要があるとして「先制攻撃ドクトリン」まで打ち出し、アメリカ国家はついに十年来の懸案だったイラクの軍事的改造に踏み込んだ。そしてその後は、イラクの「大量破壊兵器査察」と同じ手口で、今度は「核査察」を梃子に、しだいに照準を本来の目標であるイランに向けつつある(それに比べれば、北朝鮮のあがきなどアメリカにとって、うるさいハエ程度のものだろう)。七九年のイスラーム革命のカリスマだったホメイニの死後、イランは徐々に軟化路線をとり、一般的にはもはや世界の不安要因だとはみなされていない。にもかかわらず、核査察問題を焦点化することでいまや「イラン問題」が生じつつある。そしてそれはやがて対イラクと同じやり方で、緊急の「国際危機」にまで高めることができるのだ。「イスラーム革命」のイラン、百人以上のアメリカ大使館員を四〇〇日余にわたって人質にしたイラン・イスラーム共和国政権こそが、イスラーム世界の復興と自己主張を支える拠点であり、アメリカの世界経営戦略にとって放置できない敵なのである。
