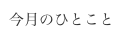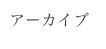アメリカの「国務」としての世界秩序


(「バグダッド陥落」の翌々日に共同通信を通じて配信された記事です)
バグダッドが陥落したという。アフガニスタンと同じく、米英軍は予想外に早く「目標」達成に近づいたようだ。たしかにこれでイラクの人々は(クルド人も含めて)フセインの支配体制から解放される。けれどもことは単純ではない。テレビに流れたフセイン像倒壊の現場には、五百万市民のうち二百人程度しかいなかった。カメラの前で米軍に手を振る人がおり、また略奪に走る人びとがいる。それが伝えられる「解放」の一端だ。
首都進攻の前後、イラク兵は千人規模で殺されたが米側の死者はその日一人とも報じられた。一方は大量の無意味な死、他方は「崇高な使命」のための犠牲だ。空爆の犠牲者や、戦闘に巻き込まれて死んだ人の数は数えられてもいない。フセインは嫌いだが家族や祖国のためにとわざわざ帰国した人もいた。多くの人びとがこの「解放」をやり場のない思いで迎えていることだろう。それは同時に新たに介入した強者への屈従の始めでもある。
ところで、メディアが「イラク戦争」と呼ぶこの事態はいったい「戦争」なのだろうか。たしかに大規模な軍事行動があり、空爆や戦闘で人が死ぬというかぎりでは「戦争」である。だがその「戦争」に米国が「勝った」のだとして、「敗戦国」はどこなのか。イラクなのか。しかし米国はイラクを「解放」したと言う。「敵」はイラク民衆ではなくサダム・フセインだと。つまりアメリカの「戦争」は、もはや一国ではなく、ひとりの「独裁者」を標的にしたものだったのだ。その「敵」は、あらかじめ「犯罪者」で、抹殺の対象ではあっても、初めから交渉相手ではない。だから首を撃ち落とすように標的として爆撃される。そしてこの「処刑ゲーム」にはもはや停戦や講和の相手はなく、「解放」された「無秩序」があるだけだ。
この事態が示しているのは、もはや国家の主権は「力の正義」の前に何ものでもないということ、それに自己決定権さえ「力の保護」なしにはありえないということ、そしてその「力」の作り変える世界とは、米国の秩序以外の何ものでもないということだ。
そこにはもはや諸国家の主権を前提とした「国際関係」という概念はない。世界の秩序は米国の「国務」なのである(アメリカには外務省はない)。今回フランスが「ブッシュの戦争」への反対を貫いたのは、たんに自国の利権のためばかりではなく、冷戦後の世界運営のあり方として「諸国家の社会」の共同原則を守ろうとしたからだ。
この「戦争」の背後にあるのは、九・一一以後公然化した超大国アメリカの「本土防衛」の要請であり、そこで目指されているのは安全からエネルギー確保までの米国の地位の万全化である。その地位と安全を脅かすものがいるかぎり、米国はそれを防ぐ権利があり、そのためにはどんな手段も正当化されるという主張が、「先制攻撃」論として打ち出された。イラク侵攻は、世界の他の地域の「解放」が米国の安全につながるという、「アメリカ的秩序」確立のための「遠征」だった。
だがまさにそのために、米国では「テロの危険度」が高まっているという。強大な力を行使すればするほど自分が脅かされると感じるというこの皮肉な逆説。そこからの現実的な出口に、米国社会はいつになったら目を向けるのだろうか。
その一方で「イラク解放」の現実は、冒頭に示唆したように多くの問題を孕んでいる。「正義」を掲げて剣を振るう米国の「救世主思想(メシアニズム)」は、多くの人びとの生活の多様な思いをサダムといっしょに「除去」することになる。サダムの悪政を知りつつ、なぜ「米国の戦争」に反対する広範な世論が世界的に沸き起こったのか、それをもう一度とくと考えてみる必要がある。