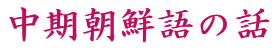 アクセント
アクセント
ハングルのローマ字転写は福井玲式、傍点は無点を - 、1点を + 、2点を = でローマ字転写の後ろに付してある。
(1) アクセントと傍点
現代朝鮮標準語にはないが、中期朝鮮語には日本語にあるような音の高低、すなわちアクセントが存在した。「声調」ともいうが、これはハングル創製当時の学者が中国音韻学の用語を借りて用いたものであって、朝鮮語のアクセントは中国語にあるような声調ではない。韓国の学界ではあくまで「声調」と呼んでいるが、もしそれが中国語のような声調を念頭にしているのなら、その呼称は厳密には正しいとはいえない。
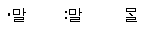 中期語の文献を見ると、ハングルの左横に点が加えられている。これはアクセントを表したものであり傍点と呼ばれる。無点を平声、1点を去声、2点を上声という。「平声」「上声」といった用語も中国音韻学の用語を借りている。中期語の平声は低調、去声は高調で、上声は昇り調だったことが分かっている。このうち、上声は低調と高調が複合した低高調なので、中期語のアクセントは低調と高調の2つのレベルを持っていたということになる。
中期語の文献を見ると、ハングルの左横に点が加えられている。これはアクセントを表したものであり傍点と呼ばれる。無点を平声、1点を去声、2点を上声という。「平声」「上声」といった用語も中国音韻学の用語を借りている。中期語の平声は低調、去声は高調で、上声は昇り調だったことが分かっている。このうち、上声は低調と高調が複合した低高調なので、中期語のアクセントは低調と高調の2つのレベルを持っていたということになる。
例に挙げた3つの単語は、左側の例の1点ついた mar「斗」が高調(去声)、真ん中の例の2点ついた mar「語」が低高調(上声)、右側の例の点のない m@r「馬」が低調(平声)である。ちょうど私たちが「雨」と「飴」を区別するように、中期朝鮮語でも音の高低で「mar(斗)」と「mar(語)」を区別していたのである
(2) アクセント核
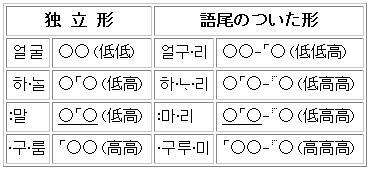 日本語は1単語のうちどこから音が低くなるかがアクセントの重要なポイントである。例えば、「からす」は「か」の後ろから低くなり、「こいのぼり」は「の」の後ろから低くなる。このとき「からす」の「か」、「こいのぼり」の「の」の直後には「降りアクセント核」があると見る。
日本語は1単語のうちどこから音が低くなるかがアクセントの重要なポイントである。例えば、「からす」は「か」の後ろから低くなり、「こいのぼり」は「の」の後ろから低くなる。このとき「からす」の「か」、「こいのぼり」の「の」の直後には「降りアクセント核」があると見る。
中期朝鮮語の場合は逆に、どこから音が高くなるかがポイントとなる。だから、日本語とは反対にそこに昇りアクセント核(略して昇り核ともいう)があるとみるわけである。そしてこの昇りアクセント核より前の部分は低調に発音され、後ろの部分は高調に発音されることになる。
表の例、'er-gur-(顔) という単語は、'er も gur も傍点がなく、ともに低調である。従ってこの単語にはアクセント核がないと見る。ha-n@r+(空) は ha が無点で低調、n@r に1点がついて高調なので n@r の直前に昇り核があると見る。gu+rum+(雲) という単語は gu も rum も1点がありともに高調なので、語頭の gu の直前に昇りアクセント核があると見る。昇り核を 「 というカギカッコのような記号で表し、モーラ(音の単位)を○で表したものが、表のハングルの横にある図である。なお、上声の単語、例えば mar=(語) のような単語は、上声が低調モーラと高調モーラの複合であるので、それ自体が ○「○ と表記される。だから mar= は ○「○ と表せるのだが、いちおう2モーラではあるが1音節の単語なので、1音節であることを表すために ○「○ のように下線を付しておく。なお、○ と 「 によるアクセント表示の方法は、菅野裕臣先生によるものである。
表の右側は、主格語尾 i (日本語の「…が」にあたる)がついた形を載せてある。i という語尾はそれ自体が昇りアクセント核を持っているので 「○ と表示される。従って、アクセント核のない 'er-gur- ○○ という単語に i がつくと ○○「○ のように i だけが高調になり、1点がつく。ha-n@r+ ○「○ はすでに n@r の直前にアクセント核があるため、i がついて ○「○「○ となっても i のアクセント核は意味を持たず、○「○○ と解釈される。アクセントは低調と高調の2種類しかないため、ひとたび高調に転じたアクセントは、それ以上高い音へ転じることはなく、単に高調のままに留まるだけである。gu+rum+ 「○○ に i がつくと、「○○○ のように高調モーラが3つ連続することになる(本来は 「○○「○ だが、ha-n@r+ の場合と同様に語尾 i のアクセント核は意味を持たないので 「○○○ と解釈される)。ハングルを見ると真ん中の ru に点がなく、「高低高」となっているが、これについてはこのすぐ下で言及する。
(3) 去声不連三, 語末平声化
昇りアクセント核の後ろでは全てが高調(去声)と解釈されるが、実際には低調(平声)が現われる場合が少なくない。これは高調が3つ連続するのを避ける中期朝鮮語の音声上の特徴のためであり、韓国の金完鎮先生は去声不連三と呼んでいらっしゃる。アクセント核の後ろに2つのモーラしかなければ2つとも高調で現われるが、3つ以上あるときは以下のように規則的に低調が現われる(低調を○、高調を●で表す)。
…「○○○ → …「●○●
…「○○○○ → …「●●○●
…「○○○○○ → …「●○●○●
上の表で、gu+ru-mi+ (雲が)の真ん中の ru が低調(無点)で現われているのは、まさにこの去声不連三によるものである。音韻論のレベルでは高調と解釈されるが、実際の音声としては低調として現われる現象が去声不連三である。
また、語末で高調が2つ続く場合に、語末の高調が低調に交替する現象がある。金完鎮先生が語末平声化(語末去平交替)と呼んでいらっしゃるものである。理由ははっきりしていないが、文がそこで切れるのではなく続いていくのを表しているらしい。菅野裕臣先生は語末平声化が起こる形を「継続形」と呼んでいるが、ゆえんはまさにそれである。
…●● → …●○
例えば、下の例は「乎はだれそれにという口訣に用いる字である」という意味の訓民正音諺解の中の1文であるが、ここで h@+non-、gie+cei-、bsy+nyn- はアクセントの型がみな 「○○ なので、1字めも2字めも高調(去声)で現われて、ともに1点がつくべきであるが、実際には語末が無点の低調(平声)で現われている。
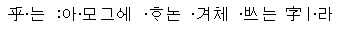
上の例を見ても分かるが、語末平声化は連体形でしばしば起こる傾向にあることを挙げておこう。
用言は活用によってアクセントが決まっている。中期語は第Ⅰ語基から第Ⅳ語基まで4種類の語基があったが、語基によってアクセント核の位置が動くものがあった。例えば下の例は bsy-da (使う)と ga-da (行く)の例だが、bsy-da はアクセント核が常に語頭にあるのに対して、ga-da の場合は第Ⅰ・Ⅱ語基ではアクセント核がないが第Ⅲ語基で語頭にアクセント核が現われ、第Ⅳ語基で第2モーラにアクセント核が現われるというように、語基活用によってアクセント核の位置が異なっている。
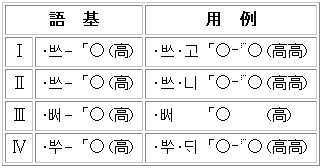
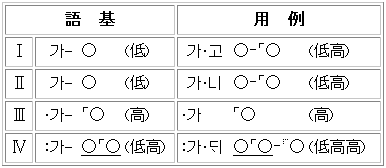
なお、語尾はそれぞれ固有のアクセント核を持っている。上の例で go+ や d@i+ は 「○ のように、頭にアクセント核があるが bsy+go+ や bsu+d@i+ の場合すでに語幹の頭にアクセント核があるので、語尾にある2つめのアクセント核が意味をなさないことは1の (2) で見たとおりである。従って、2つめのアクセント核は全く無視されることになる。
接尾辞も語基活用があり、用言語幹同様に語基にアクセント変化がある。下の表は、謙譲接尾辞 -s@b-、尊敬接尾辞 -si-、現在接尾辞 -n@- の活用とアクセントである。
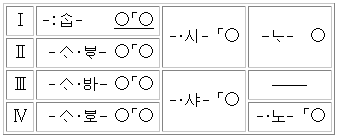
-s@b- と -si- はアクセント核の位置に変化がないが、-n@- は第Ⅳ語基でアクセント核が生じる。
例えば、ni-r@- (言う)という動詞の語幹に -n@- が付くとき、ni-r@- はアクセント核がないので ○○ と表され、全て低調(平声)で現われる。これに -n@- が付くと、-n@- もやはりアクセント核がないので低調で現われ、ni-r@-n@- 全体で ○○○ と全て低調になる。ここに -ni (…するので)という語尾が付くと、-ni はアクセント核を持つので 「○ と表され、ni-r@-n@-ni+ 全体で ○○○「○ と表され、アクセントは低低低高となる。しかして、最後の ni にのみ傍点が1点つくことになる。
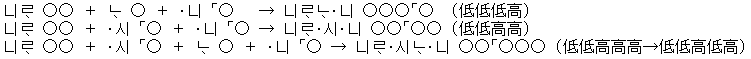
ある種の語幹に、ある種の接尾辞や語尾がついたときに、アクセント核の位置が変わることがある。
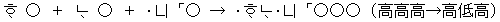
上の例は、h@-(する) に接尾辞 -n@- がついている。h@- は ○、-n@- は ○ と2つともアクセント核がないので、本来ならば ○○(低低) となるはずだが、この2つがくっつくと語頭にアクセント核が生じて 「○○(高高) となる。h@- のみならず ga-(行く) や ju-(やる)など、語幹がアクセント核のない1音節母音語幹用言のとき、後ろに接尾辞 -n@-、-ge- 、-de-、-si-、-z@v- などがつくと、語頭にアクセント核が生ずる。このようにアクセント核の位置が変わる現象は、日本語の「読む」と「読みます」でアクセントが変わるのと似ている。
このような現象は体言でも起こりうる。例えば na-(我) ○ に n@n+(…は) 「○ がつくと ○「○ ではなく、やはり語頭にアクセント核が生じて 「○(「)○ となる。
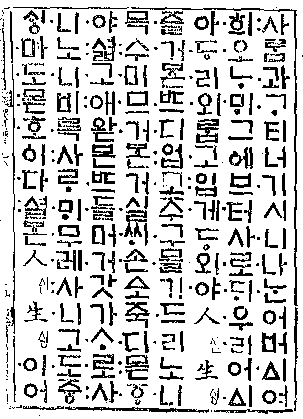 では中期朝鮮語のアクセントを『釈譜詳節』巻六の5張で確認してみよう。
では中期朝鮮語のアクセントを『釈譜詳節』巻六の5張で確認してみよう。
1行め
- sa=r@m-goa+ … sa=r@m+(人) ○「●● に 共格語尾 goa+ 「● がついて ○「●●● となる。去声不連三により ○「●○● と現われる。
- g@+ti- … 「●● だが、語末去平交替により 「●○ と現われる。
- ne-gi+si-ni+ … ne-gi+(思う) ○「● に尊敬接尾辞 si+ 「● と接続形語尾 ni+ 「● がついて ○「●●● となる。去声不連三により ○「●○● と現われる。
- na+n@n+ … na-(我) ○ に とりたて語尾 n@n+ 「● がついて ○「● だが、n@n+ の前で na- の直前にアクセント核が生じて 「●● となっている。
- 'e-be-zi+ … ○○「●。
- 'ie-hyi+'o+ … 'ie-hyi+(分かれる) ○「● に接続形語尾 'o+ 「● がついて ○「●● となっている。
2行め
- n@-m@i+ … n@m-(他人) ○ に属格語尾 @i+ 「● がついて ○「●。
- gy-qei- … ○○。アクセント核なし。
- by-te+ … ○「●。byt-(つく) の第Ⅲ語基形。
- sa-ro+d@i+ … sar=(生きる) の第Ⅳ語基形 sa-ro+ ○「● に接続形語尾 d@i 「● がついて ○「●●。
- 'u+ri+ … 「●●。語頭にアクセント核がある。
- 'e-zi+ … ○「●。
3行め
- 'a-d@+ri+ … 'a-d@r+(息子) ○「● に主格語尾 i+ 「● がついて ○「●●。
- 'oi+r@b-go+ … 'oi+r@p+(孤独だ) 「●● に接続形語尾 go+ 「● がついて 「●●● となり、去声不連三により 「●○● と現われる。
- 'ib=gei+ … 'ib=(迷わしい) ○「● に副詞形語尾 gei+ 「● がついて ○「●● となる。
- d@-'oi-'ia+ … ○○「●。d@-'oi-(なる) ○○ の第Ⅲ語基形。
4行め
- jyr+ge+vyn- … jyr+gev+(楽しい) 「●● の第Ⅱ語基 jyr+ge+vy+ 「●●● に連体形語尾 n がついた形。語末去平交替により 「●●○ と現われる。
- bdy+di+ … bdyd+(意) 「● に主格語尾 i 「● がついて 「●● となる。
- 'eb=go+ … 'ebs=(ない) ○「● に接続形語尾 go+ 「● がついて ○「●● と現われる。
- ju-gu+myr+ … jug-(死ぬ) ○ の第Ⅳ語基 ju-gu+ ○「● に体言形語尾 m がつき、さらに対格語尾 yr+ 「● がついて ju-gu+myr+ ○「●● となっている。
- gi-dy+ri+no-ni+ … gi-dy+ri+(待つ) ○「●● に現在接尾辞 no+ 「● と接続形語尾 ni+ 「● がつき ○「●●●● となるが、去声不連三で ○「●●○● と現われる。
5行め
- mog-su=mi+ … mog-sum=(命) ○○「● に主格語尾 i 「● がついて ○○「●● となる。
- my+ge+vyn- … my+gev+(重い) 「●● の第Ⅱ語基 my+ge+vy+ 「●●● に連体形語尾 n がついた形。語末去平交替で 「●●○ となる。
- ge-sir+ss@i+ … ges-(こと) ○ に指定詞 i+ 「● がつき、それに接続形語尾 -r-ss@i+ 「● がついて ○「●● となっている。
- son+zo- … 本来 「●● だが、語末去平交替で 「●○ と現われている。
- jug-di+ … jug-(死ぬ) ○ に体言形語尾 di+ 「● がついて ○「● となる。
- mod= … ○「●。
- h@+'ia+ … 「●●。h@-(する) ○ の第Ⅲ語基形。
6行め
- sier=go+ … sier= ○「● に接続語尾 go+ 「● がついて ○「●● となる。
- 'ai='oad-byn- … 'ai= ○「● と 'oad-byn- ○○ は別の単位。合わせて ○「●+○○。
- bdy+dyr+ … bdyd+(意) 「● と 対格語尾 yr+ 「● で 「●●。
- me-ge+ … ○「●。meg-(食う) ○ の第Ⅲ語基形。
- gas-ga-s@+ro+ … ○○「●●。gas-gas- ○○ に具格語尾 @+ro+ 「●● がついた形。
- sa=ni+no-ni+ … sa=ni+(生きる) ○「●● に現在接尾辞 no+ 「● と接続形語尾 ni+ 「● がついて ○「●●●● となり、去声不連三で ○「●●○● と現れる。
7行め
- bi-rog+ … ○「●。
- sa=r@-m@i+ … sa=r@m+(人) ○「●● に語尾 @i+ 「● がついて ○「●●● となり、去声不連三により ○「●○● と現れる。
- mu+rei+ … mur+(群れ) 「● に語尾 ei+ 「● がついて 「●●。
- sa=ni+go-do+ … sa=ni+(生きる) ○「●● に語尾 go+ 「● と do+ 「● がついて ○「●●●● となり、去声不連三で ○「●●○● と現れる。
- juq-saiq- … ○○。アクセント核がない。
8行め
- ma+do+ … 「●●。
- mod= … ○「●。
- ho+qi-da+ … h@-(する) ○ の第Ⅳ語基形 ho- 「● に語尾 qi-da+ ○「● がついて 「●●● となり、去声不連三で 「●○● と現れる。
- sier=vyn- … sierb=(悲しい) ○「● の第Ⅱ語基形 sier=vyn+ ○「●● に連体形語尾がついて ○「●● だが、語末平声化が起きて ○「●○ と現れる。
- 人生'i+ … 漢字語「人生」に語尾 'i+ 「● がついている。
このように、中期朝鮮語のアクセント体系は非常に明瞭である。従って、上のようにアクセントに関する規則をいくつか覚えれば、中期語の文献に出てくるアクセント現象はほとんど理解することができるのである。
6. 役に立つ文献
中期語のアクセントに関しては、以下のような文献を参照すると役に立つ。
- ▲ 許雄(1955)「旁點 研究」、『東方學志』第2輯、延禧大學校出版部
- 韓国のアクセント研究の嚆矢ともいうべき研究。中期語語彙のアクセント型を詳しく分類し、現代慶尚道方言との対応関係を分析。朝鮮語アクセント研究の古典的論著。
- ▲ 金完鎮(1963)「形態部 聲調'yi 動揺'ei 對ha-'ie」、『西江大學 論文集』第1輯、西江大學
- 去声不連三、語末去平交替を定式化した論文。以降のアクセント研究に多大な影響を与えた必読の一篇。
- ▲ 金星奎(1994)『中世國語 聲調 變化'ei dai-han 研究』、se'ur大學校 國語國文學科 文學博士學位論文
- アクセントのさまざまな現象を語源的視点を入れて綿密に分析した論著。去声不連三の変則的な現れ方について鋭い切り口で論じている。アクセント論からのアプローチではないが、分析の手法はアクセント論に近い。
- ▲ 河野六郎(1953)「中期朝鮮語用言語幹の聲調に就いて」、『河野六郎著作集』、第1巻、平凡社
- 語基を導入してアクセントの現象の解明を試みた論文。金完鎮(1963)の去声不連三の理論が発表される前の論著だが、それに似た言及がなされている。
アクセント論にのっとった日本の研究には以下のようなものがあるので、参照するとよい。
▲ 門脇誠一(1976)「中期朝鮮語における声調交替について」、『朝鮮学報』第79輯
▲ 福井玲(1985)「中期朝鮮語のアクセント体系について」、『東京大学 言語学論集'85』、東京大学文学部言語学研究室
▲ 福井玲 編(2000)『韓国語アクセント論叢』、東京大学大学院人文社会系研究科 附属文化交流研究施設 東洋諸民族言語文化部門
韓国の論著は概してアクセント論から中期語のアクセントを論じたものが非常に少なく、多くは「声調」と捉えている。
中期朝鮮語の話へもどる
朝鮮語の部屋のメニューへ
ホームページのトップへ
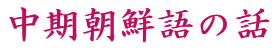
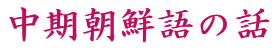
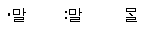 中期語の文献を見ると、ハングルの左横に点が加えられている。これはアクセントを表したものであり傍点と呼ばれる。無点を平声、1点を去声、2点を上声という。「平声」「上声」といった用語も中国音韻学の用語を借りている。中期語の平声は低調、去声は高調で、上声は昇り調だったことが分かっている。このうち、上声は低調と高調が複合した低高調なので、中期語のアクセントは低調と高調の2つのレベルを持っていたということになる。
中期語の文献を見ると、ハングルの左横に点が加えられている。これはアクセントを表したものであり傍点と呼ばれる。無点を平声、1点を去声、2点を上声という。「平声」「上声」といった用語も中国音韻学の用語を借りている。中期語の平声は低調、去声は高調で、上声は昇り調だったことが分かっている。このうち、上声は低調と高調が複合した低高調なので、中期語のアクセントは低調と高調の2つのレベルを持っていたということになる。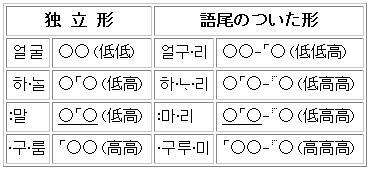 日本語は1単語のうちどこから音が低くなるかがアクセントの重要なポイントである。例えば、「からす」は「か」の後ろから低くなり、「こいのぼり」は「の」の後ろから低くなる。このとき「からす」の「か」、「こいのぼり」の「の」の直後には「降りアクセント核」があると見る。
日本語は1単語のうちどこから音が低くなるかがアクセントの重要なポイントである。例えば、「からす」は「か」の後ろから低くなり、「こいのぼり」は「の」の後ろから低くなる。このとき「からす」の「か」、「こいのぼり」の「の」の直後には「降りアクセント核」があると見る。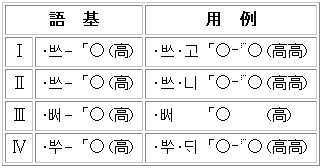
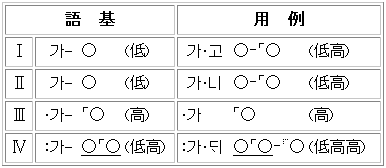
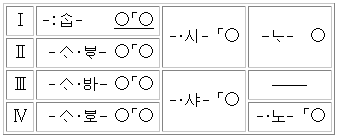
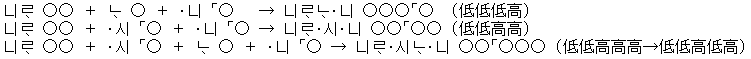
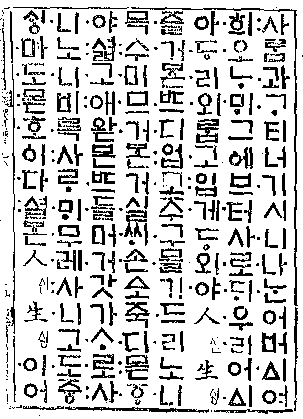 では中期朝鮮語のアクセントを『釈譜詳節』巻六の5張で確認してみよう。
では中期朝鮮語のアクセントを『釈譜詳節』巻六の5張で確認してみよう。