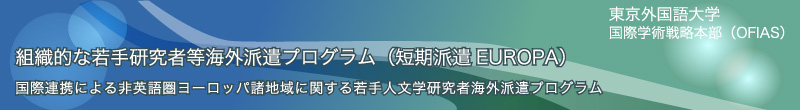2011年12月 月次レポート(中村隆之 フランス)
短期派遣EUROPA月次報告書12月
中村隆之(東京外国語大学リサーチフェロー/フランス社会科学高等研究院)
今月の報告は、初旬に訪れたベルギー王立中央アフリカ博物館の見学記から始めたい。パリから電車で1時間30分ほどで訪れることができるブリュッセルに日帰りで訪れた12月4日、近郊のテルヴューレンに足を運んだ。ブリュッセル中心から電車やバスを乗り継いで約1時間ほどである。王立アフリカ博物館はベルギー王国の旧植民地コンゴの文化財、「美術品」を所蔵している。文化財と「美術品」と述べたのには理由がある。この博物館では、博物学的展示と美術館的展示が併存しているからである。入口付近は主にアフリカで収集された品々を、衣食住や芸能といった各テーマにあわせて展示している。一方、常設展の後半は、「原始美術」としてその芸術性を認知されている彫像の数々が、さながら宝石のように暗室のショーウインドウのなかで不気味な光を放っている。この展示手法は明らかに近年のもので、素人の感覚からしても、パリのケ・ブランリ美術館(musée)との相同性を指摘せずにはいられない。じつは報告者がベルギーの王立中央アフリカ博物館(musée)に関心を抱いたのも、ケ・ブランリ美術館開館の記念シンポジウムの記録『諸文化の対話』のなかで、王立アフリカ博物館の学芸員の発表、とりわけこの場所を、植民地をめぐる開かれた記憶の場にしようとする数々の努力に触れたことが大きかった。たしかにこの博物館内には、洗練されたアフリカ料理が低価格で食べられる食堂があったり、限られた予算内での教育的な展示の企画や、さまざまな文化交流の催しが開かれていることはわかった。家族連れの客を引こうと子供受けする企画が開催されていたりもした。しかし、そうした創意工夫にもかかわらず、ベルギー王立アフリカ博物館に私が感じた印象は、おぞましく異様なものだった。その印象を強める理由は、ケ・ブランリ美術館の再現のような既視感、もう少しいえば、審美性の名のもとに、収奪の痕跡を巧妙に隠蔽する装置として機能している「原始美術」の演出だけに必ずしもあるわけでなかった。
異様な印象を抱いたいまひとつの理由は、博物館常設展の最初の通路の中央に置かれた象の剥製にある。この象は、1958年ブリュッセル万国博覧会のためにベルギー領コンゴから運ばれてきた。象だけでない。万国博覧会のためにアフリカの動物相を代表する多くの動物が剥製として展示されている。じつは、ベルギー王立アフリカ博物館の展示品のおよそ半分は「象」に代表されるアフリカの動物の剥製の展示なのだ。
この博物館を訪れる人たち(家族連れが一定数いた)がどのような思いで観賞するのかはわからない。少なくとも私には、動物相を復元したジオラマは、植民地主義の露骨な現前以外のなにものでもなかった。このジオラマの説明は「科学的」であり、植民地支配の過去を清算するような言葉はひとことも書かれていないにもかかわらず、である。ちなみに報告者はまだパリの自然史博物館を訪れていないが、おそらく同じような展示物が予想される。しかし、王立中央アフリカ博物館の恐るべきところは、動物も文化財も含めてすべてがベルギー領コンゴ支配との関係において併置されているところである。このようなあからさまな展示は、今日なかなか実感しにくい植民地支配の問題を視覚的に示してくれる点で、逆説的だが貴重であるともいえなくない。
今月は中旬にパリで本研究に関連する催しが続いた。ひとつは、フランス社会科学高等研究院に博士論文を提出した研究者の審査会である。Silyane Larcher氏のL'Autre citoyen. Universalisme civique et exclusion sociale et politique au miroir des colonies post-esclavagistes de la Caraïbe française (Martinique, Guadeloupe, années 1840-années 1890)という論文の審査である。主査のピエール・ロザンヴァロンをはじめとして、エティエンヌ・バリバール、パトリック・ヴェイユほか計6人の教授陣が審査にあたった。題名にあるとおりカリブ海フランス植民地を参照項に市民概念とその適用の実際などを、歴史学、政治学、社会学の多岐の分野にわたって考察した論文である。1870年のマルティニックでの蜂起について一次史料にあたって再構成した点なども評価されていた。自分の関心に引きつけると、1848年の奴隷制廃止がどのようなプロセスを経て実際に適用され、また適用されなかったのかという点に興味を抱くとともに、ある問題を総合的に解明するさいにはいわゆる学際的な方法が要請されるのだという感想をもった。
また、全-世界学院のセミナーで、最近浩瀚なエドゥアール・グリッサン論を上梓した哲学者アラン・メニルの講演を聞く機会もえた。諸事情で前半を聞き逃してしまったが、フランソワ・ヌーデルマンの司会のもと、グリッサンのキーワードである「クレオール化」の複数の意味について語っていた。報告者も来年以降グリッサン論に本格的に取り組む予定であるので、これを機にメニルの著作を読む必要を感じた。先月から始まったエリック・ファサンとルイ=ジョルジュ・タンのエメ・セゼールをめぐるセミナーの二回目では、セゼールの『植民地主義論』を出発点に、南アメリカのギュイヤンヌ県選出のクリスティアヌ・トビラが提出した、奴隷制と奴隷貿易を「人道に対する罪」と定める法律以降の奴隷制の記憶をめぐる話が展開された。またエリック・ファサンは、近年、植民地主義とナチズムがほとんどセットのように語られるようになったが、その先駆けとなったセゼールの『植民地主義論』が刊行された1950年当時、まだ植民地主義の問題、とりわけ人種差別の問題はほとんど社会科学の分野でも注目されることがなかったことを考えると、いつ、どのような条件で植民地主義の問題は可視化したのか、という点を問うべきだという、興味深い問題提起がなされた。
ほかにも、今月下旬から海外県映画週間がシネマテーク・フランセーズで始まり、オープニング上映でOh Madianaという、1970年代のカリブ海移民への差別やアイデンティティを描く佳作とともに、映画創成期の監督ジョルジュ・メリエスによる1902年のプレ山噴火を題材にした短編サイレント映画を観た。この映画週間中シネマテークに通いたいという思いもあったが、先月以来続けている関係資料の読解と執筆が遅々として進まないこともあり、日々を自宅および図書館で過ごすことを選んだ。先月取り組んでいたカリブ海地域の先住民についての資料調査と執筆にも一段落がつき、今月は同地域に敷かれた奴隷制について、その歴史的展開を経済的視点から捉える方向で執筆作業を進めている。来月以降もこの作業を引き続き継続しつつ、なるべく早く次の研究段階に移行したい。
王立中央アフリカ博物館の象のはく製