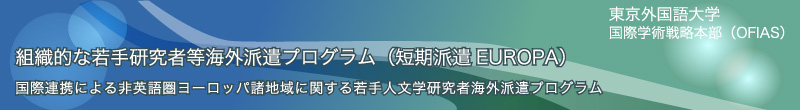2011年9-10月 月次レポート(岩崎理恵 ロシア)
2011年9月・10月月次報告
報告者:岩崎理恵
派遣先:ロシア国立人文大学
9月前半は公募書類の準備に加え、最後の学会報告に向け忙しく過ごした。加えて8月までの暑さが嘘のように急に気温が下がり、逆に湿度が上がったこともあって風邪をこじらせ、ひどい咳で眠れず体調がなかなか回復しないという悪循環に陥った。
このような時に、研究とはまったく関係のないところで問題が発生し、対処に追われたこともさらにストレスを加えた。まず9月頭に突然、6日間にわたって自宅でのインターネット・アクセスが切断された。サーバー・モデム間の通信が確認できない状態のため、「原因究明と復旧をお願いしたい」と契約プロバイダーのサポートセンターに数回電話したのだが、「申し入れは受理された。サポートチームが順次対応するので、アクセスが回復するのを待って欲しい」という返事が返ってくるだけで、いたずらに日数が過ぎるばかりであった。アクセス不能の理由は通信ラインの工事をしているからだと説明されたが、顧客に事前の連絡もせず接続が切断されたり、復旧に6日もかかるとは、と釈然としない思いだった。が、日本の「普通」はロシアでは通用しない。モスクワにはWiFiフリーのカフェが無数にあり、単にインターネットに接続するのには困らないが、ただでさえ集中力の必要な論文や書類書きの合間を縫って、メールチェックや調べもののため近所のカフェに通うのは、息抜きというより余計な手間でしかなかった。
ふり返ればこのようなごたごたもせいぜい10日ほどの間のことでしかなかったのだが、実際以上に長く感じたのは体調不良のせいかも知れない。ようやく書類を発送し、学会報告の原稿を書き終えネイティブ・チェックを済ませたのは、学会が目前に迫った9月半ばのことだった。
9月12日からはいよいよ、モスクワの科学アカデミー世界文学研究所にて国際学会「『始まりと終わり』詩人の生と宿命」が始まった。実は昨年2010年は詩人アレクサンドル・ブロークの生誕130周年、今年2011年は没後90年の年に当たり、報告者は偶然ながらその両方をロシアで迎える幸運に恵まれたことになる。今回の学会のタイトルはブロークの未完に終わった長編詩『報い』冒頭の「芸術家よ、固く信じよ、始まりと終わりを」という一節を引いており「終わり」を意識させるものになっていたが、祝祭的な雰囲気に包まれた去年の学会ほどの参加者はなく、筆者の指導教授であるマゴメードワ先生も足の怪我で不参加だった。が、アヴリル・パイマン教授の姿はあったし、学会組織委員長であるイリーナ・プリホジコ女史は変わらず暖かく、きめ細やかなホストぶりで会を進行して下さった。
まず2日間にわたり世界文学研究所での報告会が行なわれ、筆者は初日に、1906年に書かれた詩«Так окрыленно, так напевно...»についての報告を行なった。ブロークの初期の詩におけるヒロインの中でも「王女」の形象は重要な位置を占めるが、今回取り上げた詩においては、それまでの一連の作品ですでに定着した語彙や、王女のイメージの源泉の一つである『眠れる王女』(ジュコフスキー)、『死せる花嫁』(プーシキン)等の要素を受け継ぎながらも、男性に剣を取るよう促し、旅路へ送り出すという新たな役割を負った姿で描かれている。このため「王女」の形象の系譜上、一つの転換点となっているばかりでなく、1907年に書かれた戯曲『運命の歌』のヒロインの一人エレーナのおもかげをも感じさせる点で、ブロークの詩作と、1906年以降生み出された抒情劇とをつなぐ、鎖の輪のような役割をも果たしていると考えられるのである。
夏の間時間をかけて論を練り上げてきたこともあって、報告の内容に関する不安はなかったが、38度の熱をおして壇上に立ったため、本番は緊張する余裕すらないまま、あっという間に終わってしまった。翌日の報告も体調不良のため聞くことはできず、3日目に予定されていたモスクワ郊外シャフマトヴォのブローク博物館保護区へのエクスカーションへの参加も見合わせた。
ただ、これでようやくロシアでの研究生活を締め括ることができる、という達成感は大きかった。前年のブローク学会で「来年こそはこの場で発表しよう」と決意し、そのためのステップとしてこの1年、さまざまな場で学会発表を行なってきたが、それぞれに反省点や学んだ点があった。自分で決めた目標でも、時間的・能力的に追い込まれたり、気後れから逃げ出したい気持ちになったりすることもあり、とりわけ滞在期間の後半からは、数をこなすだけではなく質も高めなくてはというプレッシャーを感じていた。それだけに今回は、弱気になりかける自分に克てたという喜びが大きかった。
モチベーションを保ち続けることができた大きな要因は、ロシアでマゴメードワ先生を始め、これまで論文や著作でしか知らなかった研究者らと知り合い、その業績に触れる機会に恵まれたことである。第一線で活躍している研究者の報告や論文の中に、自分が感じていた疑問点を解くヒントを見つけた時の喜びや、それについて議論することのできる相手がいるありがたみは、日本で孤独に作業を進めてきた筆者にとって、何物にも代えがたいものだった。
学会後は自宅で療養していたため、風邪はほぼ全快したが、一週間後には就職試験のため日本に一時帰国した。この強行軍がたたったのか、モスクワに戻った直後の10月頭からまた具合が悪くなった。始めは風邪がぶり返したのかと思い、風邪薬や頭痛薬など飲んでいたのだが効いている様子がない。目から眉間にかけての鈍痛や微熱などは、根をつめて論文書きをしている時にはよくあることであるし、疲れのせいかとあまり気にも留めていなかったのだが、ふとしたことから、副鼻腔炎の可能性があることを知った。念のため持ってきていた抗生物質で症状を若干抑えることはできたものの、正確な診断と治療は日本の医師に任せたいと思い、とにかく大事を取りながら、残りの二週間を乗り切ることを決めた。
しかしちょうど帰国に向け、本格的な引き上げ準備にも取りかからなければならない時期で、荷造りや掃除など、自然肉体労働が多くなる。大量の書物を郵便局まで運び、発送する作業も一仕事で、そうした外出で疲れてしまうと、翌日には症状が悪化し、割れたビンから水が漏れるように、体に力が入らない状態になってしまう。これまでは気力で乗り切ってきたが、今回ばかりは体力の限界を超えてしまったらしい。友人・知人に応援を頼み、荷物を運ぶため車を出してもらったりして何とか乗り切った。
このような波乱はあったものの、一年間大きなトラブルもなく、ひとまず無事に滞在を終えることができ、ほっとしている。今後日本に研究基盤を移すことになっても、この体験を糧に、強い精神力で乗り切っていきたいと考えている。