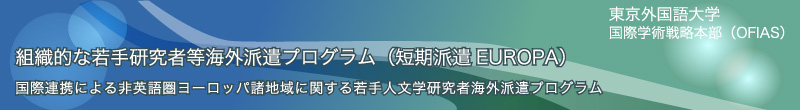2011年4月 月次レポート(岩崎理恵 ロシア)
2011年4月月次報告
報告者:岩崎理恵
派遣先:ロシア国立人文大学
4月15日から17日にかけて、エストニアのタルトゥ大学で開催された若手研究者向けの国際学会に参加し、報告を行なった。
タルトゥ大学を訪れるのは昨年7月、ペテルブルグへの研究旅行の帰りに立ち寄って以来だった。その時は大学が夏休み期間中だったにもかかわらず、同大学ロシア文学研究科のロマン・レイボフ教授とレア・ピルド教授が出迎えて下さり、ユーリー・ロトマンとザラ・ミンツ夫妻の眠る街外れの墓地まで案内して下さった。またロシア文学研究科の共同研究室で、1883年から10年にわたり同大学(当時の名称はドルパト大学)で教鞭を取ったボードゥアン・ド・クルトネが残していったという伝説の椅子にかけ(実際、伝説にすぎないが)、美味しいコーヒーをご馳走になりながら、研究のテーマや進捗状況などさまざまな話をした。わずか一日の滞在であったが、それ以来タルトゥは特別な場所になり、今回の学会への参加が決まった時には「またあの場所に行ける」という嬉しさで、出発までの慌ただしさも忘れられたほどだった。
ロシアからタルトゥに入るルートはいくつかあるが、今回はモスクワから空路でラトビアのリガに入り、「ユーロライン」の長距離バスで国境を超えることにした。航空券が割安で、乗り継ぎの時間の自由が利くことが主な理由だが、結果としてこのルートを取ったのは正解だった。ペテルブルグやプスコフを経由してロシアから直接エストニアに入国した参加者は、パスポート・コントロールのため国境で1時間も足止めされるなど、それぞれ大変な目に合っていたらしいが、ラトビア・エストニア間は嘘のようにスムーズに通過することができた。リガからおよそ4時間、目的地に到着したのは夜の10時半だったが、文学研究科の学生がバス停で出迎えてくれ、ホステルまでタクシーに乗せてくれた。
翌日、人文大学のエカテリーナ・リャミナ教授の特別講座を皮切りに、学会が始まった。残念ながら、ピルド教授は体調不良とのことでお会いできかったが、レイボフ教授と文学研究科のリュボーフィ・キセリョーワ科長にはまたお目にかかることができた。また今回は、同研究科のドミトリー・イワノフ教授と博士課程のアレクセイ・ヴドーヴィン氏が学会事務局としてさまざまな準備や連絡に当たって下さった。
「若手研究者向け」と銘打った学会は各地で随時開催されているが、報告のレベルは今回が群を抜いて高かった。参加者27名のうち、ほとんどがモスクワ、ペテルブルグの修士・博士の学生であり、他の学会で知り合った研究仲間もいて「知った顔」が多く、すぐに馴染むことができた。また海外からは、イタリアとドイツからそれぞれ1名、ハンガリーから2名の参加者がいたが、似たような趣旨の学会で、これだけの外国人と一緒になったことはこれまでなく、彼らにとってもタルトゥはやはり憧れの場所なのだなと感じた。
報告者は3日目に、ブロークの初期の詩篇「麗しの淑女の歌」を始め、第一巻詩集に繰り返し登場する「王女」の形象について報告した。先行研究によれば、この形象はフォークロアに取材して書かれたプーシキンの「サルタン王物語」「死んだ王女と七人の勇士の物語」、ジュコフスキーの「眠れる美女」等複数の文学的先例を持つとされるが、報告では、ブロークが最も密接な影響を受けたЯ.П.ポロンスキーの詩«Царь-девица»とブロークのヒロインの関連性を論じた。
学会日程が朝から夕方までみっちり組まれていたため、自由時間はあまり取れなかったが、市内の本屋は一通り巡ったほか、空き時間にはタルトゥ大学の植物園を散歩したりもした。4月のタルトゥはまだ肌寒く、時折小雨がぱらつくこともあったが、屋台でねこやなぎや黄色いチューリップの花束が売られている光景に、ヨーロッパの春を感じた。
最も印象に残ったのは、最終日、閉会のことばの代わりに流れたテープ音源である。レイボフ教授がこの日のために探し出して下さったカセットテープには、1990年の若手研究者向け学会であいさつするザラ・ミンツ女史の肉声が収められており、亡くなる半年前のものと聞いた。ミンツ女史にお会いできなかったことは筆者にとって何よりの心残りなのだが、声だけでも聞くことができ感激した。生き生きとした明るい話しぶりに、人となりがしのばれた。
レイボフ教授によれば、ソ連崩壊直前の1990年の学会にアメリカの若手研究者の一団が参加し、振り返ればこれが、現在のように開かれた、真に国際的な大会へと発展していく転換期だったという。録音は、そうした意味でも象徴的な大会の記録であったらしい。そうした歴史に、自分も曲がりなりにも連なることができたことが嬉しかった。
帰国後は、4月末に提出予定の論文2篇の仕上げに取り掛かった。2月に報告を行った「日本の歴史と文化」学会の論文集のためのロシア語の原稿と、日本の学術雑誌に投稿するための日本語の論文をそれぞれ仕上げて送った。
また、12月から取り組んできた早稲田大学演劇博物館の翻訳プロジェクトが終了し、4月からウェブ公開が始まったとの知らせを受けた。現在、英米、独、露のモダニズム期の演劇論の翻訳22点が以下のサイトで閲覧可能である。(http://kyodo.enpaku.waseda.ac.jp/trans/仏語の翻訳も今後追加される予定)
タルトゥ行きは、今年前半の一つの山場であった。前述のミンツ女史はあいさつの中で、「皆さんが今後、『若手研究者』ではなく、『よい研究者』となってタルトゥに戻って来て下さることを願っています」と語っていたが、この言葉通りになるよう、今後も努力していきたい。
タルトゥ大学、スラヴ人文学科棟の前で 学会での報告の様子