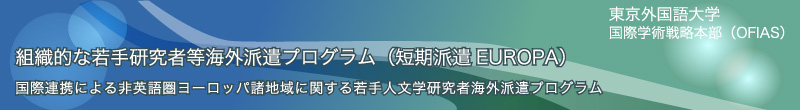2011年11月 月次レポート(フィオレッティ・アンドレア イタリア)
月例レポート
(2011年11月、博士後期課程 フィオレッティ・アンドレア)(派遣先:ローマ大学、イタリア)
11月は、研究に必要な資料の収集をおこなった。特に物語論(ナラトロジー)と翻訳理論の分野に集中した。物語論に関してはジェラール・ジュネットやロラン・バルト、藤井貞和の研究は必須の文献である。私の研究の目的は、時代とともに、とりわけ十七世紀から小説における語りの方法がどのように展開し、変化してくるか、そして西洋の語りの方法がどのような形で明治時代の日本文学に翻訳され、導入されたかである。そのため、分析を進めるために、物語論だけではなく、書誌学、原典批評、印刷物と出版業の歴史にまで研究領域を広げる必要があると考えている。この領域に関して、博士論文の参考文献の一部になる作品を以下に挙げる。これらのテキストから、研究テーマをより深く扱うための重要な手がかりをえた。
Pasquale Stoppelli, Filologia della letteratura italiana, Carocci, 2008;
Pasquale Stoppelli (a cura di), Filologia dei testi a stampa, CUEC, 2008;
Lorenzo Baldacchini, Il libro antico, Carocci, 2001;
Lucien Febvre Henri-Jean Martin, L'apparition du livre, 1958;
Elizabeth L. Eisenstein, The printing revolution in early modern Europe, 1983;
Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy. The making of typographic man, 1962;
David McKitterick, Print, manuscript and the search of order, 1450-1830, 2003;
James Thorpe, Principles of textual criticism, 1972;
Philip Gaskell, A new introduction to bibliography, 1972;
Philip Gaskell, John Baskerville. A bibliography, 1959.
以上の作品は、あくまでも参考文献の一部にすぎず、今後も研究範囲を広げていく必要があるのは言うまでもない。例えば、研究計画でも言及した通り、近代小説の語りの手法における引用府の機能という問題がある。この点に関しては、西洋文学における句読法という領域に触れなければならない。現在この分野で役立ちそうな資料を探索しているので、来月のレポートで成果を報告するつもりである。
11月10日、ボローニャ大学芸術・音楽・演劇・映画学科で開催されたディスカッション「新能楽:不連続の連続」(Il nuovo nō: continuità di discontinuità)に出席した。ボローニャ大学のMatteo Casari先生と静岡文化芸術大学の土肥秀行先生が主催した。能楽の「シテ」としても知られる静岡文化芸術大学の梅若猶彦先生をはじめ、日本文学や演劇に携わる様々な研究者が参加した。その顔触れは多彩であった。Monique Arnaud先生は日本国外で唯一人の有資格師範として活躍している人で、ミラノに国際能楽協会(International Noh Institute)を開き、以前から能楽の実験的で活発な活動を行っている。平家物語のイタリア語訳を準備しているヴェネツィア大学教授のLidya Origlia先生は三島由紀夫が作った能について発表した。日本演劇のイタリア人研究者であるヴェネツィア大学のBonaventura Ruperti先生は明治時代以降日本で行われた能の近代的な試みを紹介した。
同じく10日には、"The Italian Restaurant"という梅若先生のオリジナル作品が演出された。この前衛主義的な能を上演するため、ボローニャ大学の学生たちが俳優として起用された。みなプロの俳優ではないものの、わずか5日間の準備とは思えない素晴らしいパフォーマンスを披露し、観衆から大きな評価をえていた。能のような代表的な日本の伝統芸能がどのように近代化されえるか、また一般的に日本の伝統的な演劇に馴染みがほとんどないイタリアの観客の前でどのように上演できるのか、といったことを観察できたのは、比較研究の視点でまたとない機会だった。