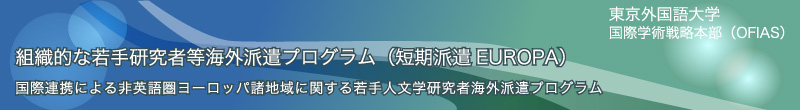2010年11月 月次レポート(平田 周 フランス)
短期派遣EUROPA月次レポート(11月)
平田 周
留学の長所の一つは、自らが専門とする国の知的状況に直接触れる機会が与えられることにあると思います。そうした知的状況との関わりで自らの研究を再考したり、あるいはそのなかでの自らの研究の位置を測る機会にもなります。
現在、今年の9月にパリ第八大学に提出した修士論文の第三章の部分をさらに発展させ、独立した日本語論文にすべく研究しています。第三章では、アンリ・ルフェーヴルやニコス・プーランツァスの「国家論」とミッシェル・フーコーやジル・ドゥルーズの「権力論」との関係を扱いました。論文では、1970年代後半のこれらの議論を取り上げなおしたいと考えています。
今回はこの論文で報告者が扱う年代と無関係ではない、フランスにおける「全体主義」や「アウシュヴィッツ」、そして、一見これらと関係ないように思われるポスト・モダンをめぐる言説について簡単に報告してみたいと思います。
フランスでは1970年代の中頃から、第二次世界大戦のレジスタンスによってそれまで広く大衆に支持されていたフランス共産党とそのマルクス主義の理論が凋落するにつれて、資本主義対共産主義という対立軸から、民主義対全体主義という対立軸へと言説がシフトしていきます。ソルジェニーツィンの『収容所群島』の仏訳が出版され、この著作はヨーロッパの国のなかでもとりわけフランスにおいて物議をかもしました。こうした対立軸の移行に大きな役割を果たしたのは、スターリニズムを早くから批判していたクロード・ルフォールと、彼自身は一緒にしてほしくないといいますが、ベルナール・アンリ=レヴィやアンドレ・グリュックスマンに代表される「ヌーヴォー・フィロゾーフ(新しい哲学者)」と呼ばれる一派です。
全体主義と一口にいってもナチズムのそれとスターリニズムのそれとは(ハンナ・アーレントは『全体主義の起源』のなかで、近代における〈収容所〉という場所の出現ということで同じカテゴリーに入れますが)、区別されるべきものであるように思われます。ナチズムによるユダヤ人の殲滅に関しての研究は、1950年代においては、ラウル・ヒルバーグやアレントらの少数の手になる研究を除いては極めて数が少ないものでした(彼ら・彼女らの研究はこの主題に関しては今なお欠かすことのできない文献です)。しかし、1970年代以降になると、「ホロコースト」に関する研究の量は膨大なものとなっていきます。
この点でアメリカの歴史学者ノーマン・G・フィンケルスタインの『ホロコースト産業』は興味深いものです。この著作は初版が出版された2001年にフランスのファブリック出版から仏訳されています。著者はナチス収容所からの生還者を両親に持つユダヤ人で、この著作では、ホロコーストにまつわる補償を自らの利権とするユダヤ人組織を告発し、スキャンダルなものになりました。彼の批判の対象ははっきりしています。それは、「ホロコースト」を、他の虐殺と比較にならない人類史における唯一無二の災厄とし、自らの行動を批判する相手を反ユダヤ主義と呼ぶことで、ホロコーストの表象を支配の言説として流通させるイスラエル及びアメリカのユダヤ人エリートです。こうした批判は、多くの批判を招きましたが、ヒルバーグやチョムスキーは彼を擁護しています。さて、このフィンケルスタインの主張にしたがえば、ホロコーストに関する文献は、はっきりと確定できるある時期から増大していきます。それは、1967年の第三次中東戦争以降、アメリカが自らの中東戦略においてイスラエルとの同盟関係を強めることで、アメリカのユダヤ人組織もイスラエルと緊密な関係を結んでいくことになる時期です。以後、「ホロコースト」の表象は、歴史研究に留まらず、地政学的な次元にも結びついていくことになるのです。
フランスの思想史の文脈では、ホロコーストの問題、「アウシュヴィッツ」の問題は、とりわけハイデガーのナチズムへの関与において取り上げられます。1987年に出版されたヴィクトル・ファリアスの『ハイデガーとナチズム』をきっかけとして、ジャック・デリダやフィリップ・ラクーラバルトがとりわけこの論争に加わりました。報告者の指導教官である西谷教授が『不死のワンダーランド』でこの問題を扱っています。報告者の側としては、ポスト・モダンの旗手とされるジャン・フランソワ・リオタールの1988年の著作『ハイデガーと「ユダヤ人」』に着目したいと思います。
リオタールのこの著作の中心問題は、なぜ西欧の哲学史における存在忘却を思考した哲学者が、ユダヤ人の殲滅に沈黙したのかというものです。この問いに対して、リオタールは、存在や忘却に対して、記憶しえぬものの他者の法の証言を対置することで答えます。
リオタールは、この記憶しえぬものの他者の法を「ユダヤ人juifs」の名で語り、ギリシャ-キリスト教に貫かれた西欧が、その無意識においてこの他者の法を抑圧し、忘却してきたといいます。この忘却は、表象のレベルでのユダヤの殲滅(アウシュヴィッツ)の記憶を喚起することでは解決されず(この点でリオタールはユダヤ人の殲滅の表象可能性を主題とするクロード・ランズマンの『ショアー』を評価します)、ユダヤの他者の法が示す「精神の悲惨、未完成なものに対する精神の隷属が、精神にとって本質的なものであることを証拠立て」ることで、償われるとリオタールは主張します。
ここにおける西欧の「精神」とは、リオタールにおいてはヘーゲルの弁証法の論理によって表現されるものです。ヘーゲルの世界史の論理において、戦争や暴力といった否定的契機は、より高次の目的の達成のために正当化可能なもの、つまり「和解」可能なものとして提示されます。しかし、リオタールは、「アウシュヴィッツ」の出来事はこのような西欧の合理性の目的[テロス]に回収できないものであり、「ユダヤ人」とは、そうした西欧のギリシャ-キリスト教的な「精神」が記憶しえなかった他者の法であると主張します。
こうしたアウシュヴィッツとハイデガーの関係についてのリオタールの考えは、1979年に出版された『ポスト・モダンの条件』の議論と重なるところがあります(余談として付け加えておくと、昨年はリオタールのこの著作が出版されてちょうど30年になり、報告者が通うパリ第八大学でもリオタールについてのシンポジウムが3日間にわたって開催されました)。「ポスト・モダン」というと、一般に戦後の消費社会に対応した時期区分として語られる傾向がありますが、リオタールにおいてはそのような時期区分そのものの失効として語られます。この著作では、ポスト・モダンとは、啓蒙やプロレタリアートの解放といった「大きな物語」の不信の表すものとして語られますが、こうした不信は、『ハイデガーと「ユダヤ人」』の論点から考えるならば、「アウシュヴィッツ」によってもたらされたものであるとはっきりと言うことができます。
それゆえ、文脈は異なりますが、ジャック・ランシエールは、芸術と政治の関係を考察する著作、『美学への不満』(2004年)のなかで、リオタールについて次のように述べています。「リオタールにおいて、ポストモデルヌは、決して芸術的かつ理論的な旗印ではなかったし、せいぜい記述的なカテゴリーや診断でしかなかった。そして、この診断は、本質的な機能をもった。その機能とは、芸術のモダニズムを政治的解放から切り離し、そのモダニズムを別の歴史物語に接続するために切り離すというものである。というのも、「大きな物語」や「絶対的な犠牲」への有名な嫌悪は、多文化主義的な優しい心を持った人々にとって大事な小さな物語の多様な世界に面しているものではまったくない。この診断は、「大きな物語」や「絶対的な犠牲」の純然たる変化であって、西洋の近代史を、プロレタリアートの解放ではなく、ユダヤ人の計画的な絶滅へと同化させるものなのである」。
ランシエールの議論の文脈では、リオタールの議論は、あらゆる政治的な企ては全体主義へと至るので、それに抗するために西欧の歴史が行き着いた「アウシュヴィッツ」という災厄を証言しなければならないというようにまとめられます。ランシエールは、このようなリオタールの議論が現代の言説空間において、「政治」から「倫理」への転回をしるしづけたとし、痛烈に批判します。
ランシエールの議論の文脈から離れても、アウシュヴィッツの出来事が西欧の歴史において特異なものであり、深刻な反省を迫るものであることは疑いがありません。しかし、いかなる「目的」にも還元できない「災厄」は、西洋の近代化の過程と切り離すことのできない植民地化の過程においても、ヒロシマ・ナガサキにおいても、ベトナム戦争においても、現代のパレスチナにおいても、ここで挙げることのできないほどの多くの事例にも当てはまります。フィンケルシュタインは先に挙げた本のなかで繰り返し比較の必要性を主張しました。出来事の固有性は比較なしにはありえません。そうした比較こそが、われわれが過去と向かい合い、われわれの共同体がいかに過去を共有するのかについて、真に考えるための条件なのだと思います。
最後に、話を現在報告者が進行中の作業に戻せば、こうしたアウシュヴィッツやポスト・モダンをめぐる言説が1980、90年代以降支配的になるのに対して、70年代後半に行われた国家論についての言説はあまり顧みられなくなりました。報告者は、こうしたコンテクストを踏まえた上で、新たにルフェーヴルの国家論を論じる必要性を考えたいと思います。