前ページに戻る
1997年度卒業論文
浜本若子
イズニック陶器にみえる中国陶器の影響
なお、事情により、卒業論文にあった注は掲載できませんでした。参考文献リストを参照ください。
- 第一章 序文
- 第二章 元・明時代の染付
- 第一節 染付陶磁器とは
- 第二節 元時代の染付(至正様式)
- 第三節 元末から明初頭期にかけての染付(洪武様式)
- 第四節 明初期の染付(永楽・宣徳様式)
- 第五節 明中期以降の染付
- 第三章 交易品としての染付とトプカプ宮殿の中国陶磁コレクション
- 第一節 東西交易ル−トと中国陶磁
- 第二節 東西交易が染付の生産に与えた影響
- 第三節 トプカプ宮殿コレクションと染付
- 第四章 イズニック染付陶器
- 第一節 イズニック陶器生産の歴史
- 第二節 イズニック陶器の様式の展開
- 第三節 中国の染付陶磁とイズニック染付
第一章 序文
世界の歴史に残る大帝国であったオスマン朝の遺物として多くの人々を魅了する、トプカプ宮殿やスルタン・アフメット・ジャミィ(通称ブル−・モスク)に代表される建築物を語るときに、それらの内部を装飾するイズニック陶器の美しさを無視することはできないであろう。オスマン朝の最初の首都であるブルサの近郊に位置するイズニックにおける陶器生産は、十五世紀後半から約二世紀間の短い期間ではあったが盛んに行なわれた。鮮やかな赤とブル−の対比が印象的な、独特の色彩を見せるものがその代表格として有名である。しかし、その有名な多彩陶器が登場する以前、オスマン朝下のイズニック陶器生産創始期には、中国の染付磁器からの強い影響が感じられる染付様式の陶器が多数造られていることが知られている。
中国の陶磁器生産は、八千年ほど前に土器が製造されてからの長い歴史の中で、常に高度な水準の生産技術を誇り、世界各地の陶磁器生産において先進的な役割を果たしてきた。その製品が時代を超えて、文化の違いを超えて多くの人々に愛されてきたことは周知の事実と言えよう。中国の陶磁器の模倣を通じて、あるいはその形態・彩色・文様からの触発によって、おもにユ−ラシア大陸の多くの地域でそれぞれの文化と結びついたオリジナルな陶磁器が発達してきた。しかし、生産の歴史や技術の面で中国が抜きんでてはいたものの、決して中国陶磁が他の文化圏に一方的な影響を及ぼしていたわけではないと思われるのが興味深いところである。特に西アジア・中東地域における陶器生産と中国陶磁の生産との関係については、地理的に近接しており古くから文化的交流・接触があること、交易のル−トが整っており貿易が行なわれてきたことを考えると、お互いが与えあう影響は小さいものではないことが容易に想像できる。オスマン朝における陶器生産もその例外ではない。
そこで、ここでは十五世紀後半から十六世紀にかけて多く生産された、染付様式のイズニック陶器を取り上げ、それらに影響を与えたと言われる中国の元・明時代の染付磁器と比較し、お互いの関係を検証する。中国陶磁がオスマン朝の陶器生産に与えた影響というものはどういうものであったのか、イズニック陶器はどのように中国陶磁の影響を消化し、後期のものに見られるオスマン朝的といえるオリジナリティを獲得していったのか。あるいは、イズニック陶器またはオスマン朝文化から中国陶磁へ影響を与えたということは考えられないか。以上のことを念頭に置いて考えていきたいと思う。
まず、染付とはどういった陶磁器であるか、中国における染付陶磁器の発生から発展の過程を第二章で概観する。第三章では、中国の陶磁器がオスマン朝へどのようにしてもたらされ、イズニック陶器に影響を与えうることとなったのかの鍵を握る東西交易について考察をし、世界でも屈指のコレクションを誇るトプカプ宮殿の中国陶磁コレクションの中の染付磁器についても言及する。そして、第四章でイズニック染付陶器の形・彩色・文様・材質等の面から特徴を見出し、関連性の見られる中国の染付磁器と比較する。イズニック陶器の様式の変遷の中で中国陶磁が及ぼした影響を考察し、イズニック陶器のオリジナリティがいかなるものなのかということを考えて結びとしたいと思う。
第二章 元・明時代の染付
第一節 染付陶磁器とは
染付とは、白磁の素地に酸化コバルトを主成分とする顔料で文様を描き、その上から透明釉をかけて摂氏千三百度程度の高温で焼き上げた、白地に青藍色の文様がくっきりと浮かび上がっている陶磁器である。ただ、この「染付」という言葉は日本における呼び名であり、中国語では「青花(チンホア)」、英語では「ブル−・アンド・ホワイト」と呼ばれるものである。「染付」という名称は、白地藍彩の焼物から染織の藍染を想起して付けられたものだと考えられている。本焼きの前に、透明釉の下(裏)に絵付けがなされる釉下彩技法の一種で、「釉裏青」と呼ばれることもある。ここでは、白地藍彩のものを陶器・磁器の区別なしに染付と呼ぶことにする。
染付の発生については、いまだに最終的な結論に至るような明確な論拠は示されておらず、諸説がわかれている。まず、誕生した時期は、唐・宋時代か、元時代前・中期か、元時代末か。どこの地域で誕生したのか。どのようなきっかけがあったのか。佐々木達夫氏は染付の起源に関する論点について、誕生の年代にはこだわらず、以下のように分類している。
A[中国国外の影響で誕生]
- イスラム世界から技術的影響を受けて景徳鎮で誕生
- イスラム世界から技術的影響を受けて景徳鎮ではない地域で誕生
B[中国国内の伝統技術から誕生]
- 景徳鎮内部の技術的発展で誕生
- 他地域(吉州窯説と磁州窯説)の技術的影響を受けて景徳鎮で誕生
- 景徳鎮ではない地域(一地域で、あるいは複数の地域で互いに無関係に)で誕生
白地にコバルトによる彩画が施された陶器は、九世紀頃からメソポタミアを中心とする西アジアのイスラム世界で作り始められ、十二世紀にはペルシアを中心に、染付と同様に透明釉下にコバルトで彩画された陶器が生産されていた。また、景徳鎮で元時代末期以降に盛んに製造された染付に使われたコバルトを含む顔料は、イスラム世界からのものであることを示唆するかように「回青(回回青ともいう)」と呼ばれ、成分もイスラム圏で産するものと類似している。A説のイスラム圏からの技術的影響の内容としては、このように類似する彩画の技法の面からの影響と、コバルトの原産地がペルシアであるという二点を根拠としている。
しかし、イスラムの陶器が中国陶磁に影響を与えるほど中国へ持ち込まれたという形跡はなく、器形や文様、成形や焼成の技術には類似点がほとんど見られないことから、イスラム世界からの影響には疑問もある。これまで最も主流を占めてきたのはBの1説であった。景徳鎮は宋・元時代に青白磁生産の中心地であり、元末から明にかけて中国最大の染付生産地であることから、景徳鎮内部で白磁生産技術から発展して、染付が生産されるようになったと考えることができる。景徳鎮の白磁生産技術の展開がきっかけとなったとする考え方が多くの学者によって示されている。しかし、白磁や青白磁から染め付けへの展開が曖昧にされている。Bの2説の考え方は、染付の生産が確認される以前に染付と同じ釉下彩技法が発達していた磁州窯あるいは吉州窯からの影響を景徳鎮の窯が受け、呈色材をコバルトに変えることで染付が誕生したというものである。しかしながら、この説を決定的とするような発見はされておらず、説明が十分であるとはいえない。最近の発掘調査による宋・元時代のものと見られる染付の発見は、Bの1・2説はあくまでも景徳鎮における染付の誕生を説明するものに過ぎず、中国の染付生産の開始を説明するものではないことを示している。これらの調査から、単独の地域で染付が誕生したのではなく、複数の地域で互いに無関係に誕生、あるいは偶然に発生したというBの3説の可能性が説かれる。
陶磁器の研究は、残された文献資料と陶磁器とを照らし合わせて確認するという作業から展開されてきたこともあり、染付に関して言えば、文献と遺品の多く残っている明時代の、特に宮廷用の陶磁器を生産した官窯の研究が最も進んでいる。異民族によって支配された元時代の陶磁器に関しては、文献や中国において元時代のものと判別できるような遺品があまり多く残されていないことから、長いこと「陶磁の暗黒時代」とまで言われていた。1929年にR・L・ホブソン氏によってロンドンのデイヴィッド財団に収蔵されている至正十一年(1451)の紀年が表わされている一対の染付青花龍文象耳瓶が紹介されたのが、元時代の染付陶磁器が確認された最初である。その後、1950年代にJ・A・ポ−プ氏によりイスタンブルのトプカプ宮殿と、イランのアルデビル寺院の収蔵品の中から、その染付龍文象耳瓶を基準作として文様・構成・描法を検討して一定のグル−プを検出した。この研究の成果を受けて、元時代に染付陶磁器の生産が行なわれていたことが確認されている。この染付龍文象耳瓶が、現在でも確認される最も古い染付陶磁器であるが、これを染付の出発点と見るにはあまりにも様式として完成度が高いことから、染付の発明は更に時代を遡ると一般的に考えられている。さきほども触れたように、釉裏彩の技法は古くから用いられ、晩唐時代には染付とは文様を描くのに用いられる顔料のみが異なる鉄絵が流行していたことから、晩唐時代以降ならいつでも染付誕生の可能性は考えられる。染付の発明がいつの時代かということについては、 先銘氏に代表される唐時代起源説、宋時代起源説などが唱えられてはいるが、現在は元時代に発明されたと見る考え方が主流であり、元時代のいつに発明されたのかが問題の焦点となっている。

<至正十一年(1451)染付青花龍文象耳瓶、デイヴィッド財団蔵>
ただ、いずれの説にしても細部にわたってはいまだに解明されておらず、推論に頼る部分が多く、信頼のおける新たな調査結果が待たれるところである。染付の誕生の時期・場所・きっかけ等については謎が多いのである。
本論文では、一定の特徴が認められている至正様式を元時代の染付として取り上げるところから、染付についての研究を始めることとする。
第二節 元時代の染付(至正様式)
先述の、デイウィッド財団に収蔵されている、至正十一年(1451)の紀年が表わされている染付龍文象耳瓶を基準としてJ・A・ポ−プ氏によって検出された、一連の元染付のグル−プは、至正様式とも呼ばれている。前説でも述べたように、元染付の編年は確立されておらず、元染付と考えられている陶磁器の全てがこのグル−プに属するものであると確定されたわけではないが、ここでは元染付=至正様式として取り上げることとする。

<元時代の染付の作品>
元染付の主な特徴としては、装飾が非常に華美であること、大型の作品が多いことが上げられる。元時代の染付は中国国内においてはあまり高い評価を得ておらず、むしろ西方の各地の有力者に愛好され、さきほどにも述べたように中国国内より、他国で多く確認されている。トルコのトプカプ宮殿コレクションや、イランのアルデビル寺院コレクションなどがそうである。中国国内においては、青磁・白磁のほうがより高い評価を得てきており、染付は俗なものと見なされてきたことも、資料の不足とともに染付についての研究の発展を妨げてきた原因と指摘されている。元染付の作品の多くは、輸出品として生産されたことはほぼ間違いがなく、そのことが元染付陶磁の特徴に大きな影響を及ぼしていると考えられる。なお、貿易陶磁としての元染付陶磁については、後の第三章で詳しく触れることとする。ここではまず、元染付の文様の特徴を見る。
元染付に特徴的に見られる文様としては、次の四つのものが上げられる。
- 魚藻文 魚が蓮池や藻の中を泳ぐ姿を写実的に描いたものである。この文様が持つ著しい写実性は、陶工達が絵付けに熟練したこと、コバルト顔料によって色彩の濃淡を表現できるようになったことによって可能になったと言われている。斉藤菊太郎氏の研究によれば、この図柄は陶磁の中国江南地方に流行していた絵画のの中の一ジャンルに含まれるもので、景徳鎮の絵付けはその影響を受けているということである。
- 人物文 元時代の染付に表わされる人物文様のほとんどは、元時代に流行した元曲という雑劇から取材されたものであるということが、斎藤氏の研究によって知られている。
- 八宝文 八宝とはラマ教の教説でめでたいものとされている八種の宝物で、法螺・法輪・宝傘・白蓋・蓮花・宝瓶・双魚・盤長のことであるが、元染付には雑宝といわれる珠・銭・陰陽板・珊瑚・丁子・火炎宝珠などが多用されている。この文様は主文様としてよりも、先端を尖らせたラマ式蓮弁文の中に描かれることが多い。
- 如意頭文西方の金属器デザインの影響が強く見られるアラベスク風の文様で、主文様としてではなく、他の文様と組み込んだ形で使われる文様である。白磁にコバルトによる鮮やかな青藍色で力強く文様が描かれ、その意匠はイスラム世界の影響を伺わせるものである。西方イスラム世界的な部分と漢民族的部分が混ぜあわされたような図柄が非常に印象的である。
次に、元染付の器形の特徴について考察する。まず、実際にどのような形のものがあるか。以下のように分類した。
- 大型のもの 酒会壺・扁壺・冥瓶・瓢形瓶・平縁または稜花の縁を持つ盤など。
- 中型のもの 玉壺春瓶・水注・鉢など。
- 小型のもの 高足杯・い・杯と托・皿など。
先にも述べたように、元染付陶磁には大型の作品が多い。景徳鎮窯だけでなく、竜泉窯や磁州窯などでも大型のものが多く生産されており、この時代に通じての特徴のようである。このことを説明する見解としては、元王朝の支配者たるモンゴル系民族の嗜好によると言うものと、西方のイスラム諸国からの注文を受けて作られたことによるとするものがある。元染付が貿易陶磁としての性格を持ち、実際に西方のイスラム諸国に多く残されているということを考慮すれば、単に元王朝の嗜好という理由にとどまるものではないと考えられる。
第三節 元末から明初頭期にかけての染付(洪武様式)
元染付の編年研究の先駆者であるJ・A・ポ−プ氏は、元染付(至正様式)と、永楽・宣徳様式と認識されている明初期の染付との中間点に位置する作品群の存在を推定した。至正様式と永楽・宣徳様式の双方の特徴をあわせ持ち、しかもどちらにも属さない、洪武様式と現在呼ばれているものがそれである。
 <洪武期の作品>
<洪武期の作品>
洪武様式作品の特徴としてはまず、他の時期のものと比べて、著しく青藍色の発色の鮮やかさが劣っているということが上げられる。やや黒ずみ、淡い色合いである。元末期の社会的動乱の影響で、主にコバルトを産する西方との交易が滞ったことにより、良質のコバルトを入手しにくくなったためと考えられる。そして、いずれのものもやや厚手で、素地の露われている底裏の部分は赤みを帯びており、きめが粗く黒褐色の斑点が現われ、胎土に不純物が多く含まれていることがわかる。
文様については、元時代至正様式の唐草文がほぼそのままの形で使われ、蓮華・牡丹・菊のような植物文が多用される。また、鉢の口辺に波濤文が表わされること、蓮弁の中に花文がはめこんであること、高台や内側に雷文繋ぎのあることが特色としてあげられる。中心をなす主文様にも植物文が用いられるが、この前後の至正様式や永楽・宣徳様式には多く見られる龍・鳳凰・鳥・魚などの動物文や、植物文の中でも葡萄・瓜は登場しない。元時代に多用された西方世界的なモチ−フが見られないという点が興味深い。
器形については、そもそも洪武様式とされている作品の数が少ないので、今後の研究によって種類が変わってくる可能性はある。現在まででは、玉壺春瓶・水注・ケンディ・梅瓶・大壺・大盤・稜花盤・皿・托と杯・大鉢・碗の形のものが確認されている。
第四節 明初期の染付(永楽・宣徳様式)
中国の染付の中でこれまで最も高い評価を受けてきたのが、この永楽・宣徳時代の作品であり、染付の黄金時代と言われている。なぜここで永楽染付と宣徳染付を一括して論じるかと言えば、この二つの時代の作品群を明確に分類することが困難だからである。「永楽」銘の入った作品も確認されてはいるが、宣徳時代の作品は官窯のものであってもほとんど無銘である。宣徳時代の作品には、「大明宣徳年製」の銘が書き込まれている。しかし、無銘であれば永楽時代のものかというとそうではなく、無銘であっても宣徳官窯の作品と考えられるものもある。官窯の製品に銘が書き込まれるようになったのは、宣徳期に入ってしばらく経ってからのようである。それぞれの時期の染付陶磁器の持つ特徴も大きな隔たりはなく、永楽から宣徳へかけて非常に洗練された優美な様式が展開された。永楽帝期から宣徳帝期にかけての明王朝の繁栄を示唆するものであろうか、顔料のコバルトも良質のものが手に入るようになったようであり、或いは中国産のものを扱うようになりその技術が向上したのか、藍の発色は洪武様式のものに比べて鮮やかである。


<永楽期の作品>
永楽様式の特徴としては、まず藍と白のコントラストが元や洪武の作品と比べて、より鮮明になったということが言えよう。先述のように顔料が良質になったことに加え、素地をなす白磁の質が高くなったことも貢献している。この時期の官窯の体制については明確ではないが、永楽期に作られた有力者の墓趾から出土した作品には白磁が多く、「永楽年製」の銘を持つものも主として白磁であり、景徳鎮で優れた白磁が生産されたことはほぼ間違いがない。その白磁は、甜白という名称を与えられた格別なもので、きめのこまやかな、艶やかな白地が比類の無い美しいものである。
文様には、草花文が多く見られ、龍・鳥を除いては動物文がかなり減少している。元時代に多く見られた鳳凰文、麒麟や魚藻図があまり登場しなくなる。牡丹・蓮華・薔薇・宝草華・山茶花・菊・霊芝・撫子・朝顔・梔子などの多様な四季花を混ぜた、丸みを帯びた転回の蔓をなす唐草文がよく見られる。また、果実折枝文が配置されることも多く、長寿吉祥を表わす桃・石榴・葡萄・枇杷・霊芝・桜桃・蘋果(リンゴ)等が組み合わせてある。波濤文は元時代の特徴的なS字形の迫力のある曲線から、より写実的なものになり、やがて装飾化していく。元時代によく見られた如意頭文もほとんど見られない。蓮弁文は、元時代の力強さを感じさせるものから、丸みを帯びたなごやかなものになっている。白地と文様のバランスが良く、余白を生かした絵画的なものが多く見られる。
器形では、盤と呼ばれる深めの大皿が多く、大きさは元時代のものを遙かに上回る径六十センチほどのものがあり、当時の焼成技術の高さがうかがわれる。元時代のものからさらに形のバリエ−ションは増え、それまで作られていた形のものに加えて、水注や盤、燈下台に西方イスラム世界(特にペルシア)の金属器をかたどったものが現われる。
宣徳様式は、まさに染付黄金期のものとして礼賛されてきたものである。永楽様式を受け継ぎながら、より洗練させたものだと考えられている。ただ、宣徳様式をもって染め付け生産の極致とする考え方は、元から明初期の作品についての研究が進むにつれて見直されてきている。宣徳様式の作品への永楽様式からの変化・展開が把握しにくく、どちらの様式とも判別しがたい作品も多いが、多少の違いはある。染付の青藍色の色合いがやや明るくなり、全体として繊細・緻密で端正な印象を与える。文様も、器形も大きな変化は見られない。器形の面から考えると、小品に優れたものが多く、大きな形のものが減る。そして、それまでは白磁や色釉磁器にのみ見られ、染め付けには使われることがなかった文様の型押し技法が、碗や皿の白磁の部分に使用されるようになった。文様の傾向は、永楽時代の絵画的なものから、より図案的な方向へ向かう。

<宣徳期の作品>
この時期の染付の多くも貿易品として生産されたことが、中国国外のコレクションに残された作品の多さでわかる。しかし、この明初期の貿易はいわゆる朝貢貿易であった。元時代の染付陶磁器の様式がイスラム世界の王朝の嗜好を反映したと思われるのに対して、明初期時代の永楽・宣徳陶磁器はイスラム世界の嗜好を反映したと言うよりは、むしろ元時代の様式をある程度受け継いだもので、直接に彼らの嗜好が反映されたとは言えない。もちろん需要する側の嗜好を取り入れていないわけではないが、とくに「イスラム風」に近づけようと努力はしていないように受けとられる。永楽・宣徳様式が初期のイズニック染付に与えた影響は後の第四章で詳しく論ずるが、イズニック染付の作品の中で、明らかに永楽・宣徳染付を模倣したとわかるものが見られるというのは非常に興味深い事実である。
第五節 明中期以降の染付
永楽・宣徳期に非常に質に高い染付が作られ、官窯における染付生産が降盛していたのに比べ、これに続く正統・景泰・天順の時期には、官窯銘を持つ作品が残っておらず、官窯の低迷期と言われている。官窯でまったく生産が行なわれなかったわけではないが、幼年で帝位を継いだ正統帝以後の明王朝の混乱を反映するかのように、陶磁器の生産ははかばかしくなかったようである。これらの時期の作品として確認できるものに、蓮華唐草文や花折枝文、八宝文の描かれた蓋付きの壺がある。また、人物文の背景に雲や建物が描かれた雲堂手の文様が施された一群の壺の作品がある。民窯のものか官窯のものか定かではないが、明初期からの民窯における生産の流れを汲むものと考えられている。
 <成化期の作品>
<成化期の作品>
成化期には、貿易品を含めてかなり大量の生産が再び行なわれたという文献が残っているようであるが、実際には遺品は少ない。この時期の作品の評価は非常に高いが、幻の焼物としての希少価値も含まれるからであろう。とは言うものの、染付の作品自体も宣徳時代に次いで質の高いものであると言われている。胎土は薄く成形は緻密で、素地の白磁は永楽白磁に称される甜白のものと遜色の無い、釉の滑らかな美しいものである。文様は、余白を生かし主文様を大きくとる、永楽・宣徳期の意匠を受け継いでいる。ただ、この時期の青藍色の色調は永楽・宣徳期に比べ、ややくすんだものか、淡いものである。三杉氏は、これらの作品に使われている顔料の産地が、中国国内のものであろうと推測している。ところで、成化官窯を代表するのは、この時期に完成した豆彩とも呼ばれる五彩磁器とされる。この時期以降、景徳鎮の生産において、染付の地位は五彩に次ぐものとされ、中国における染付生産の降盛はひとつの帰結を見たと言えるであろう。
 <弘治期の作品>
<弘治期の作品>
弘治の時代には、前代の官窯における余りにも大量な生産によって、工人達やひいては景徳鎮社会全体の疲弊を招いたことから、官窯の生産が抑えられたと伝えられている。このため、この時期の作品は成化様式をそのまま受け継ぎ、新たな展開を見せることはなかったようである。弘治に次ぐ正徳期にも官窯の生産は盛んではなく、「大明正徳製」銘の記された作品にアラビア文字を文様化したものがあることから、この時期にアラビア文字の文様化が行なわれるようになったと考えられている以外には、特に目立つような変化は見られない。成化期以降、色彩的なものが流行し始めた影響か、弘治から正徳にかけて黄地の染付が見られるようになった。この時期あたりから、染付陶磁器に多彩のものが多く生産されるようになってきて、やがていわゆる白地藍彩のものに取って変わっていくのである。


<正徳期の作品>
嘉靖時代には、景徳鎮では安定した生産が長期にわたって行なわれる。この時期から、官塔民焼制と呼ばれる民窯への委託焼成が行なわれるようになった。その結果、官窯の技術が民窯に伝わり、民窯の技術が向上した。国力の回復を反映してか、再びコバルトの輸入が始まり、菫青色と呼ばれる紫がかった明るい藍色になる。磁器の輸出量も増えた。文様も端正で緻密なものから、自由で伸びやかなものになっていく。先述のように、成化時代から兆しが見られた多彩陶磁の流行もあってか、余白を効果的に使うよりも、文様で描きつぶすような傾向が強くなっていく。降慶・万暦の時代を経て明王朝下における官窯の生産は幕を閉じ、清の時代にまた再開される。染付は生産され続けるが、厳密に言うところのブル−・アンド・ホワイトの時代は終わりを告げるのである。
 <嘉靖期の作品>
<嘉靖期の作品>
第三章 交易品としての染付とトプカプ宮殿の中国陶磁コレクション
第一節 東西交易ル−トと中国陶磁
シルク・ロ−ドの名で古くから知られている、中国を中心とする東アジア世界と西アジアのいわゆるオリエント世界との間の交渉の歴史は、紀元前二千年期まで遡ることができる。西方にアケメネス朝・ヘレニズム世界・ロ−マ帝国、東方に秦・漢帝国、南方にマウリア朝・クシャ−ナ朝が起こり、高度な文化を誇り栄えた紀元前一千年期には往来も活発化し、陸上交易ル−トが整ったと考えられている。この陸上交易ル−トが、十九世紀になってドイツの地質学者リヒトフォ−ヘン氏によってザイデンシュトラ−セン(絹の道、シルク・ロ−ド)と名付けられた
。現代になってこの呼称が広く普及したことから、東西交易の主ル−トと考えられがちであるが、この時期には海路による貿易も活発に行なわれている。初期文明の中心地であったインダスとメソポタミアとの交易も、アラビア海からペルシア湾に入り、海路を辿ってきたであろうということが、インダス文明の担い手であったハラッパ人の使った印章がメソポタミア各地や、ペルシア湾のバ−レ−ン島でみつかっていることから考えられている。前漢の武帝の時代(前
141−87)には、海路インドに至る交易路が利用されるようになり、インドを介して中国の絹や黄金とロ−マ帝国のガラス製品などがやりとりされた。その後、二世紀の中期には、ロ−マ帝国と中国とを結ぶ海路が開かれ、両帝国の直接の交易も実現している。いわゆる東方世界と西方世界との間の物資の流れを見ると、陸路が時として政治状勢の影響で不安定となることもあったのに対し、海路の往来は、それぞれの地域で王朝が交替したり、ロ−マ帝国が分裂した(
396)時にも活発であった。
七世紀に、イスラ−ム帝国であるウマイヤ朝(661−750)が出現し、その後のアッバ−ス朝以下のイスラ−ム帝国は貿易を重視したため、この時代に陸路・海路ともに交通路は整備され、交易はますます盛んになった。西アジア・南アジアから中国へ多くの人々が訪れたことを示唆する文献も残っている。さらに時代は下って九−十世紀には、中国産の陶磁器が主要な貿易用の商品として取り扱われるようになった。この頃、波に強い竜骨船が開発されたり、羅針盤が利用されるようになるなど航海術が発達したこと、中央アジア方面の政情が不安定であったことから考えて、海路による交易はいっそう盛んになったと考えられる。河北省の窯白磁・定窯白磁、 江省の越窯青磁、湖南省の長沙銅官窯磁、広東省産の緑褐釉磁・褐黒釉磁・白磁などの陶磁器が輸出されていたが、アジア各地で発見されている。イランでも、九−十世紀に貿易港として栄えたペルシア湾岸のシ−ラ−フの遺跡から、前述の中国陶磁が発見されている。また、内陸のニシャプ−ルやサマッラなどでも同様のものが見つかっており、ペルシア湾岸の港から陸揚げされて、そこから陸路運ばれたものだと考えられている。
十二世紀頃から、莫大な量の青磁・白磁が輸出され、エジプトにおいてもフスタ−トを始めとする当時の都市の遺跡から、非常に質の良い宋・元時代の中国陶磁が多数出土している。そのことからも、中世の東西交易において陶磁器がいかに重要な商品であったかがうかがわれる。
十三世紀後半に元の時代に入り、広大な領土を掌中に納めたモンゴル帝国の支配下において、交易はますます盛んになった。元王朝下の中国において、貿易商品として台頭してきたのが、染付陶磁器である。元染付は中国国内では伝世品として遺されている作品は少なく、発見された数はごく僅かである。しかし、東南アジアや西アジア地域では数多く発見されている。フィリピン、インドネシア、タイなどの東南アジア地域で発見された作品は、中国風の中型の日用品や小型の儀礼洋品が多いのに比べて、イスラ−ム系王朝の栄えた西アジア地域や南アジアのインドのイスラ−ム系の有力者のコレクションに見られる作品は、至正様式の大型のものが多く、中型・小型のものは少ない。ミニアチュ−ルの中の食事風景を描いたものを見ると、大型の食器を人々が囲んでいる様子が表わされていることからも西アジア地域の人々が大型の陶磁器を欲し、その需要に応えて大型の作品が生産されたと推察される。
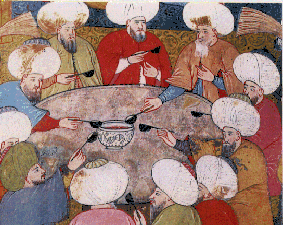 <アフメト三世のス−ルナ−メより(Levni画)>
<アフメト三世のス−ルナ−メより(Levni画)>
しかし、大きなものでは径四十センチ、重さは一つ十キロを下らないであろうそれらの至正様式染付を、遙か西方の地域までいかにして運んだのか。イランやエジプトまで大量にもたらされた作品のほとんどが、陸路をキャラバンの荷としてラクダの背に積まれて運ばれたとは考えにくい。大量に輸送できる船に積まれて海路を辿ったと考えるのが適当である。そして、そのことを裏づけるように、ペルシア湾岸の港ホルムズや紅海岸の港アイザ−ブなどを代表とする南海やインド洋の沿岸地域の遺跡から、相当数の元染付片が出土している。
明朝時代(十四世紀後半から十七世紀半ば)になると、中国とその他の国々との間の貿易は、明朝に対する朝貢貿易という形で行なわれた。つまり、朝貢品を携えた使節に対して、明朝がそれらの使節に対して特産品を与えるという形をとった。明朝の中期までこの体制は続き、西アジア方面からやってきたイスラム商人が自由に活躍した元時代とは異なった性格を持つ交易が行なわれた。諸外国の国王が明朝の皇帝に送る外交文書である「表文」と、明朝が諸外国の各船につき一枚づつ与えた「勘合」との両方を持った朝貢者以外を認めず、自由貿易を制限した。永楽帝の時代には積極的な対外政策が取られたこともあり、永楽帝が宦官の鄭和に命じて大海事遠征を行なわせ、この時代から、鄭和が訪れたより多くの国々との間に朝貢関係が結ばれた。西洋取宝船とも呼ばれるこの遠征の目的は、明王朝の勢力を諸外国に示し、国威を宣揚しようということであったようである。だが、交易が元王朝時代のように自由に行なわれなかったとは言っても、決して交易自体は衰えたわけではなく、明時代の染付を始めとする陶磁器は、かなりの数の作品が諸外国へもたらされ、西アジア・中東地域の遺跡や、現在も残るトプカプやアルデビルのコレクションに数多く遺されている。このことから、明王朝が諸外国との交易に力を入れていたことが伺える。三杉氏は、この遠征は単に明王朝の力を見せつけるためだけではなく、貿易を管理する宮廷に大きな利益をもたらす官業貿易を強力に推し進めようという意図が働いてのことであろうという解釈を述べている。そして、景徳鎮に官窯がおかれて明王朝のバックアップの下に栄えたことが、永楽時代に景徳鎮で生産される陶磁器の質・量の急激な向上を導いたのではないかと述べ、鄭和の海事大遠征の、陶磁貿易史上における意味を評価している
。鄭和の遠征は、永楽帝から宣徳帝の時代にかけて(1405−1433の二十二年間)、七回にわたって行なわれ、東南アジア各地を始め、南海を横切って、セイロン、インド南岸のカリカットを経由し、更にインド洋を横切って、ペルシア湾岸のホルムズ、アデンを経由して紅海に入りメッカにも達し、またモルヂブ諸島を経てアフリカ大陸東岸のモガディシュやマリンディにまで到達している。やはり、このル−トが明時代の交易の基盤をなすものと考えられることから、明時代の陶磁器もほぼ鄭和の海事遠征ル−トを辿るものであると考えられる。
十六世紀に入り、明朝の海禁令を侵して海外に密航した中国人海賊が中心となり、明王朝との通商を断わられたポルトガル人や、「寧波争貢事件」を契機に朝貢貿易の統制が強化された日本人や、福建・ 江・広東の沿海地方の中国人らが結託して、大規模な密貿易が行なわれた。明朝政府は嘉靖二十七年に、この大掛かりな密貿易を取り締まろうとしたが、この密貿易によって利益を上げていた沿海地方の人々の強い反感を買うなどして、成果を上げることはできなかった。この後十年にわたって、中国人海賊や密貿易者達が活躍し、大倭 時代と呼ばれた。この時代の陶磁器の多くは、彼らの密貿易によって各地へもたらされたと考えられる。しかしその後、海禁政策に対する批判が高まってきたこともあって、降慶元年に廃止され、 州月港が一定の条件の下に開放されることとなった。十六世紀以降、明・清の陶磁器はイスラ−ム商人の手を経ずに、ポルトガル商人やスペイン商人によって、直接ヨ−ロッパへもたらされるようになった。ポルトガル商人達はマカオに拠点を置き、インド洋を横切り、喜望峰を回ってアフリカ大陸を迂回してヨ−ロッパへ到達するル−トを利用するようになった。スペイン商人達は、植民地となったフィリピンに拠点をおいて中国陶磁を得、ポルトガルやイギリス、オランダなど海の覇権を狙う他のヨ−ロッパ国との対抗関係の中で、太平洋を横断して新大陸のメキシコを経由するル−トを開いた。
十七世紀の初頭、オランダ東インド会社が発足した。十六世紀末からオランダ商人達はバタビアに商館を次々と構え、中国の陶磁器を取り扱うようになった。オランダ東インド会社の取り扱った中国陶磁の数は膨大なものであったことがわかっている。染付を全ヨ−ロッパに広め、中国以外の国々での染付生産の普及に一役買い、世界の染付史に大きく貢献したのが彼らなのである。十七世紀前半期に、オランダと中国の磁器交易の中心地はバタビアより中国本土に近い台湾に移され、台湾が中継地として栄えた。しかし、十七世紀半ばに、明朝が滅んで清朝が満州族によって建国され、明朝の重臣の鄭成功が台湾を根拠地として反乱を起こした。台湾の政情が不安定になったので、オランダはその後、日本の長崎に交易の中心を移し、当時、鎖国政策を取っていた江戸時代の日本との貿易を行ない、中国の芙蓉手の磁器をもたらすなどして、日本の陶磁生産にも大きな影響を与えた。
明王朝が滅亡して清王朝の時代に入ったが、王朝交替後すぐには良質な陶磁器が大量に生産されることはなかった。その間、学者によって区切り方は異なるが、一番長いもので、明の万暦帝の後即位して一か月で泰昌帝が亡くなった1620年から康煕二十一年までの約六十年間は、中国磁器の輸出低迷期であるとされている。康煕帝の時代の中期になってから、上質な陶磁器が再び生産されるようになり、清朝時代に作られた陶磁器の中でこの康煕帝期のものが最も多く輸出されている。清朝時代には、ヨ−ロッパ・アメリカの各地に非常にたくさんの、バラエティにとんだ中国の陶磁器が運ばれている。しかしそれらのうちの多くはヨ−ロッパの人々の嗜好を反映していて、如何にも彼らの注文に応えて作られたという印象を与える、形やデザインに中国の伝統性を感じさせないものや、ことに色彩の華やかなものが多い。元時代から貿易品として取り扱われてきた染付は、この時代から色彩的なものに押されて、影が薄くなってくるのである。
こうして東西交易の歴史を俯観すると、シルク・ロ−ドと呼ばれて親しまれている陸路の印象に隠れがちであるが、こと陶磁器に関して、海路交易の重要性が陸路のそれを凌ぐものであることがわかる。この海路のことを、主に陶磁器貿易との強い関連性から三上氏は「陶磁の道」
と呼び、三杉氏は陸路と対応させて「海のシルク・ロ−ド」
と呼んでいる。中国で生産された陶磁器の中で最も貿易品として普及し、世界各地の陶磁器生産に影響を与えた染付の生産・発展の歴史は、この海路貿易の歴史が背景となっていると考えて差し支えないであろう。
第二節 東西交易が染付の生産に与えた影響
染付がいったいいつ、どこで発生したのかという点については明確な結論に至っておらず、様々な推測が研究家によってなされているということは、第二章の始めで述べた通りである。染付が交易品として台頭してくるのは元時代後半期以降のことであるが、宋から元にかけての時代には龍泉窯青磁が主な交易品であった。このことは、韓国新安沖で発見された交易船
の積荷の主なものが、龍泉窯青磁や景徳鎮の白磁であったことからもわかっている。
それでは、染付はいかにして青磁に取って替わり、貿易陶磁として主流をなすようになっていったのか。三杉氏は、交易の主な担い手であった中東イスラ−ムの商人を通じて、交易の相手であった中東の人々の嗜好が反映された結果ではないかと述べている
。まず第一に、青磁と染付を比べてみた場合、より絵画的で図案・文様が鮮明にくっきりと描かれている染付のほうが、彼らの美意識に強く訴えてくるものがあったのではないかと述べている。中国人には九つの「徳」を有する玉への信仰にも似た憧れがあり、玉を持つことでその徳に与かることができるという考え方があった。そもそも青磁は、玉への憧れが反映されて、人造の玉を生み出そうとしたことに端を発している。しかし、そのような考え方を持たない中東・西アジア地域の人々にとっては、彼らの嗜好により近い、装飾の華やかな染付のほうが魅力的であったと考えられる。実際、輸出品として生産された青磁の多くも、時代が下るにつれて貼花技法による浮彫りや片彫りのものが多くなり、より装飾的であることからも、彼らの好みがうかがわれる。第二に、青磁がかなり長い期間、交易品として取り扱われてきた結果、中東に広く青磁がもたらされて珍しさが薄れ、より新しくて魅力的な商品が求められるようになったことがあるのではないかと述べている。エジプトのフスタ−トの遺跡から発見された越州窯青磁は十世紀前後のものであると推測され、それから元の時代まで四世紀にわたって、大量の青磁が中東にもたらされたと考えられるからである。青磁に替わる、新しい交易用の陶磁器として染付がブ−ムになった背景には、中東・西アジア方面の商人達の影響が大きいと考えられる。トプカプ宮殿コレクションの染付の中には、茘枝の折枝文、蓮池文、葡萄文など、青磁の釉下に施されたのと同様の文様を施されたものがある。中東や西アジア方面へ陶磁器をもたらした商人達のコントロ−ルが陶磁器の生産活動に及び、青磁を主に作っていた龍泉窯と染付生産の中心地となる景徳鎮との間で工人の移動が行なわれた可能性を指摘している。
元時代から明・清時代にかけての染付生産の流れは第二章で概観した通りであるが、それぞれの時代に作られた染付の様式に、交易はどのような影響を与えたのであろうか。
元・至正様式の染付は、青磁や白磁などのモノ・カラ−の陶磁器と比べてみると、白と藍とのコントラストを作り上げている文様が非常に大胆な構図を取り、豪華絢爛な印象を与える。宋時代に最も盛んに造られた青磁・白磁が繊細・優雅な印象を与え、いかにも中国の知識人達に好まれたであろうと思われるのに対し、百八十度ほども違うタイプのものである。その意匠には、中東イスラ−ム地域で生産されてきた金属器の形・文様の影響がうかがわれる。器面をいくつかの同心円などに分割し、密度の濃い文様を施している点に、中東・西アジア的な要素が見られる。元の支配者層というのはモンゴル系の民族である。彼らは中国に本拠地を定め、東アジアから中央アジアにかけての広い地域を支配した。この時代にはジャムチと呼ばれる駅伝制度が整備されて陸路は安定し、貿易港には中東イスラ−ム地域からの商人など外国から多くの人々がやってきて滞在し、活発に交易活動を行ない、海路・陸路共に交易も盛んであった。この元王朝時代に、西アジア・中東方面の文化が育んできた美意識が、交易用とは言えども中国の陶磁器に取り入れられるようになったというのは非常に興味深いところである。単に交易用として中東地域の人々の好みに応える陶磁器を造らせただけなのではなく、もともと彼らは古くから西方の文化に親しみ、積極的に中東地域のイスラ−ム文化と接触しようとした痕跡をここに残したとも考えられないだろうか。ただ、南・東南アジア地域では中東向けのものとは異なった元時代の染付が発見されていることもあり、染付陶磁器がまったく中東方面のみを意識して造られたものではないことを示している。この時代の染付陶磁器は交易によって、より広範な地域に広まったものと考えられる。
明の時代に入ると、交易は朝貢貿易の形を取り、元時代のように西方諸国の注文に応えて陶磁器が造られるということはなかったようである。しかし、元時代の景徳鎮で形成された交易用の染付生産の流れが絶たれたというわけではない。朝貢に応じて明の特産品を与えるという尊大な交易の方法ではあったが、実際には相手国の嗜好をまったく無視したものではないと思われる。しかし、永楽・宣徳様式の染付は至正様式に見られた力強さ、連続的な文様でぎっしりと埋め尽くすような装飾性をやや抑え、より写実的・絵画的な文様の使い方をし、洗練された印象を与える。西方的な要素は唐草文の使い方や大型の器形に残されているが、陶磁器全体が醸し出す雰囲気は西方のイスラ−ム世界的と言うよりは中国的である。明の時代から宮廷の需要に専ら応えるための官窯の制度が整備され、染付は官窯で生産されるようになり、単に交易用としてだけではなく宮廷でも使われるようになった。明初期の永楽・宣徳時代の染付には、中国人がそれまでの交易用陶磁の生産の伝統を生かして西方イスラ−ム的な雰囲気をなぞってつくった、中国人のエキゾチシズムとでもいうものが感じられるのである。
その後、明後期に及んで、朝貢貿易が廃止され、欧米諸国からの需要・注文も染付の生産に大きく関わってくる。この時代から清の時代の染付の生産には、注文に応えるという要素が大きくなってきて、欧米諸国の東洋趣味を満たすということを主眼として造られるものが多くなってくる。しかし、染付はこの時代には交易品の主流をなすものではなくなってきており、その地位はやがて多彩のものに変わっていった。多彩のものに押されるようにして、染付生産は続けられるものの、その作品には元時代や明初期時代に造られたものに見られるような挑戦的・進取的な風合いが薄れていくように見受けられるのである。
どの時代も中国の陶磁器は、行く先々で高価で貴重な品として取り扱われ、権力を持つ人々に愛された。染付はその典型的なものである。依然解明されていないことは多いが、染付は交易を通して古今東西の様々な文化を吸収してそれを反映し、さらに交易によって各地にもたらされて様々な地域の陶磁器生産に影響を与えた、文化・文明の交流を映す鏡としての側面を持った陶磁器なのである。
第三節 トプカプ宮殿コレクションと染付
西アジアに大帝国を築いたオスマン朝の栄華のほどをしのばせる、陶磁器の大コレクションがイスタンブルのトプカプ宮殿(現在は博物館)に遺されている。なかでも、保有する中国陶磁を含む東洋陶磁の質、約八千から一万点前後である
と言われているその膨大な収蔵量は世界でも名だたるものである。このコレクションを最初に整理・分類したのはドイツの中国陶磁学者エルンスト・チンメルマンである。彼は1910年にメフメト五世から依頼されて調査を始め、その後バルカン戦争が起こって調査を一旦中止したが、共和国が成立し、トプカプ宮殿が博物館となった後に館長のハリル・エドヘム氏から依頼を受けて調査を再開し、1925年から1927年にかけて分類を終えた。この調査の結果、1930年には最初のカタログ
が発行された。
このコレクションの内容は、J・A・ポ−プ氏によると
、十四世紀以降の元・明時代の青磁が一番多く、その他に染付・白磁・黄磁・藍磁・金欄手を含む五彩(赤絵)・黄地紅彩磁・褐釉白盛上磁(柿南京)などである。
この時代、様式ともにバラエティに富んだコレクションは、購入によるだけではなく、他の王朝からの献上品であったり、攻略の際に戦利品として略奪するなどの様々な手段によってコレクションに加えられている。ポ−プ氏によると、什物収蔵記録が残っており、1495年の弟二号目録から陶磁に関する記載が登場するということである。そして、バヤズィット二世治世下(1481−1512)の1501年の第三号目録から中国陶磁に関する記載が見られる。収蔵の経緯については、三上氏は十四世紀の元時代のものから十五世紀初期の明初のもののグル−プと、十六世紀の明中期以降のグル−プに分けて考えるのが適当であるとしている
。十四世紀から十五世紀の始めにかけては、オスマン朝はまだアナトリアの一君侯国に過ぎず、とくに十五世紀の始めにはティム−ル帝国に国家の大部分を占領され存亡も定かではなかったのである。このことからもわかるように、当時のオスマン朝が交易によって中国陶磁を直接に得て、そのコレクションを保持できるような状態であったとは考えにくいのである。前者のグル−プについては、オスマン朝がその領土を回復する十五世紀前半期以降、近隣の王朝を攻略し、その支配を拡大していく過程で戦利品あるいは献上品として獲得したものではないかと考えられている。1514年の目録には、セリム一世がペルシアのサファヴィ朝の皇帝イスマイルに戦勝した際に、タブリ−ズのヘシュト・ベヘシュト宮殿から戦利品として六十二点の中国陶磁を持ち帰ったという記録がある。タブリ−ズは十三世紀後半から十四世紀にかけて、モンゴル帝国の一部であったイル汗国の首都であったから元から陶磁器がもたらされていたであろうし、サファヴィ−朝のアッバス一世がアルデビル寺院に奉納した中国陶磁の中には、元時代の陶磁器が多数含まれていたことからも、この戦利品に元時代の陶磁器が含まれていたということが推察される。この記録は、セリム一世がアレッポ、ダマスカス、カイロへの遠征を行なった際にも、同様のことが行なわれたということを示唆している。とくにマムル−ク朝征服時に、膨大な量の元時代・明初期の中国陶磁が戦利品としてトプカプにもたらされたのではないかと、三上氏はフスタ−ト遺跡の調査から推測している
。トプカプ宮殿に収蔵されている十五世紀初期までの時期に造られた中国陶磁は、中東・西アジア地域の有力者達のコレクションの姿を写し出していると言える。なお、三杉氏はトプカプのコレクションの中には、征服前のイスタンブル、つまり東ロ−マ帝国の首都、コンスタンティノ−プルにおけるコレクションも含まれているのではないかと述べている
。中国から東ロ−マ帝国に至るル−トは解明されていないが、オランダやポルトガルによって喜望峰を回るル−トが開かれる以前に、中国から東ロ−マ帝国を経て、ヨ−ロッパへ達するル−トが存在していた可能性を指摘している。
十五世紀後半以降、明中期以降の中国陶磁のグル−プは、交易によってもたらされたものが主である。「正徳年製」の銘が入ったものは、明王朝からの賜与品であると考えられる。これに関して、ポ−プ氏はパウル・カ−氏の研究を援用して、アラビア文字でコ−ランの章句が表わされた陶磁器が明の武宗正徳帝からセリム一世へ贈られたという記述が、アラビア商人サイ−ド・アリ・エクベルが著わした『キタイ・ナ−メ』に見られ、トプカプにこれに該当する陶磁器があり、文献的に裏付けるものではないかとしている
。この時期の陶磁器も、やはり海上ル−トをたどってきたものと考えられる。中国からイスタンブルへ至るまでのル−トが三杉氏によって示されている
。メインル−トの一つは、インド洋から紅海に入り、ス−ダン北端のアイザ−ブに上陸してナイル川上流に達し、ナイル川を下ってカイロ、或いはフスタ−トからアレキサンドリアを経由して地中海へ出て、海路イスタンブルへ到達するものがある。もう一つは、ペルシア湾岸のホルムズに上陸し、陸路メソポタミア・イランを経由してシリアやレバノンの海岸に達し、そこから海路イスタンブルへ至るル−トである。
十六世紀以降の中国陶磁については、インド洋から喜望峰を回ってアフリカ大陸を迂回し、ヨ−ロッパを経由してからイスタンブルへもたらされたものが主であると考えられている。実際に、コレクションの中にはアルバレス瓶の通称で知られている、ポルトガルの貴族の紋章が入った染付がある。これはおそらく、中国からポルトガルへ運ばれ、紋章を入れられた後に、なんらかの理由でオスマン朝へもたらされたものであろう。嘉靖・降慶・万暦から、清の康煕・雍正・乾隆の時代にかけての中国陶磁は、当時のヨ−ロッパが大航海時代を迎えて盛んに世界各地との交易を展開していったことや、宮廷や貴族の間における東洋趣味が流行していたことを反映して、大量にヨ−ロッパへ運ばれた。トプカプ宮殿のコレクションの中で明中期以降のこれらの陶磁器がかなりの割合を占めていることから、このル−トで運ばれたものが最も多いと思われる。
さきほども述べたように、このコレクションには膨大な量の上質な中国陶磁が、破片などではなく完全な形で遺されている。このことが、とくに中国に遺されていない十四世紀の至正様式染付の特定を代表とする、中国陶磁の研究に大きな役割を果たした。コレクション全体から見れば数は目立っては多くないものの、とくに元末期から明初期にかけての染付は質・量ともに世界に比類のないものである。それは先の記述に従って言い換えれば、戦利品や献上品などとしてオスマン朝のもとに集められ、トプカプ宮殿に収められるまでの一世紀ほどの間、西アジア・中東各地でこれらの陶磁器が尊ばれ、大切に保管されてきたことの表れでもある。また、この時期の染付を模倣した陶器がエジプトやペルシアで生産されていたことがわかっているし、オスマン朝の下でもイズニックにおいて明らかにその形や文様をコピ−したとわかるものが造られた。なぜ染付が好まれたかということについては前節で触れたとおりである。また、このコレクションには、白磁・青磁・染め付け・赤絵などに金属製の蓋を付け加えたり、トルコ石やルビ−などの宝石をはめこんだりする細工が施されているものがある。極めて特殊な形で中国陶磁器がのこされている例であるが、それらに彼らの陶磁器の見方・捉え方がうかがわれて面白い。

<染付蓮唐草分筆箱 十五世紀末〜十六世紀初>
もともと西アジア・中東地域では古くから金属器の生産が盛んで、その細工も発達しており、中国陶磁器に対する需要は金属器の代替品として始まったという歴史がある
。現に、西アジア・中東地域との交易用として生産された中国陶磁器は、形・文様などの面でかなりこの地域で造られた金属器を意識して造られている。彼らにとっては、陶磁器も金属器も道具として同次元のものであり、金属器に施されていた装飾を陶磁器にそのまま施すことに違和感がなかったのではないだろうか。対照的に、日本では同じ染付についても元末期・明初期のような様式として完成度の高いものよりも、青藍色の発色が淡く、文様もどこか不完全なもののほうが茶人の間で愛されたということである
。同じ陶磁器の愛で方にも、それぞれの文化が育んだ美的感覚の違いが反映されるように思われる。トプカプ宮殿コレクションは、中世の西アジア・中東イスラ−ム世界の美意識の姿を具体的な形で見せてくれるものであると言えるのではないだろうか。
第四章 イズニック染付陶器
第一節 イズニック陶器生産の歴史
イズニックにおける陶器生産は、年代ははっきりしないが、オスマン朝がイズニックを支配下に入れる以前、ビザンティン帝国時代にはすでに始まっていたと考えられている。
ビザンティン時代の陶器生産がオスマン朝下のイズニック陶器生産に受け継がれたかについては解明されていない。しかし、オクタイ・アスラナパ氏の1960年代の発掘調査で、イズニックで「ミレトス陶器」と呼ばれる釉下彩技法によって文様の施された陶器が生産されたことが判明している
。この陶器は十五世紀以降に造られたものと思われるが、これがババ・ナッカシュ様式に始まるオスマン朝陶器の生産につながるものかということについては疑問がある。
オスマン朝下のイズニックにおける陶器の生産は、征服王メフメト二世がイスタンブルを攻略して首都とした十五世紀半ばあたりから始まったと考えられる。食器や儀式用の道具として使われる陶器と、建築物の壁面を装飾するタイルが盛んに生産された。しかし、イズニックと言えばトプカプ宮殿のハレムやスルタン・アフメット・ジャミィなどを代表とする装飾タイルが有名であるが、陶器の方はトルコ国内のコレクションにはあまり遺されていない。膨大な中国陶磁のコレクションを数世紀に渡って維持してきたにもかかわらず、トプカプ宮殿にも現在一点も陶器は遺されていない。オスマン朝宮廷の記録にもイズニック陶器が日常的に使用されたことを示すものは見つかっていない。しかし、残存するイズニック陶器は中国陶磁、とくに染付から多大な影響を受けながらも単にそれらの模倣に終わらず、極めて独自性の高いものが造り出されるに至ったほど成熟した。
十六世紀後半以降、ヨ−ロッパではその花文様のレパ−トリ−の豊かさや美しさの故か、イズニック陶器がもてはやされるようになり、多くの陶器が彼の地へもたらされた。ロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバ−ト博物館のコレクションなどにその多くが遺されている。そのことから考えても、イズニック陶器は単なる高価な中国陶磁の安価な代替品ではなく、オスマン朝独自の文化の一部として花開いたと言える。確かに、中国陶磁のコレクションの影に隠れてしまいがちではある。しかし、イズニック陶器は宮廷と無縁のものであったわけではなく、宮廷に購入されたり、あるいは宮廷から不要になったものが売却されたりしたという記録も残っている
。実際、イズニック陶器生産の盛衰には宮廷の産業への寄与が大きな要因となっているし、イズニック陶器の様式の変遷には宮廷の趣味や嗜好が生産の方向性として大きく関与している。ヌルハン・アタソイ氏は、イスタンブル市内やトプカプ宮殿内での大火災が頻繁に起こった時期と、イズニック陶器生産の最盛期が重なっていることから、おそらくイズニック陶器の良品のうちの多くが消失してしまったのではないかと述べている
。
現在、トルコ語ではイズニック・タイルのことをチニィ(cini)、イズニック陶器のことをケラミック(keramik)
と表現して区別している。ここでは、両者を厳密には区別せず、とくにイズニック・タイルという言葉を出す場合には陶器一般と区別したものとするが、イズニック陶器という場合にはとくに断わらない限りはタイル以外の陶器の総称とする。両者の使われ方が違うことがそれぞれの持つ特徴に違いを与えたということはできるが、様式の大きな差異が見られるというほどではない。ただ、十六世紀以降生産の重点がタイルにおかれるようになった頃から、それぞれの生産の展開に違いが見られるようになる。建築物の装飾に使われるタイルは規格をそろえることが必要とされ、材質はもちろんのこと、その文様や形などの表現は形式的なものに終始するきらいがあり、やや画一化が見られる。それに比べると、陶器の生産は比較的自由なもので陶工達のインスピレ−ションが生かされやすく、その形や図柄には彼らの豊かな表現力が反映された。陶器生産はタイルの二次的なものとして行なわれていたが、タイル生産の中で起こった様式の変容を取り入れるなどして、発展を遂げていったのである。タイル・陶器ともに、同時代の西アジア・中東イスラ−ム地域で行なわれていた陶器生産の中でも類の無い、独自性を持った作品がつくられた。
この時代のこの地域で行なわれた陶器生産は中国陶磁器のコピ−が主体となっていることから、高価で貴重な中国陶磁器の不足を補うという目的がまず第一にあったものと思われる。イズニックもその例外ではなく、後に述べるようにその初期には元・明時代の染付陶磁器と見まごう程に模倣したものが造られている。オスマン朝宮廷の記録に残っているイズニック陶器購入の記録からも、中国陶磁器の代替品として需要したというイズニック陶器と宮廷との関係が浮かび上がってくる
。
イズニックの陶器生産にはその初期から宮廷の産業に対する庇護は見られるが、オスマン朝宮廷は中国明王朝の官窯のような宮廷専用の工房や窯を持っていたわけではないようである。宮廷の注文に応じて陶器やタイルが生産されたと同時に、宮廷が市場を通じて購入することもあった。市場での購入の割合が増えるということは、一面、宮廷の産業に対する関心が薄れていくということを表わしている。十六世紀末には、イズニック陶器に対する宮廷の需要に変化が起こり始める。イズニック産のものについては、奢侈品としての陶器よりも日常品としての実用的なものが求められるようになっていったのである。トプカプ宮殿の中国陶磁コレクションに明の嘉靖期以降の陶磁器がかなりの数量あることからも、時期的に考えて、高級品としての陶器の需要が中国陶磁器に押されていったものと容易に推察される。
十七世紀に入ると製陶技術にもその様式にも発展は見られなくなり、時代が下るにつれてイズニック陶器の質は落ちはじめた。1648年にイズニックを訪れたエヴリヤ・チェレビはその記述に、スルタン・アフメットの治世期から宮廷の圧力によってイズニックの工房が激減し、産業が衰退しつつあったことを示している
。イズニック衰退の要因としては、宮廷の価格統制によって経済的に逼迫していったこと、周辺の交通事情の変化によってイズニックが時世の流れから取り残されていったことなどが挙げられる。このような外生的な要因から、イズニックの陶器産業を巡る事情は悪化し、中国陶磁器や同じオスマン朝の中のキュタヒヤ陶器との競争力を失っていったのであろう。作図はずさんになり、彩色もかつてのものと比べると鮮やかさを失い、胎土も粗く、施釉の技術も落ちている。イズニック陶器産業の断絶については依然解明されていない部分は多いが、十七世紀以降のイズニック産の作品の質の著しい劣化を見ると、イズニック陶器産業が衰退の一途をたどったと考えられる。オスマン朝下の陶器生産の中心がいつキュタヒヤに移ったのか、イズニック陶器産業がいつ断絶してしまったのかについては定かではないが、十七世紀中には移っていたものと思われる。イズニックでは現在はほとんど陶器産業の面影は残っていない。
第二節 イズニック陶器の様式の展開
征服王メフメト二世期に始まるオスマン朝陶器としてのイズニック陶器初期に、ババ・ナッカシュ様式陶器がある。ババ・ナッカシュとは、メフメト二世期の写本芸術の大家である。彼が写本に施した装飾のデザインが陶器の文様に取り入れられ、彼の名を取ってババ・ナッカシュ様式と呼ばれている。十五世紀のティム−ル朝芸術に見られた「国際ティム−ル朝様式」と呼ばれた中国風の花文様に更に手を加えて、アラベスク文様と組みあわせて用いた、オスマン朝美術独自の文様で、ル−ミ−・ハタイ文様といわれている。この様式の陶器の作品には十五世紀末頃から、硬質できめが細かく真っ白な良質の素地に釉下彩技法による装飾の施された、いわゆる染付陶器の中でも良質なものが表われる。その素地の美しさ、コバルトをふんだんに使った鮮やかな青藍色の発色は、中国の元末・明初期の染付磁器を連想させる。同時期、周辺の西アジア・中東地域の陶器生産において中国陶磁のコピ−が熱心に行なわれていたことからも、このババ・ナッカシュ陶器が中国の染付陶磁の影響を受けて造られたと考えて良いだろう。しかし、この陶器はその独自のル−ミ−・ハタイ文様のゆえか、単なる中国陶磁のコピ−には終わっていない。これは、オスマン朝陶器美術の開花であるといってよいだろう。
しかし、イズニックの創始期からこれほどオスマン朝独自の陶器として完成度が高いものが造られたことについては疑問がある。しかし、ババ・ナッカシュ陶器の登場以前にイズニックで生産されていたミレトス陶器は大衆的な陶器で大量生産されていたのに対し、ババ・ナッカシュ陶器は宮廷の影響の強い高級品で性格が異なることから、ミレトス陶器の発展上にあるとは考えられない。ババ・ナッカシュのデザイナ−の中に、ティム−ル朝下のサマルカンドへ捕虜として連れていかれ、ティム−ル朝芸術に感銘を受けた、アリ・ビン・イリアス・アリという人がいる。この人物は、ブルサのメフメト一世モスクの建設にも関わっているが、このモスクの建設にはタブリ−ズから陶工が連れてこられてタイル製作に関わっている。その他、タブリ−ズの陶工達の作品としてはエディルネのムラト二世モスクがある。彼らの製作したタイルは、白地藍彩の染付タイルで、ババ・ナッカシュ陶器と類似している。彼らがイズニックでタイル生産を行なったのではないかとも推測される。しかし、実際にイズニックでタブリ−ズの陶工達が活躍したということを示すような痕跡は見つかっておらず、胎土の生産技術も異なっている
ことから、彼らがババ・ナッカシュ陶器を生み出した可能性も否定されている。
スルタン・バヤジット二世期には、ル−ミ−・ハタイ文様のバリエ−ションは更に豊かになり、飾り結びの文様と、中国陶磁に使われた雲文が見られるようになる。この時代には、コバルトをたっぷりと用いて、いわゆる白抜きで文様が表わされている。メフメト二世期のものよりも、白い部分が大きくなり、素地の美しさと青藍色とのコントラストが生かされている。
セリム一世期には、オスマン帝国は更に領土を広げ、オスマン朝はこの時代に西方の覇者となり、東西交易ル−トに大きく関わることになった。第三章でも述べたように、彼はサファヴィ−朝下のタブリ−ズを攻略してヘシュト・べへシュト宮殿から中国陶磁器の優品を持ち帰った。記録には残っていないが、ダマスクスやカイロを征服した際にも同様に彼の地で保有されていた中国陶磁器を持ち帰ったと考えられる。また、タブリ−ズからタイル工や絵付け師を連れて帰ってきたという記録も残って下り、その中に、スレイマン大帝期にサズ葉文様を編み出したシャフク−ルも含まれていた
。大量の戦利品を得た一方で、交易ル−トを押えたこの時期以降に、中国陶磁器は盛んに輸入されるようになった。この社会背景がイズニック陶器生産に大きく影響を及ぼしたことは容易に推察される。オスマン朝の拡張、それに続く繁栄を受けてか、この時代に市場が活発になった。それまでは、ほぼ宮廷用の高級品に限られていたイズニック陶器も市場で大量に取り扱われるようになり、この時期から徐々に大衆化の傾向が進み始める。生産量が多くなったことの影響としては、陶器生産にかける労力の節約のために、製作方法が簡略化されるようになったことが挙げられる。コバルトをふんだんに使って白抜きで文様を表わす方法から、白地に藍の文様を描く方法が多く用いられるようになった。また、文様も複雑に絡み合った文様から、やや小さなモチ−フの連続文様が繰り返されたものが多くなっている。
セリム一世期に続くスレイマン一世(大帝)治世の初期には、ババ・ナッカシュ様式に加えて、中国陶磁器の完全なコピ−品、陶工様式、ゴ−ルデン・ホ−ン(金角湾)様式、そしてサズ様式が登場する。この時期にはイズニックの陶器生産において様々な試みが見られ、新しい様式が生まれて展開していったのである。この時期には、セリム一世期に大量にもたらされた中国陶磁を明らかに模倣した陶器が登場しているのと同時に、ババ・ナッカシュ様式と中国陶磁器の特徴を混成させた陶工様式が登場する。具象的な花の図柄が採用されるようになり、そのアレンジには中国陶磁器における草花文の図柄の影響がうかがわれる。これが陶工様式と呼ばれる所以は、宮廷の影響から離れて陶工達の自由な発想が生かされているところにある。この頃宮廷では中国陶磁器の愛好が進んでイズニックに対する宮廷からの注文が減り、イズニックの工房が市場における新たな顧客を求めていったことからこの様式は生まれたと考えられる。スレイマン大帝期から、明らかに品質の劣るより安価な庶民向けの陶器もイズニックで生産されるようになるのである。いわゆるゴ−ルデン・ホ−ン様式は、公文書に書かれたスレイマン大帝のサインを表わす、花押文を飾る渦巻き文様が施された陶器である。この陶器が金角湾のそばで発見されたとか、生産されていたという誤解からついた名であるが、この生産地もイズニックである。この名前がこの様式の正しい理解の妨げなることから、ジュリアン・レイビ−氏はこの独特のこまやかな花小枝の渦巻き文様を持つ陶器を、トゥ−ラケシュの螺旋様式と呼んでいる
。サズ様式は、先ほども述べたようにセリム一世によってタブリ−ズより連れてこられた絵師のシャフク−ルによってオスマン朝宮廷にもたらされた。もともとサズ葉文様はサファヴィ−朝の絵画から始まったもので写本芸術に用いられていたが、後にオスマン朝で陶器の文様として使用されるようになった。鳥の羽根のような形の長い葉がそれである。ババ・ナッカシュ様式は新しい様式の誕生に押されるようにして、影が薄くなっていく。ババ・ナッカシュの要素を取り入れたものは継続してみられるが、そのものの作品が造られたのは、この時期が最後であると思われる。また、この時期に多彩陶器生産の下地が見られ始める。それまでは、白地に藍一色であったが、この頃から青色のバリエ−ションが増え始め、青菫色やトルコ石色、更に薄い水色など同系色ではあるが色が塗り分けられるようになる。
スレイマン大帝の治世中期にかけては、顔料が開発され、緑、紫、黒などさらに使用される色が多くなり、多彩への移行が進んでいく。この時期の陶器やタイルを総称して、ダマスクス様式として分類するのが一般的である。しかし、レイビ−氏はこのダマスカス様式陶器は1530年代から1550年にかけての時期の紫の使われていないタイプと、1550年代移行の紫も使用されているタイプとに峻別することができるとしている
。この時期のいつごろかは明確ではないが、黒の顔料によって輪郭線が描かれるようになり、陶器の図柄はますます絵画的なものになっていく。また、ゴ−ルデン・ホ−ン様式や陶工様式のものに見られる、図面を埋め尽くすような装飾性は抑制され、白地の部分は背景として残されることが多くなり、ややすっきりとした印象を与え、一つ一つのモチ−フがはっきりと判別できるものになっている。文様にはあらゆる花、果実、草木が組み合わせて用いられるようになり、後のイズニック陶器、タイルの図柄の基底をなすデザインであると言える。そして、この様式の登場から、イズニック陶器の主流は白地藍彩の染付タイプから離れて行き、より色彩の華やかなものが登場するのである。
スレイマン大帝治世期には、スレイマン一族を記念する建造物の建築がしばしば命令され、それらの内部を装飾するタイルもその度に大量に注文された。彼の治世期の前半期には、まだタイルよりはその他の陶器一般のほうが生産の中心であったと言えるが、その後期、1550年代以降は、むしろタイル生産の重要性が増してくる。そのことが、オスマン朝陶器に対する色彩感覚の転換を招いたのであった。十六世紀前半期には、タイルはほとんど白地藍彩の染付タイプの六角形タイルがほとんどであったが、後半期からは使用される色は多くなり、形も四角形のものが多くなった。いわゆるダマスカス様式のタイルが造られるようになってほどなく、紫の代わりに、より鮮明な赤が用いられるようになった。陶器と違って少し離れたところから眺める装飾タイルには、存在感の薄くなりがちな紫よりも、青や白などその他の色にかき消されることの無い赤の存在感が求められたのである。赤色は本来陶磁器においては扱いにくい顔料であるが、厚いスリップ掛けが可能になった。この赤が使用された例には、マムル−ク朝の陶器があり、そこから影響を受けているものと思われる。この赤は薄めて使うことができず、赤が盛り上がるような仕上がりになっている。これがイズニックタイル・陶器の特徴として有名な、トマト赤である。この頃から、チュ−リップ、カ−ネ−ション、バラ、ヒヤシンスの四種の花を主に用いた四花文様式が登場する。この図案は、宮廷画家のカラ・メミによって始められたのではないかと言われている。スレイマン治世末期には、ボ−ル・レッド(紅土質の鮮紅色)が見られるようになる。この時期から異なる土の色を一つの作品において併用したものが始めてみられる。また、文様には初めて絨緞の意匠が取り入れられている。
多彩陶器が多く造られるようになったものの、セリム二世期にも白地藍彩の染付は依然として生産されていた。また同時に、それとは対照的な青やオレンジがかった赤などの色地のスリップ・ウェアが造られていた。イズニックの初期には白地に白またはオフ・ホワイトのスリップが好まれていたが、この時代あたりから色スリップも使われるようになるのである。
ムラト三世治世期から、イズニックの陶器生産に衰退の影が見え始める。彼の時代には、挿絵入りの写本芸術が庇護されたが、タイル生産注文は減少し、これがタイル生産技術の低下を招いたと言われている。この時期には一旦廃れたババ・ナッカシュ様式が復活したり、サズ葉文様に花を組み合わせたり、帆船文や動物文・人物文などの具象的な文様が多く登場するようになるなど文様のバリエ−ションは豊かであった。しかし、彩色技術のほうは追求されなかったようで、とくに進展はない。この時期には古典期のもののリヴァイヴァルが見られるが、この時期からイズニック陶器の様式の進歩的な展開は見られなくなるのである。
第三節 中国の染付陶磁とイズニック染付
初期のババ・ナッカシュ陶器はイズニック染付陶器の出発点であると言える。このババ・ナッカシュ陶器が中国の染付の影響を受けて造られているとはいいながら、中国染付磁器の模倣に走っていない点が興味深い。明らかに模倣したと一見してわかるものが造られるようになるのは、ババ・ナッカシュ陶器の登場からさらに時代を下ったセリム一世期なのである。オスマン朝イズニック陶器のごく初期に受けた中国の影響というのは、鮮やかな白地にコバルトを用いて美しい白と青藍色のコントラストを見せるというコンセプトの面においてであったと思われる。白抜きで文様を表わす彩色の施し方には、元の至正様式の大皿との類似性が見られることから、元染付磁器の影響を受けていると考えられる。オスマン朝美術の中では、陶器が発達する以前に写本芸術や、金属器・カ−ペットなどの他の工芸品が発達していた。イズニック陶器はそれらの装飾に用いられた文様を使っている。ババ・ナッカシュ陶器は文様・図案の面から考えるとオスマン朝下で造られていた金属器の影響が強いようである。文様、モチ−フの細部にはいわゆる中国的な要素も含まれている。ル−ミ−・ハタイ文様のハタイというのは中国由来のものであるということを意味している。しかし、西アジア・中東イスラ−ム地域で生産された金属器と中国陶磁とが古くから関わりを持ち、交易を通じてお互いに影響を与えあってそれぞれの形・文様を展開してきたことから考えても、中国陶磁からの直接の影響を論じることはできないであろう。彼らが取り入れたいわゆる中国的な要素も、すでに金属器生産の中で消化され、言うなれば西アジア・中東イスラ−ム風にアレンジされていたと考えられる。陶器の器面を構成する図案は、中国的というよりはオスマン朝的と呼びうるものである。
イズニック陶器の図案には、草・花・木・果実などの植物文様や、波頭文様などの抽象文様が好まれ、用いられた。これらの文様の組合せは、イズニック陶器生産を通じて多用される。これらのモチ−フのデザイン、図案における使われ方には明初期の永楽・宣徳期の染付磁器の影響が大きい。葡萄文を主文様とするもの、アラベスク状の花文を主文様とするものに明初期の中国磁器と見まごうほど完全に模倣している作品が見られる。これらの陶器はセリム一世期以降に造られたことから、彼の遠征でもたらされた中国陶磁器との関連性が深いと考えられる。また、その他にも蓮の花束文様もその図案の形から見て模倣が試みられたものである。これらの図案は、中国陶磁器の模倣に始まり、やがてイズニック流にアレンジされて、非常に装飾的なものへと変化していく。明の染付磁器の図案のほうがコバルトのむらによって立体感を感じさせ、写実的な印象を与えるのに対し、イズニック陶器のほうは平面的でやや写実性の面から見れば劣る。陶器の絵付け技術の違いもあるだろうが、美的感覚の違いをうかがわせる。イズニック陶器の図案は全般に平面的な印象を与えるものが多い。写実性を重んじず平面的な傾向が強いのは陶器の図案に限ったことでなく、例えばミニアチュ−ルにも同様の傾向が見られることから、ミニアチュ−ルから文様を取り入れるなどしてその装飾の影響を強く受けている陶器についても、そのような美的感覚でもって捉えられたと言えるのではないだろうか。皿の形も、稜花形の輪郭が使われ、中央の見込みの部分に主文様を置き、カヴェットの部分には器面を分割して花文様や蓮弁文を模したものがおかれた。カヴェットの部分は、明時代のものには、花のアラベスク文で装飾されている場合と器面を分割して一個一個モチ−フを置く場合とがあるが、器面を分割した場合、皿の縁の切れ込みの数と一致しているのに対して、イズニックのものは必ずしも一致しておらず、左右対称でないこともある。またイズニックのものの文様には規則性はなく、組合せ方もその時々によって異なっている。このような相違はイズニックの職人が中国の職人ほど構図やデザインに対してこだわりを持っていなかったためであろうとジュリアン・レイビ−氏は述べている
。

<葡萄文皿 左が中国の染付陶磁、右がイズニック染付>

<花唐草文皿 左が中国の染付陶磁、右がイズニック染付>
ここで挙げた明の染付葡萄文皿と染付花唐草文皿の外縁部には波頭文様が施されているが、イズニックの皿もそれを明らかに模倣している。しかし波頭文様とわかるものもあるが、波頭文様を取り入れて行くうちにそれがどんどん様式化していって、小さな渦巻き円がたくさん集まったもののようになる。
明初期の染付と比べると、イズニック染付陶器には文様の形や図案の構成にほとんど制約がないように見受けられる。中国磁器におけるそれぞれのモチ−フ・文様が中国の人々にとっては何か図象学的に意味を持つものであったとしても、オスマン朝の人々にとっては単なるモチ−フや文様にしか過ぎず、その用い方に制約もル−ルもないが故に、彼らの様式の中に柔軟に取り入れられたものと考えられる。
多彩陶器が登場してからも、白地藍彩の染付タイプのイズニック陶器は造られ続けた。一方、十六世紀後半以降のイズニックのタイルについては、このタイプのものはほとんど見られなくなり、多彩のより華やかな方向へと進んでいった。多彩タイルの勢いに押されて、十六世紀以降の白地藍彩染付タイプの陶器は忘れられがちであるが、多くの作品が残されている。この時期の陶器には、一見したところ中国陶磁器の影響がうかがえないように思われる。しかしレイビ−氏は、いわゆる元の至正様式や明の永楽・宣徳様式のみならず、十五世紀末から十六世紀初頭にかけて輸入された陶器からも、イズニックはインスピレ−ションを与えられていたと述べている
。これらの陶磁器は中国で中東への輸出向けに造られたものであると考えられている。弘治年間前後に生産された、文様のぎっしりと描き込まれた陶器の中には、巻き込みの強い葉文様がよく見られる。この文様がアレンジされて「三つの渦巻き」文様が登場したということである。この文様は、主文様の背景として三つ一組になった渦巻き円が器面の至るところに散らされているものである。また、先ほど明初期の染付磁器の完全な模倣として取り上げたアラベスク状の花文の系統の、渦巻いた花文等も見られる。花文の配置の仕方や蔓の絡ませ方に、十五世紀前半期のものとは異なった趣が見られる。またこの時期には、麦束文様がモチ−フとして多用された。図案に方向性を与えるもので、サズ葉文と似た使い方をされる。中国の陶磁器装飾の中のかぎ形の葉が、オスマン朝で独自のアレンジを加えられて、オスマン朝的な文様になった好例だということができる。このモチ−フは様々な使われ方をした人気の高いもので、優雅な雰囲気を醸し出している。植物文様だけではなく、抽象文様も使われている。中国陶磁器の蓮弁文が様々な形にアレンジされて、器面に放射状に施されているものが多く見受けられる。

<花鳥文皿 左が中国の染付陶磁、右がイズニック染付>
十六世紀の後半には、嘉靖年間の染付陶磁器が輸入され、その中でも、築山のデザインが取り入れられた。植木鉢に花があしらわれているものがそれである。しかし、この時期ごろからイズニックの陶工達はあえて中国陶磁器の影響を排除しようとしている面が見られる。いかにも中国風を意識したというような陶磁器が造られなくなっていくのである。しかし、宮廷の好む陶磁器は中国のものであることが多かったこともあって、この動きはイズニックの陶器産業にはプラスにはならなかったようである。やがて、質だけではなく量のうえでも中国陶磁器はオスマン朝におけるイズニック陶器を陵駕していき、宮廷の中国陶磁器愛好はイズニック陶器の衰退の一因となったのである。
イズニック染付陶器の変遷を見てみると、中国陶磁器の影響があったといっても、彼ら自身のアイデアで独自の様々な図柄、彩色、形の陶器が生まれていると思われる。白地藍彩のイズニック染付が様式を展開して、後には白いスリップをかけた素地にトマト赤、鮮やかなトルコ青、緑などを用いた艶やかな多彩陶器が造られるようになる。中国のほうでも、単色の染付から、やがて五彩などの色絵に流れが傾いていく。しかしそれぞれの多彩陶器・磁器を見てみると、当たり前のことながら、背景となっている美的感覚が余りにも違うことに気づかされる。彩色の組合せ、図案の構成、文様のバリエ−ション、器形、大きさなどの様々な要素が組み合わさって形成するそれぞれの美術的価値は、様式が発展していくにつれて次元の違うものになっていった。同時代における生産技術については中国のほうが常に数歩先のリ−ドをとっていたものの、イズニックは影響を受けながらも中国の足跡をたどることに終始するのではなく、イズニックなりに捉え得た中国の陶磁器生産の長所を取り入れて消化し、独自性を持つ陶器を早い時期から生産し始めたのであった。
イズニック陶器の持つ図案の細かさ、鮮やかな赤と青を対比させる彩色の大胆さは、オスマン朝の風土と人があって初めて成立しえたものであるといえよう。
参考文献
- Aslanapa, Oktay. Turk Sanati, Istanbul,1993, pp.317-332.
- Atasoy, Nurhan and Raby, Julian. IZNIK: The Pottery of Ottoman
Turkey, London,1989.
- アタソイ、ヌルハン&レイビ−、ジュリアン著 加藤卓男監訳『イズニク オスマン・トルコ幻の名陶』中央公論社、1996年。
- 藤岡了一著『陶磁大系42 明の染付』平凡社、1975年。
- 深井晉司著「イスラムの美術」嶋田襄平編『東西文明の交流3イスラム帝国の遺産』平凡社、1970年、301-341頁。
- 長谷部楽爾著「陶器」深井晉司編『大系世界の美術8イスラ−ム美術』学習研究社、1972年、287-296頁。
- 長谷部楽爾監修中沢富士雄・長谷川祥子編著『中国の陶磁第八巻 元・明の青花』平凡社、1995年。
- 小山富士夫著『陶器全集第十一巻 元・明初の染付』平凡社
- 小山富士夫著「イスタンブ−ルの古陶博物館 トプカプ・サレイ博物館」『芸術新潮』13:10、1962年10月、38-39頁。
- 三上次男著「イスラム美術と中国」上野照男:三上次男編『世界美術全集22オリエント(3)イスラム』角川書店、1962年、188-200頁。
- 三上次男&ケマル・チュ−著、護雅夫訳、並河萬里写真 『中国陶磁 トプカプ・サライ・コレクション』 平凡社、1974年。
- 三上次男著「イスラ−ム陶器の成立・発展と中国陶磁 イスラ−ム陶器研究序説」三上次男編『世界陶磁全集21』小学館、1986年、127-136頁。
- 三上次男著『三上次男著作集1 陶磁貿易史研究上(東アジア・東南アジア篇)』中央公論美術出版、1987年。
- 三上次男著『三上次男著作集2 陶磁貿易史研究中(南アジア・西アジア篇)』中央公論美術出版、1988年。
- 三上次男著『三上次男著作集3 陶磁貿易史下(中近東篇)』中央公論美術出版、1988年。
- 三上次男著『三上次男著作集4 中国陶磁史研究』中央公論美術出版、1989年。
- 三上次男著『三上次男著作集6 イスラ−ム陶器史研究』中央公論美術出版、1990年。
- 三杉隆敏著「トプカピ・サライの中国陶磁(1)染付」『みづゑ』745
、1967年2月、34-43頁。
- 三杉隆敏著 「トプカピ・サライの中国陶磁(2)リフォ−ムされた器とその海上交易ル−ト」『みづゑ』746、1967年3月、41-51頁。
- 三杉隆敏著「中近東に残る中国の染付」『日本美術工芸』358、1968年7月、7-25頁。
- 三杉隆敏著「染付の青料コバルトの謎」『日本美術工芸』507、1980年12月、60-68頁。
- 三杉隆敏著『世界の染付1 元』同朋舎出版、1981年。
- 三杉隆敏著『世界の染付2 明初期』同朋舎出版、1982年。
- 三杉隆敏著『世界の染付3 明後期・清』同朋舎出版、1982年。
- 三杉隆敏著『世界の染付4 伊万里・李朝・安南』同朋舎出版、1987年。
- 三杉隆敏著『世界の染付5 西アジア・ヨ−ロッパ』同朋舎出版、1983年。
- 三杉隆敏著「染付と海のシルクロ−ド」『日本美術工芸』559、1985年4月、15-20頁。
- 満岡忠成著「トルコ染付火炉」『日本美術工芸』408、1972年9月、98-99頁。
- 佐賀県立九州陶磁博物館編『トプカプ宮殿の名品 スルタンの愛した陶磁器』毎日新聞社、1995。
- 護雅夫監修 並河萬里写真 高橋昭一訳『トプカプ宮殿博物館 宝物館』トプカプ宮殿博物館全集刊行会、1980年
- Oney, Gunur. Turk Cini Sanati, Istanbul,1976.
- オネイ、ギョニュル著、水野美奈子訳「トルコのイスラ−ム陶器」『世界陶磁全集21』小学館、1986年、211−232頁。
- Porter,Venetia. Islamic Tiles. London, British Museum
Press,1995.
- 佐々木達夫著『元明時代窯業史研究』吉川弘文館、1985年。
- 高橋忠久著「イスタンブルとトプカプ宮殿」『出光美術館報』55、1986年8月、8-16頁。
- 高橋忠久著「トルコ・トプカプ宮殿秘宝展 オスマン朝の栄光」『古美術』87、1988年7月、112-116頁。
- 東京国立博物館編『特別展 中国の陶磁』 1994年。
- Wilson, Eva. Islamic Designs, London, British Museum
Publications,1988.
前ページに戻る


 <洪武期の作品>
<洪武期の作品>


 <成化期の作品>
<成化期の作品> <弘治期の作品>
<弘治期の作品>

 <嘉靖期の作品>
<嘉靖期の作品>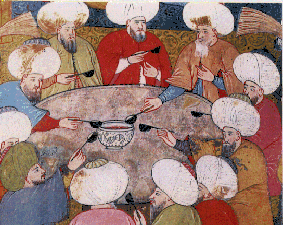 <アフメト三世のス−ルナ−メより(Levni画)>
<アフメト三世のス−ルナ−メより(Levni画)>


