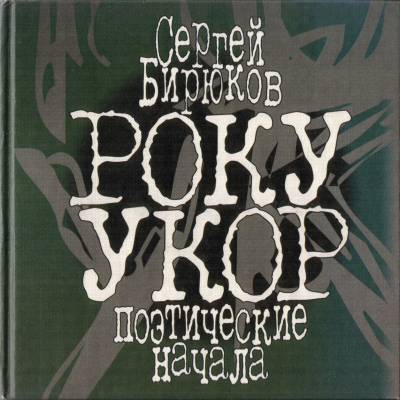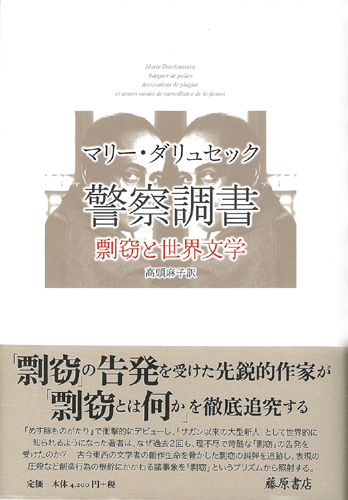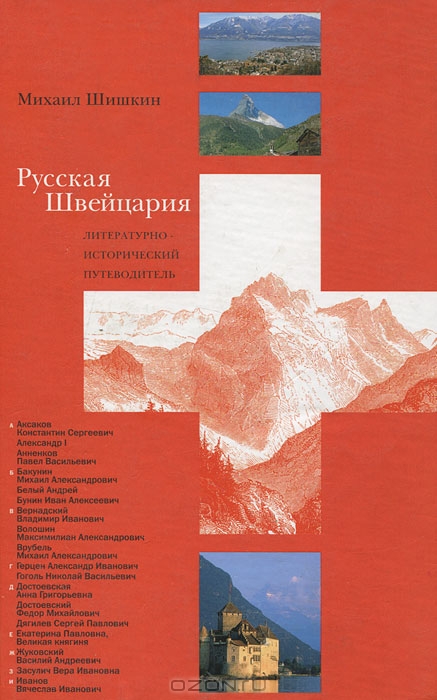派遣留学でペテルブルグに滞在している沼野ゼミ3年の工藤順(なお)くんがホットな文化情報をいろいろ送ってくれるので、随時このブログで紹介していくことにした。
これからロシアに留学するという人、ロシア文化に興味がある人、ペテルブルグが好きな人にはきっと面白くて役に立つ情報が満載だと思う。どうぞご贔屓に!
まずはペテルブルグ演劇案内。工藤くんが実際に自分で行った劇場について、自分の肌で感じた印象について、芝居の内容とともにお伝えする。第1回目は「定番」の劇場から。
「超個人的ガイド to ロシア(文責:工藤なお)」 (1)
★「ペテルブルグ演劇案内①」
定番篇①「アレクサンドリンスキー劇場」Александринский театр
演目:『検察官』(9/26)、『分身』(11/7)
堀江新二他著『ペテルブルグ舞台芸術の魅力』(東洋書店、2008)で事前に予習した限り、ペテルブルグ演劇といったらこの人!というビッグネームは主に2人、ワレリー・フォーキンとレフ・ドーヂンだと言えるでしょう。それは確かに事実のようで、フォーキン率いるアレクサンドリンスキー劇場、ドーヂン率いるマールイ・ドラマ劇場はペテルブルグで最も有名かつ実力のある劇場であると言って間違いないと思います。その内の前者、フォーキンの演出になるゴーゴリとドストエフスキーです。
フォーキンの演出は、後にマルイシツキー小劇場(小劇場篇参照)についても述べることですが、身体の制御の仕方・音楽の用い方が際立っています。(が、マルイシツキーとは別の次元ではあります。)
『検察官』(ゴーゴリ原作)の演出は、メイエルホリドの演出案を元にフォーキンが演出しなおしたもの、と書けばアヴァンギャルド界隈の人は思わず腰を浮かしてしまうことでしょう。実質演出家が2人存在することになり、この劇の功績が正確にはどちらに属するのかは分からないものの、2人の才能がぶつかった結果の産物と捉えるのが正解だと思います。
まず最初に、「遅れてやってきた観客」の態で主人公フレスタコフが登場し、劇が始まります。彼は客席の合間をぬって舞台上にたどり着くと、舞台中央にある椅子(ステージの方を向いて設置されている)に腰をかけます。この時点で『検察官』という物語がモチーフとする「(我々を見張る)眼」という構造が、何とも軽々と舞台上に設定されてしまうのです。観客はその枠を脳裏に置きながら舞台を観ることになるでしょう。
随所に挟まれるダンス的な集団行動、客席で演奏され始める奇っ怪な音楽、それはマルイシツキー小劇場の「自由芸術家工房」劇団が有する若く激しい身体性とは方向性からして異なる、奇妙で不器用な、しかし思わず笑ってしまうような身体性です(その後ろにはもちろん正確な肉体的鍛錬が存在します)。ふと思ってみたのですが、それは「ゴーゴリそのもの」ではなかったでしょうか。ゴーゴリは超一級のコメディ作家であり、この劇は最初の主人公の登場から劇の終りまで笑いでもって観客を捉えて離さない恐ろしい劇でした。
『分身(二重人格)』(ドストエフスキー原作)も路線としてはシリアス劇というよりはコメディに近いです。『検察官』と同様、贅沢な大道具の用い方に目を見張ります。大道具は、「分身」のテーマに沿って、全面に鏡が貼られています。
演出は、『検察官』よりも先鋭的なメタ構造によります。舞台の最初と最後に観客席からあるアクションが起こることで、観客側にそれを印象づけることでしょう。
劇は、「役人」の役を演じる男女数名による集団行動的なダンス(あるいはダンス的な集団行動)から始まりますが、実際に物語の始まりを告げるのは主人公ゴリャトキンが客席から立ち上がり、「金を払って見に来ているのだからしっかりやれ!」といった旨の文句をステージに投げつける時です。ここで「劇場」という枠が明らかに策定されると同時に主人公ゴリャトキンの性格も一挙に把握されます。そしてクライマックスには二階席で一般人の格好をした俳優(おそらく)が立ち上がって、最初と同じように「納得できないな!」というような申し立てをステージに向かって行い、終劇となります。
この時点で観客としては、単純に拍手を送ることにためらいを感じてしまわざるを得ないでしょう。『分身』というテーマ設定だけでも相当におもしろいのに、フォーキンはさらに「劇」とは何か、「観客とステージ」の関係はどうあるべきか、といったメタ次元での問題設定をも孕ませてしまうのです(この点ではロシア・アヴァンギャルドの演劇、例えばそれこそメイエルホリドの演劇との接点を見いだすことも出来るでしょう)。
それは2時間弱の芝居に対しては過剰な要求かもしれませんが、何一つ不十分な印象は残しません。それは考えてみればすごいことです。そしてなにより、こうした演出が、歴史あるアレクサンドリンスキーの建物の中で行われている事実が、単純におもしろい。

アレクサンドリンスキーは、ネフスキー通り沿いすぐなので治安的にも安心。建物はオペラハウス並みの豪華さです。ペテルブルグに来て演劇をみるなら、一番にここに来てまず間違いないでしょう。開演1時間前に国際学生証をカッサに提示すれば、残っているチケットを半額で買えるそうです(試したことはありません)。