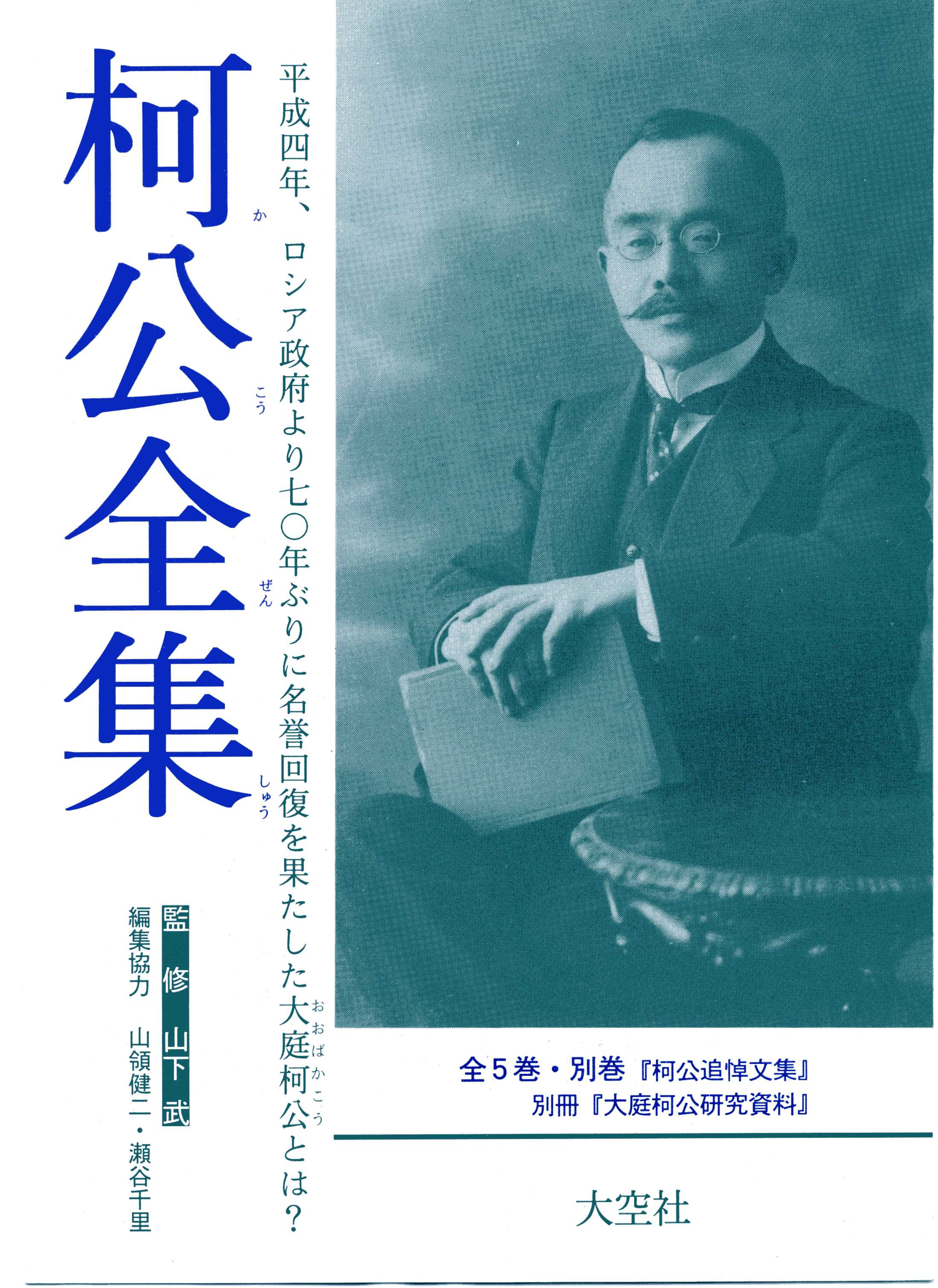現代ロシア映画における宗教
2011年度「指導教員が勧める優秀卒業論文」として、私のゼミから御園生みのりさんの卒論『現代ロシア映画における宗教』が東京外国語大学のHPに掲載されている。
↓
http://www.tufs.ac.jp/insidetufs/kyoumu/doc/yusyu23_10.pdf
ソ連崩壊後のロシア社会に「宗教復活」とも言える現象が見られ、ロシア映画に宗教のモチーフが目立つようになってきたことを踏まえ、激変する現代ロシアで映画が宗教にどのように向き合おうとしているのかを分析し、その意味するところを考察したアクチュアルな研究だ。
扱っているのは3人の映画監督の作品それぞれ2本ずつ、計6作品。
ウラジーミル・ホチネンコ(1952年生れ) 『司祭』『イスラム教』
バーヴェル・ルンギン(1949年生れ) 『ツァーリ』『島』
アンドレイ・ズヴャギンツェフ(1964年生れ) 『追放』『エレーナ』
ホチネンコ監督の『司祭』(2010)は、ロシア正教を共産主義イデオロギーに替わるものと見なす国家の後押しを受けて作られたもので、聖職者たちが高潔な人物として描かれている。『イスラム教徒』(1995)は、異教徒に対する不寛容をテーマとしており、現代ロシア社会の矛盾を象徴している。
ルンギン監督の『ツァーリ』(2009)は、イワン雷帝を主人公にすることで、信仰心が篤くても残虐でもあり得るという矛盾した人間の姿を現代に通じる問題として突きつけ、『島』(2006)は、教会という制度から逸脱した主人公に現代の「貧しき人々」の救済を見出そうとしている。
ズヴャギンツェフ監督の『追放』(2007)は、表面的には宗教を扱っているようには見えないが、「楽園追放」「神殺し」といった宗教的モチーフを象徴的に用いており、『エレーナ』(2011)は、現代ロシアの日常に潜む「黙示録」的な要素を描きだしている。
このようにホチネンコ→ルンギン→ズヴャギンツェフと進むにしたがって、宗教的モチーフが「内在化」していくところが面白い。
『島』の主人公には、自らに過酷な苦行を課すことによって神に近づき時に奇跡を起こす力を得る「聖愚者(ユロージヴイ)」の面影が感じられる。

ルンギン監督『島』より